日本二百名山
信州百名山
甲信越百名山
中央線から見える山
日本の山岳標高1003山
日本2500m峰
日本の山1000
長野県の名峰百選
特選日本名山50
2000メートル以上の642山
槍・穂高・乗鞍
最終更新:ヤマレコ/YamaReco
穂高連峰を正面に捉える静かな二百名山

霞沢岳は長野県の山で標高は2646mです。北アルプスの東側に連なる常念山脈の南端にあたるとされており、日本日本二百名山に選ばれています。
北アルプスの代表的な登山拠点である上高地(かみこうち)に近接していますが、登山者は比較的少なく、静かな山行を楽しむことができます。
また北アルプス南部を見晴らす絶景が満喫できる山として知られています。

山名の由来は、南東斜面を流れる梓川の支流「霞沢」にちなむとされています。また、山に霞がかかりやすいから、とする他説もあるようです。
穂高連峰の大パノラマが魅力の山

霞沢岳の山頂部は見晴らしが良く、山頂を含むいくつかのピークでは穂高連峰をはじめ、焼岳や乗鞍岳などの名峰を一望することができます。八ヶ岳や南アルプス、白山などが見えることもあります。

山頂はハイマツに囲まれたこぢんまりとした場所です。その一角の草地には二等三角点がひっそりと設置されています。
登山の要衝・徳本峠

徳本峠は霞沢岳の東に位置する峠です。登山道の三叉路で、このうちの1本の道が霞沢岳を目指す唯一の一般登山道です。
残りの2本の道は松本市安曇地区の集落「島々(しましま)」と、上高地に通じています。古くは上高地へ向かう際、島々から徳本峠を経る道のりがメインルートでした。この古道は「徳本峠越え」と呼ばれています。

かつては近代登山の父と称されるウォルター・ウェストン(1861-1940年)や芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ:1892-1927年)、高村光太郎(たかむらこうたろう:1883-1956年)といった著名人も、島々からこの峠を通過し北アルプスに足を踏み入れていました。

峠に建つ徳本峠小屋は、大正12年に営業を開始した歴史のある山小屋です。本館は国の登録有形文化財に指定されています。
定番の登山ルートは上高地から

霞沢岳への入山口は上高地と島々の2か所がありますが、多くの登山者は上高地からのルートを選びます。

上高地よりしばらくは、緩やかな勾配の広い遊歩道を歩きます。

明神までは観光客の姿も多く、河童橋や明神池といった景勝地に立ち寄ることもできます。

徳本峠分岐からやや進むと、本格的な登りが始まります。黒沢に沿って道が付いており、何度か沢を渡りながら高度を上げていきます。

沢の水を汲んで給水する登山者の姿も見られます。

谷筋を登り詰めると徳本峠に到着します。徳本峠小屋に宿泊し、翌朝に山頂を目指す登山者も少なくありません。

徳本峠から先は、アップダウンを繰り返しながら山頂を目指します。
途中にはジャンクションピークやK1ピーク、K2ピークなど、アルピニズムを感じさせる名前のピークが連なります。
上級者向け・島々からのクラシックルート

一方の島々からの道は歩行距離が長く、健脚向けのルートです。より大きな達成感を得たい、または古道の歴史を味わいたい登山者に好まれています。

徳本峠までの道の大部分は沢に沿っています。苔むした岩や清流が趣を感じさせます。
ただし降雨による沢の増水や道の崩落のため、自治体により通行止めとなる場合があります。事前に最新情報を確認したうえで臨むことが大切です。

沢には桟道が設けられていたり、数多くの橋が架けられています。行き橋、戻り橋といった名のある橋も点在します。瀬戸沢が流れ込むあたりには瀬戸下橋と瀬戸上橋が、「岩魚留」と呼ばれるポイントには「岩魚留橋」と岩魚留小屋(※休業中)があります。

途中には炭焼き窯や石灰窯の跡もあり、かつての産業の名残りも見ることができます。

またこの峠道には、戦国時代の武将・三木秀綱(みきひでつな:生誕不明-1585年)の妻が村人に襲われ命を落としたと伝わります。
夫人を慰霊する石碑や、その非業の死を詠んだ折口信夫(おりくちしのぶ:1887-1953年)の歌碑がそれぞれ静かに佇んでいます。

徳本峠の手前ではちから水と呼ばれる湧き水を汲むことができます。
積雪時のバリエーションルートも人気

霞沢岳は、雪がある時期にも登山者がよく入山しています。ただし登山上級者向けで、ルートは一般登山道ではなく、西尾根や南尾根を辿るバリエーションルートです。

雪稜を歩く確かな技術が求められるのはもちろん、状況によってはロープを使って自己確保を行いながら進む場面や、懸垂下降が必要になることもあります。

稜線から望む冠雪した山々は、格別の美しさを誇ります。
| 登山口 |
上高地バスターミナル 島々宿登山口 |
|---|---|
| 周辺の山小屋 |
徳本峠小屋 岩魚留小屋 |
基本情報
| 標高 | 2646m |
|---|---|
| 場所 | 北緯36度13分16秒, 東経137度38分26秒 |
| 山頂 |
|---|
山の解説 - [出典:Wikipedia]
霞沢岳(かすみざわだけ)は、飛騨山脈(北アルプス)南部に位置する標高2,646 mの山。山体すべてが長野県松本市に属する。中部山岳国立公園内の常念山脈の最南端に位置する。アルピコ交通上高地線新島々駅の西北西16.7 kmに位置する。山頂部には三本槍と呼ばれる岩峰がある。北側の上高地には梓川が流れ、山の西から回り込み南側を流れる。その南側の梓川沿いには国道158号が通っている。山名は南東側の梓川の支流霞沢の源流の山であることに由来する。山頂の南5.7 kmには1928年に完成した東京電力の霞沢発電所があり、上流の梓川から霞沢岳の南西山腹を貫く水路のトンネルが造られ有効落差454 mでの発電を行っている。
上高地では、穂高連峰に対峙した背後の山であり、登山道は徳本峠(とくごうとうげ)からの道しかなく、縦走路から外れるため、訪れる人もあまり多くない。しかしながら、この山から見る穂高連峰や笠ヶ岳の展望は特筆に価し、ガイドブックや登山地図などでよく紹介される。日本画家の加藤美代三が霞沢岳の風景を描いている。
付近の山
この場所に関連する本
この場所を通る登山ルート
おすすめルート
-
☃ 雪山 1泊2日 槍・穂高・乗鞍



 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月冬期バリエーションルートの入門に最適な霞沢岳西尾根。 徳本峠からのアプローチは雪崩の危険性が高いので、冬期は西尾根または南尾根からの登山になります。
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月冬期バリエーションルートの入門に最適な霞沢岳西尾根。 徳本峠からのアプローチは雪崩の危険性が高いので、冬期は西尾根または南尾根からの登山になります。





 霞沢岳の山行記録へ
霞沢岳の山行記録へ

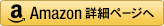










 Loading...
Loading...

