日本二百名山
新・花の百名山
日本百高山
信州百名山
富山の百山
甲信越百名山
日本の山岳標高1003山
長野県の山(分県登山ガイド)
日本2500m峰
信州ふるさと120山
日本の山1000
長野県の名峰百選
信州山歩き(中信・南信編)
信州山カード
山渓花の百名山地図帳
白籏史朗の百一名山
北陸新幹線百名山
西丸震哉日本百山
2000メートル以上の642山
北陸の百山
白馬・鹿島槍・五竜
針ノ木岳(はりのきだけ)
最終更新:ヤマレコ/YamaReco
大雪渓と古道の峠が楽しめる北アルプスの二百名山

針ノ木岳は、富山県と長野県にまたがる標高2821mの山です。

日本三大雪渓のひとつ針ノ木雪渓を抱き、夏でも雪上歩きができるところや、山頂から望む北アルプスの大パノラマが魅力です。
日本百名山の選考に惜しくも漏れたエピソードを持ちますが、日本二百名山および新・花の百名山に名を連ねています。

山頂部は山らしい端正な三角形をしており、立山連峰や黒部湖あたりからその特徴的な山容が良く見えます。
一方で麓からはあまり仰げず、長野県大町市から蓮華岳の背後にわずかに見える程度です。

山名の由来は諸説ありますが、そのひとつは山頂の東に位置する針ノ木峠にちなんでおり、大正時代から呼ばれるようになったそうです。
また「針ノ木」という名は、周辺に多く分布するミヤマハンノキの「ハンノキ」が転訛したと伝えられています。
日本三大雪渓「針ノ木雪渓」

針ノ木雪渓は針ノ木峠直下に広がる大雪渓で、白馬大雪渓、および剱沢雪渓と並び日本三大雪渓に数えられます。夏でも雪が残り、涼やかな空気を感じながら登ることができます。
一方で、雪の状況を見極めることが重要で、状況によってはアイゼンやピッケルを使用することもあります。また雪が少な過ぎる場合は踏み抜きなどの危険が高まります。雪解けの進み具合によっては、雪渓と並行する夏道を歩くことになります。

春はバックカントリースキーもよく行われています。
山頂からは北アルプスの大パノラマ

針ノ木岳の山頂は、北アルプスの雄峰を一望できる絶好の展望地です。
三等三角点が設置されており、点名の「野口」は麓の大町市の集落名にちなんでいます。

隣にそびえる蓮華岳をはじめ、爺ヶ岳や鹿島槍ヶ岳へと連なる後立山連峰の名峰群、さらに裏銀座縦走コースの山々が広がります。また黒部川を見下ろし、その向こうには立山や剱岳などの威容を拝むことができます。
越中と信濃を繋いだ針ノ木峠

針ノ木峠は針ノ木岳と、隣接する蓮華岳との鞍部に位置しています。
高所にありながら、古くは越中(富山県)と信濃(長野県)を結ぶ交通路の経由地でした。古道は「さらさら越え」とも呼ばれ、塩の道のひとつとして越中側からは塩や海産物が、信濃側からは米や味噌が運ばれていたようです。

豪雪地帯ゆえ冬のさらさら越えは極めて困難ですが、1584年に戦国武将・佐々成政(さっさ なりまさ:生年諸説あり-没1588年)が厳冬期に密かに北アルプスを横断した際、複数ある推定ルートの一つとされています。
また明治時代には牛馬が通れるほどの広さに整備され、1880年に立山新道(ほかに信越連帯新道など複数の呼称あり)として有料道路が開通しました。しかし、冬期の閉鎖期間が長く収益が上がらなかったため、わずか2年で営業を終えることとなりました。

現在の針ノ木峠には針ノ木小屋が建っており、往来するのは登山者のみです。
針ノ木小屋の創業者・百瀬慎太郎

針ノ木岳を語るうえで欠かせない人物が百瀬慎太郎(ももせしんたろう:1892-1949年)です。
彼は登山案内人として活躍し、大沢小屋や針ノ木小屋を開設して登山道の整備にも尽力しました。

その功績は北アルプス南部の近代登山の発展に大きく寄与したとされ、大沢小屋には彼のレリーフが設けられています。
また歌人としての一面もあり、レリーフに刻まれた「山を想えば人恋し、人を想えば山恋し」の詩は多くの登山愛好家に親しまれています。

さらに毎年6月は、開山祭として針ノ木岳慎太郎祭が行われています。
定番ルートは針ノ木岳と蓮華岳の2座登頂

針ノ木岳登山のメインルートは、山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」の出発点・扇沢からスタートします。

序盤は谷筋を巻くように登山道が続き、いくつか支沢を横切りながら高度を上げていきます。

大沢小屋を過ぎると道は谷底に入り、やがて針ノ木雪渓を迎えます。雪渓は場所によって急斜面となり、登り切るために体力が求められます。

雪渓を登り切ると針ノ木峠に到達します。
ここから山頂へは高山植物の咲き誇る稜線歩きとなります。

運が良ければライチョウに出会えることもあります。

多くの登山者は針ノ木小屋に宿泊し、翌日に隣の蓮華岳にも足を延ばして、2座を合わせて楽しみます。

蓮華岳へと続く稜線には、可憐なコマクサが群生するお花畑が広がっています。
人気の周回ルート「針ノ木サーキット」

登山上級者には「針ノ木サーキット」と呼ばれる周回ルートも好まれています。

扇沢を起点に針ノ木岳へ登り、その先はスバリ岳、赤沢岳、鳴沢岳、岩小屋沢岳といったピーク越える稜線歩きを満喫します。

下山は、種池山荘から柏原新道を通って扇沢へ戻ります。

宿泊地は、大沢小屋、針ノ木小屋、新越山荘、種池山荘があり、行動ペースに合わせて選ぶことができます。
針ノ木岳の難易度(信州 山のグレーディング)
88. 針ノ木岳(扇沢) 難易度B ★★☆☆☆(2)| 登山口 | 針ノ木登山口(扇沢) |
|---|---|
| 周辺の山小屋 |
針ノ木小屋 大沢小屋 新越山荘 種池山荘 |
基本情報
| 標高 | 2821m |
|---|---|
| 場所 | 北緯36度32分17秒, 東経137度41分03秒 |
| 山頂 | |
|---|---|
| 展望ポイント |
山の解説 - [出典:Wikipedia]
針ノ木岳(はりのきだけ)は、富山県中新川郡立山町と長野県大町市にまたがる標高2,821 mの山。中部山岳国立公園内にあり、後立山連峰に属する。大糸線信濃大町駅の西北西10.4 kmに位置し、針ノ木峠を挟んで蓮華岳と対峙している。大町側からは、大きな山容の蓮華岳が手前にあるため、針ノ木岳の方がやや標高が高いにもかかわらず、はっきりと見ることができない。ピラミッド型の端正な山容で、日本二百名山及び新・花の百名山に選定されている。東西の主稜線は同じような勾配であり、白馬岳のような後立山連峰の特長である非対称山稜は見られない。高瀬川の支流である篭川の上流部に日本三大雪渓の一つ、針ノ木大雪渓がある。針ノ木岳の源流部の厩窪(マヤクボ)沢にはカール地形がみられる。山体は濃飛流紋岩型の溶結凝灰岩からなる。
付近の山
この場所に関連する本
この場所を通る登山ルート
おすすめルート
-
上級 3泊4日 槍・穂高・乗鞍



 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月北アルプスの主稜線上でありながら訪れる人も少なく地味で不遇な山域ですが、ここの素晴らしさは言葉では言い表せません。筆者お奨めの好ルート!
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月北アルプスの主稜線上でありながら訪れる人も少なく地味で不遇な山域ですが、ここの素晴らしさは言葉では言い表せません。筆者お奨めの好ルート!
「針ノ木岳」 に関連する記録(最新10件)
白馬・鹿島槍・五竜
45 27 4
2025年10月23日(日帰り)



 針ノ木岳の山行記録へ
針ノ木岳の山行記録へ

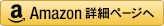












 Loading...
Loading...

