SFTS(重症熱性血小板減少症候群)感染者数は過去最高を更新し、感染地域も拡大中
マダニが媒介することで昨今話題のSFTS(重症熱性血小板減少症候群)の国内報告数は2024年までで1,071名で増加傾向にあります(死亡事例117件)。
2025年8月3日時点の累積患者数は124人、これは去年1年間の累計を上回っています。
2025年8月10日時点の累積患者数は135人、これは過去最多だった2023年の累計を上回っています(※1)。
2025年8月24日時点の累積患者数は142人、差分は西日本の既存地域の増加のみで、新たに発生した地域はありません。増加ペースもやや落ち着く傾向でしょうか。
2025年8月10日時点の累積患者数は135人、これは過去最多だった2023年の累計を上回っています(※1)。
2025年8月24日時点の累積患者数は142人、差分は西日本の既存地域の増加のみで、新たに発生した地域はありません。増加ペースもやや落ち着く傾向でしょうか。
感染症法では四類感染症に定められており、承認されたワクチンはありません。対症療法として抗ウイルス薬(ファビピラビル)の使用が承認されているとはいえ、致死率の高い深刻な感染症です。
これまでは西日本でしか確認されませんでしたが、自治体発表も含めると、今年になって北海道、秋田県、茨城県、栃木県、神奈川県、富山県、岐阜県での初めての感染事例が確認されるなど、感染地域が東日本にも拡大しつつあり、油断できなくなっています。
NHKニュースでも8月3日の集計結果に続いて、8月10日の集計結果に対しても注意喚起をしています(※2)。
これまでは西日本でしか確認されませんでしたが、自治体発表も含めると、今年になって北海道、秋田県、茨城県、栃木県、神奈川県、富山県、岐阜県での初めての感染事例が確認されるなど、感染地域が東日本にも拡大しつつあり、油断できなくなっています。
NHKニュースでも8月3日の集計結果に続いて、8月10日の集計結果に対しても注意喚起をしています(※2)。
SFTSに関する正確な最新情報を得たい場合、chatGPTなどのAIに訊ねるのではなく、厚生労働省や国立健康危機管理機構のWEBサイトを開き、そこから得るようにしてください。
【参考:AI利用に関する一般論】調査対象がぼんやりしている場合に、それを絞り込む目的でAIを補助的に参照するのは活用方法として良いと思いますが、「SFTS」や「マダニ」など、知りたい対象やキーワードが明確になっている場合は、AIを使わず、自分で情報源を確認しながら探した方が良質で正確な情報に辿り着ける可能性が高くなります。
【参考:AI利用に関する一般論】調査対象がぼんやりしている場合に、それを絞り込む目的でAIを補助的に参照するのは活用方法として良いと思いますが、「SFTS」や「マダニ」など、知りたい対象やキーワードが明確になっている場合は、AIを使わず、自分で情報源を確認しながら探した方が良質で正確な情報に辿り着ける可能性が高くなります。
マダニ
以下、国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト「マダニ対策、今できること」(※3)からの抜粋と要約です。
ひとくちに「マダニ」と言っても、日本ではマダニ科に5属48種以上が知られており、その中で少なくともフタトゲチマダニとキマチダニがSFTSを媒介することが知られています。
ひとくちに「マダニ」と言っても、日本ではマダニ科に5属48種以上が知られており、その中で少なくともフタトゲチマダニとキマチダニがSFTSを媒介することが知られています。
日本国内のマダニはほとんどが、卵→幼ダニ→若ダニ→成ダニ→産卵のサイクルをとり、各ステージで脱皮するごとに吸血する動物を替える「3宿主性」です。未吸血の状態で宿主に付着し、数日〜10数日かけて宿主から吸血を続けた後、自ら脱落して次のサイクルに進みます。
吸血中のマダニは血液を体内に取り込んで濃縮し、水分を唾液として宿主に吐き戻すところがマダニからヒトへのSFTSの感染経路となります。
幼ダニは非常に小さく見つけづらく、野ネズミや鳥を宿主とするため、若ダニや成ダニが宿主とするイノシシやシカなど大型哺乳類のいない市街地にも生息域を広げて、イヌやネコを宿主にすることができますので、これらのペットの飼い主は、住宅地の中であってもマダニの予防に留意する必要があります。
SFTSの潜伏期間は6日〜2週間で、4月〜8月に多く発症しています。
幼ダニは非常に小さく見つけづらく、野ネズミや鳥を宿主とするため、若ダニや成ダニが宿主とするイノシシやシカなど大型哺乳類のいない市街地にも生息域を広げて、イヌやネコを宿主にすることができますので、これらのペットの飼い主は、住宅地の中であってもマダニの予防に留意する必要があります。
SFTSの潜伏期間は6日〜2週間で、4月〜8月に多く発症しています。
マダニが皮膚に食いついているのを発見したら
吸血中のマダニを無理にむしり取ってしまうのは以下の問題があり危険です。
・マダニの口器が皮膚の中に残り化膿する場合がある
・SFTSウィルスを含んだ唾液を絞り出して人体内に注入する場合がある
このため皮膚科等の医療機関で、適切な処置(マダニの除去や消毒など)が推奨されています。
一方、自分で除去できる専用のツールも市販されています。ダニをクルクル回すことで、口器のトゲを無効化できるため安全に抜ける、という原理のようです(※4)
いずれにせよ、数週間程度は体調の変化に注意し、発熱等の症状が認められた場合は、SFTSの可能性を疑い、医療機関で診察を受けましょう。
【2025/9/18追記】吸血中のマダニが簡単に外れない理由として、「逆向きに生えた口器のトゲ」の他に、「マダニセメント」という物資による固着
https://www.aandt.co.jp/jpn/medical/tree/vol_17/
があり、状況がここまで進行すると上述のクルクル回すツールでは対応できず、医療機関での皮膚切開が必要になるかもしれません。以下の日記参照
https://www.yamareco.com/modules/diary/893747-detail-372229
・マダニの口器が皮膚の中に残り化膿する場合がある
・SFTSウィルスを含んだ唾液を絞り出して人体内に注入する場合がある
このため皮膚科等の医療機関で、適切な処置(マダニの除去や消毒など)が推奨されています。
一方、自分で除去できる専用のツールも市販されています。ダニをクルクル回すことで、口器のトゲを無効化できるため安全に抜ける、という原理のようです(※4)
いずれにせよ、数週間程度は体調の変化に注意し、発熱等の症状が認められた場合は、SFTSの可能性を疑い、医療機関で診察を受けましょう。
【2025/9/18追記】吸血中のマダニが簡単に外れない理由として、「逆向きに生えた口器のトゲ」の他に、「マダニセメント」という物資による固着
https://www.aandt.co.jp/jpn/medical/tree/vol_17/
があり、状況がここまで進行すると上述のクルクル回すツールでは対応できず、医療機関での皮膚切開が必要になるかもしれません。以下の日記参照
https://www.yamareco.com/modules/diary/893747-detail-372229
出典
※1
※2
※3
※4
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
Bright-Doorさんの記事一覧
-
 リスク増加中!マダニとSFTS(重症熱性血小板減少症候群)
27
更新日:2025年09月18日
リスク増加中!マダニとSFTS(重症熱性血小板減少症候群)
27
更新日:2025年09月18日
-
 大山北尾根〜札掛吊橋最短ルート(みんなの足跡反映のタイムラグ)
8
更新日:2024年12月25日
大山北尾根〜札掛吊橋最短ルート(みんなの足跡反映のタイムラグ)
8
更新日:2024年12月25日
-
 いまココの5分間隔ログをgpx変換してヤマレコで表示する
7
更新日:2024年12月04日
いまココの5分間隔ログをgpx変換してヤマレコで表示する
7
更新日:2024年12月04日
※この記事はヤマレコの「ヤマノート」機能を利用して作られています。
どなたでも、山に関する知識や技術などのノウハウを簡単に残して共有できます。
ぜひご協力ください!

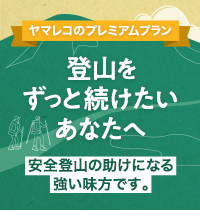











コメントを編集
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する