 二俣尾駅の約300m西側で青梅線のガードを潜り、集落を抜けて沢沿いの山道に入る。桟道が2ヶ所、沢を3ヶ所古い木の橋で渡る
二俣尾駅の約300m西側で青梅線のガードを潜り、集落を抜けて沢沿いの山道に入る。桟道が2ヶ所、沢を3ヶ所古い木の橋で渡る
 1
1
4/13 7:05
二俣尾駅の約300m西側で青梅線のガードを潜り、集落を抜けて沢沿いの山道に入る。桟道が2ヶ所、沢を3ヶ所古い木の橋で渡る
 小沢が二股に分かれ、右股に入った直後、小屋掛けの手前の木に道標が打付けられていた。写真の奥の尾根に取付く
小沢が二股に分かれ、右股に入った直後、小屋掛けの手前の木に道標が打付けられていた。写真の奥の尾根に取付く
 1
1
4/13 7:12
小沢が二股に分かれ、右股に入った直後、小屋掛けの手前の木に道標が打付けられていた。写真の奥の尾根に取付く
 雷電山南隣の450mコブから南西に伸びる支尾根を登る。取付きからしばらくは溝状に掘られた明瞭な道が続くが、急である
雷電山南隣の450mコブから南西に伸びる支尾根を登る。取付きからしばらくは溝状に掘られた明瞭な道が続くが、急である
 1
1
4/13 7:20
雷電山南隣の450mコブから南西に伸びる支尾根を登る。取付きからしばらくは溝状に掘られた明瞭な道が続くが、急である
 標高310mで一旦緩やかになるが、その上で再び急登となる。踏跡は一部不明瞭になるが、高みを目指せばよい
標高310mで一旦緩やかになるが、その上で再び急登となる。踏跡は一部不明瞭になるが、高みを目指せばよい
 1
1
4/13 7:32
標高310mで一旦緩やかになるが、その上で再び急登となる。踏跡は一部不明瞭になるが、高みを目指せばよい
 標高430mで縦走路と合流。縦走路はここで直角に折れ、道標が立っている。その道標の裏、写真の左奥から登って来たが、この方向への案内は何も無い
標高430mで縦走路と合流。縦走路はここで直角に折れ、道標が立っている。その道標の裏、写真の左奥から登って来たが、この方向への案内は何も無い
 1
1
4/13 7:49
標高430mで縦走路と合流。縦走路はここで直角に折れ、道標が立っている。その道標の裏、写真の左奥から登って来たが、この方向への案内は何も無い
 縦走路は幅広い立派な登山道。危険個所にはロープが張られ、急な上りには木の段が組まれて、過剰な程に管理されている
縦走路は幅広い立派な登山道。危険個所にはロープが張られ、急な上りには木の段が組まれて、過剰な程に管理されている
 1
1
4/13 8:10
縦走路は幅広い立派な登山道。危険個所にはロープが張られ、急な上りには木の段が組まれて、過剰な程に管理されている
 雷電山の頂上に着いた。2m程の大きな山名杭が立っていた
雷電山の頂上に着いた。2m程の大きな山名杭が立っていた
 1
1
4/13 8:40
雷電山の頂上に着いた。2m程の大きな山名杭が立っていた
 榎峠に向かって北西に降りる。急坂には延々と木の段が並べられ、膝に来る。最近交換したようで、古い部材がまだ脇に置かれていた
榎峠に向かって北西に降りる。急坂には延々と木の段が並べられ、膝に来る。最近交換したようで、古い部材がまだ脇に置かれていた
 1
1
4/13 8:42
榎峠に向かって北西に降りる。急坂には延々と木の段が並べられ、膝に来る。最近交換したようで、古い部材がまだ脇に置かれていた
 左下に都道193号線が見えてくると榎峠は近い。この峠越えの車道は奥武蔵や上州の山々に登る時、さらには渋滞する関越道の逃げ道として良く利用する
左下に都道193号線が見えてくると榎峠は近い。この峠越えの車道は奥武蔵や上州の山々に登る時、さらには渋滞する関越道の逃げ道として良く利用する
 0
0
4/13 9:07
左下に都道193号線が見えてくると榎峠は近い。この峠越えの車道は奥武蔵や上州の山々に登る時、さらには渋滞する関越道の逃げ道として良く利用する
 榎峠の車道を横切り、送電線鉄塔が建っている400m圏コブを目指す。民家を回り込みアンテナの裏から尾根に乗り、巡視路を辿る
榎峠の車道を横切り、送電線鉄塔が建っている400m圏コブを目指す。民家を回り込みアンテナの裏から尾根に乗り、巡視路を辿る
 0
0
4/13 9:25
榎峠の車道を横切り、送電線鉄塔が建っている400m圏コブを目指す。民家を回り込みアンテナの裏から尾根に乗り、巡視路を辿る
 超高圧送電線の新所沢線36号鉄塔が建つ400m圏コブに着いた。ここから西に進み、永栗ノ峰(633m峰)から南東に伸びる尾根上の500m圏コブに出る予定
超高圧送電線の新所沢線36号鉄塔が建つ400m圏コブに着いた。ここから西に進み、永栗ノ峰(633m峰)から南東に伸びる尾根上の500m圏コブに出る予定
 0
0
4/13 9:31
超高圧送電線の新所沢線36号鉄塔が建つ400m圏コブに着いた。ここから西に進み、永栗ノ峰(633m峰)から南東に伸びる尾根上の500m圏コブに出る予定
 しかし、このコブから西側鞍部まで道が無い。仕方ない、コブから北側に向かって写真の強烈な藪の中を強引に降りる
しかし、このコブから西側鞍部まで道が無い。仕方ない、コブから北側に向かって写真の強烈な藪の中を強引に降りる
 0
0
4/13 9:45
しかし、このコブから西側鞍部まで道が無い。仕方ない、コブから北側に向かって写真の強烈な藪の中を強引に降りる
 10m程降りたが期待した踏跡は無いので西にトラバース。藪は無くなったが足場が悪い急な灌木帯を斜めに下る
10m程降りたが期待した踏跡は無いので西にトラバース。藪は無くなったが足場が悪い急な灌木帯を斜めに下る
 0
0
4/13 9:47
10m程降りたが期待した踏跡は無いので西にトラバース。藪は無くなったが足場が悪い急な灌木帯を斜めに下る
 鞍部に着くと、南側から幅広い立派な道が上がって来るではないか。何てことだ!榎峠から沢沿いに上がって来る道らしい
鞍部に着くと、南側から幅広い立派な道が上がって来るではないか。何てことだ!榎峠から沢沿いに上がって来る道らしい
 0
0
4/13 9:49
鞍部に着くと、南側から幅広い立派な道が上がって来るではないか。何てことだ!榎峠から沢沿いに上がって来る道らしい
 この鞍部には、高水山を指す道標とトレイルランの案内が立っていた。この先はルートが保証されたようなもので、気が抜けてしまった
この鞍部には、高水山を指す道標とトレイルランの案内が立っていた。この先はルートが保証されたようなもので、気が抜けてしまった
 1
1
4/13 9:52
この鞍部には、高水山を指す道標とトレイルランの案内が立っていた。この先はルートが保証されたようなもので、気が抜けてしまった
 案の定、登山道並みの立派な道が続く。急な上りには木の段が組まれ、ロープまで張られている
案の定、登山道並みの立派な道が続く。急な上りには木の段が組まれ、ロープまで張られている
 0
0
4/13 10:06
案の定、登山道並みの立派な道が続く。急な上りには木の段が組まれ、ロープまで張られている
 永栗ノ峰南東尾根の500m圏コブに着いた。青梅高水山トレイルランのコース指示が木に括りつけられていた
永栗ノ峰南東尾根の500m圏コブに着いた。青梅高水山トレイルランのコース指示が木に括りつけられていた
 1
1
4/13 10:16
永栗ノ峰南東尾根の500m圏コブに着いた。青梅高水山トレイルランのコース指示が木に括りつけられていた
 ここから永栗ノ峰に向かって比較的緩やかな尾根を登る。少し急な上りには、木より手間が掛かる石の段が組まれている。昔からの登山道かしら
ここから永栗ノ峰に向かって比較的緩やかな尾根を登る。少し急な上りには、木より手間が掛かる石の段が組まれている。昔からの登山道かしら
 1
1
4/13 10:49
ここから永栗ノ峰に向かって比較的緩やかな尾根を登る。少し急な上りには、木より手間が掛かる石の段が組まれている。昔からの登山道かしら
 標高570m辺りに青梅市の基準点が埋められていた
標高570m辺りに青梅市の基準点が埋められていた
 1
1
4/13 10:56
標高570m辺りに青梅市の基準点が埋められていた
 永栗ノ峰(633m峰)の手前で林道に出た。北麓の成木集落から常福院まで続いている林道で、ここを車で上がって来れば簡単に高水山に立てる
永栗ノ峰(633m峰)の手前で林道に出た。北麓の成木集落から常福院まで続いている林道で、ここを車で上がって来れば簡単に高水山に立てる
 0
0
4/13 11:08
永栗ノ峰(633m峰)の手前で林道に出た。北麓の成木集落から常福院まで続いている林道で、ここを車で上がって来れば簡単に高水山に立てる
 林道を10分程歩いてから再び山道に入る。良く踏まれた歩き易い登山道を進む
林道を10分程歩いてから再び山道に入る。良く踏まれた歩き易い登山道を進む
 0
0
4/13 11:26
林道を10分程歩いてから再び山道に入る。良く踏まれた歩き易い登山道を進む
 軍畑駅から平溝林道経由で上がって来る道と合流した。登山地図に赤線で描かれている一般登山道で、惣岳山までこの道を辿るので、この先は気楽だ
軍畑駅から平溝林道経由で上がって来る道と合流した。登山地図に赤線で描かれている一般登山道で、惣岳山までこの道を辿るので、この先は気楽だ
 1
1
4/13 11:29
軍畑駅から平溝林道経由で上がって来る道と合流した。登山地図に赤線で描かれている一般登山道で、惣岳山までこの道を辿るので、この先は気楽だ
 常福院に寄り道する。長い石段を登り切った山門には、高水山の額が掲げられていた。山頂もこの寺の境内なのかしら
常福院に寄り道する。長い石段を登り切った山門には、高水山の額が掲げられていた。山頂もこの寺の境内なのかしら
 0
0
4/13 11:37
常福院に寄り道する。長い石段を登り切った山門には、高水山の額が掲げられていた。山頂もこの寺の境内なのかしら
 常福院の本堂。山の上のお寺としては立派な佇まいだ。左の高水山不動尊の碑の側面には、皇太子殿下と妃殿下が御来山と刻んであった
常福院の本堂。山の上のお寺としては立派な佇まいだ。左の高水山不動尊の碑の側面には、皇太子殿下と妃殿下が御来山と刻んであった
 2
2
4/13 11:39
常福院の本堂。山の上のお寺としては立派な佇まいだ。左の高水山不動尊の碑の側面には、皇太子殿下と妃殿下が御来山と刻んであった
 常福院から5分も登れば高水山の頂上。道標を兼ねた山名板とベンチが置かれている。眺望は木の間越しなので写真の対象にならない
常福院から5分も登れば高水山の頂上。道標を兼ねた山名板とベンチが置かれている。眺望は木の間越しなので写真の対象にならない
 1
1
4/13 12:30
常福院から5分も登れば高水山の頂上。道標を兼ねた山名板とベンチが置かれている。眺望は木の間越しなので写真の対象にならない
 山頂の山桜は満開を過ぎて花吹雪。淹れたてのコーヒーに花びらが飛び込む。それにしても携帯電話のアンテナが無粋だ
山頂の山桜は満開を過ぎて花吹雪。淹れたてのコーヒーに花びらが飛び込む。それにしても携帯電話のアンテナが無粋だ
 1
1
4/13 12:29
山頂の山桜は満開を過ぎて花吹雪。淹れたてのコーヒーに花びらが飛び込む。それにしても携帯電話のアンテナが無粋だ
 ここから岩茸石山を経由して惣岳山まで三山を縦走する。高水山の下り始めは岩が多いので慎重に
ここから岩茸石山を経由して惣岳山まで三山を縦走する。高水山の下り始めは岩が多いので慎重に
 1
1
4/13 12:35
ここから岩茸石山を経由して惣岳山まで三山を縦走する。高水山の下り始めは岩が多いので慎重に
 三山の標高はいずれも700m台で、アップダウンも少なくて気楽。なだらかな道を、新緑を愛でながらルンルン気分で歩む
三山の標高はいずれも700m台で、アップダウンも少なくて気楽。なだらかな道を、新緑を愛でながらルンルン気分で歩む
 2
2
4/13 12:45
三山の標高はいずれも700m台で、アップダウンも少なくて気楽。なだらかな道を、新緑を愛でながらルンルン気分で歩む
 白い山桜は珍しい。青空に溶け込むように咲き誇っている
白い山桜は珍しい。青空に溶け込むように咲き誇っている
 1
1
4/13 12:53
白い山桜は珍しい。青空に溶け込むように咲き誇っている
 岩茸石山の頂上手前は岩が多いが、ルートは明瞭
岩茸石山の頂上手前は岩が多いが、ルートは明瞭
 1
1
4/13 12:56
岩茸石山の頂上手前は岩が多いが、ルートは明瞭
 岩茸石山の頂上に立つ山名杭。三山の中で最も高く793.0m。唯一、三角点が埋まっている
岩茸石山の頂上に立つ山名杭。三山の中で最も高く793.0m。唯一、三角点が埋まっている
 1
1
4/13 13:05
岩茸石山の頂上に立つ山名杭。三山の中で最も高く793.0m。唯一、三角点が埋まっている
 ここから西北西方向に、中央:川苔山、左:本仁田山、右奥:蕎麦粒山が望める
ここから西北西方向に、中央:川苔山、左:本仁田山、右奥:蕎麦粒山が望める
 0
0
4/13 13:06
ここから西北西方向に、中央:川苔山、左:本仁田山、右奥:蕎麦粒山が望める
 同じく北北西には棒ノ折山。手前は黒山
同じく北北西には棒ノ折山。手前は黒山
 0
0
4/13 13:14
同じく北北西には棒ノ折山。手前は黒山
 東には先ほど登った高水山と、辿って来た尾根が見える。この頂には北東の風が吹き荒れて寒いのに、奥の青梅市街地は春霞でぼんやり
東には先ほど登った高水山と、辿って来た尾根が見える。この頂には北東の風が吹き荒れて寒いのに、奥の青梅市街地は春霞でぼんやり
 0
0
4/13 13:08
東には先ほど登った高水山と、辿って来た尾根が見える。この頂には北東の風が吹き荒れて寒いのに、奥の青梅市街地は春霞でぼんやり
 岩茸石山から惣岳山に向かって南下する。頂上からの下りで一部は岩場になっている
岩茸石山から惣岳山に向かって南下する。頂上からの下りで一部は岩場になっている
 1
1
4/13 13:17
岩茸石山から惣岳山に向かって南下する。頂上からの下りで一部は岩場になっている
 鞍部まで降りれば、後はなだらかな道が檜林の中に続き、のんびりした気分に浸れる
鞍部まで降りれば、後はなだらかな道が檜林の中に続き、のんびりした気分に浸れる
 0
0
4/13 13:42
鞍部まで降りれば、後はなだらかな道が檜林の中に続き、のんびりした気分に浸れる
 惣岳山の頂上手前で、左に巻道を分けると岩場になる。三山共に頂上直下に岩が多いが、この山が最も岩場っぽい
惣岳山の頂上手前で、左に巻道を分けると岩場になる。三山共に頂上直下に岩が多いが、この山が最も岩場っぽい
 1
1
4/13 13:50
惣岳山の頂上手前で、左に巻道を分けると岩場になる。三山共に頂上直下に岩が多いが、この山が最も岩場っぽい
 惣岳山の頂上は小広場となっていて青渭神社が建っている
惣岳山の頂上は小広場となっていて青渭神社が建っている
 1
1
4/13 13:57
惣岳山の頂上は小広場となっていて青渭神社が建っている
 ここからは軍畑駅まで伸びている長い長い平溝尾根を下る。惣岳山頂上から東方向に降りるが、踏跡は明瞭で赤テープも豊富だ
ここからは軍畑駅まで伸びている長い長い平溝尾根を下る。惣岳山頂上から東方向に降りるが、踏跡は明瞭で赤テープも豊富だ
 1
1
4/13 14:29
ここからは軍畑駅まで伸びている長い長い平溝尾根を下る。惣岳山頂上から東方向に降りるが、踏跡は明瞭で赤テープも豊富だ
 頂上を迂回した巻道を横切ると、北側が伐採されて展望が開ける。歩いて来た高水山から岩茸石山へ続く尾根が手に取るように見える
頂上を迂回した巻道を横切ると、北側が伐採されて展望が開ける。歩いて来た高水山から岩茸石山へ続く尾根が手に取るように見える
 1
1
4/13 14:33
頂上を迂回した巻道を横切ると、北側が伐採されて展望が開ける。歩いて来た高水山から岩茸石山へ続く尾根が手に取るように見える
 そのまま尾根筋を進むと沢井尾根に引き込まれる。平溝尾根を降りるには標高700m圏で北斜面に入る。多くのテープが注意を喚起している
そのまま尾根筋を進むと沢井尾根に引き込まれる。平溝尾根を降りるには標高700m圏で北斜面に入る。多くのテープが注意を喚起している
 0
0
4/13 14:38
そのまま尾根筋を進むと沢井尾根に引き込まれる。平溝尾根を降りるには標高700m圏で北斜面に入る。多くのテープが注意を喚起している
 標高610m圏で再び伐採地の上に出る。北側が谷底まで皆伐されて寒々しい。写真の奥の尾根が登って来た永栗ノ峰南東尾根
標高610m圏で再び伐採地の上に出る。北側が谷底まで皆伐されて寒々しい。写真の奥の尾根が登って来た永栗ノ峰南東尾根
 0
0
4/13 14:56
標高610m圏で再び伐採地の上に出る。北側が谷底まで皆伐されて寒々しい。写真の奥の尾根が登って来た永栗ノ峰南東尾根
 振り返ると、岩茸石山(右)から惣岳山(写真の左外)へ続く尾根が望める。左の峰は途中の723m峰で、縦走路はこれを巻いている
振り返ると、岩茸石山(右)から惣岳山(写真の左外)へ続く尾根が望める。左の峰は途中の723m峰で、縦走路はこれを巻いている
 0
0
4/13 15:03
振り返ると、岩茸石山(右)から惣岳山(写真の左外)へ続く尾根が望める。左の峰は途中の723m峰で、縦走路はこれを巻いている
 しばらくの間ほとんど平らな尾根道を進む。特徴が無く、高低差も無く、方向も変わらないので、現在地の確認が難しい
しばらくの間ほとんど平らな尾根道を進む。特徴が無く、高低差も無く、方向も変わらないので、現在地の確認が難しい
 0
0
4/13 15:05
しばらくの間ほとんど平らな尾根道を進む。特徴が無く、高低差も無く、方向も変わらないので、現在地の確認が難しい
 標高505m圏で、尾根上に踏跡は続いているのに、道の上に小枝が束ねて置かれ、直進を阻んでいる、何なの?
標高505m圏で、尾根上に踏跡は続いているのに、道の上に小枝が束ねて置かれ、直進を阻んでいる、何なの?
 0
0
4/13 15:38
標高505m圏で、尾根上に踏跡は続いているのに、道の上に小枝が束ねて置かれ、直進を阻んでいる、何なの?
 左を見ると木にテープが三重に巻かれ、その脇から東側山腹に踏跡が降りている。直進せずにここで左折すべし。要注意地点だ
左を見ると木にテープが三重に巻かれ、その脇から東側山腹に踏跡が降りている。直進せずにここで左折すべし。要注意地点だ
 0
0
4/13 15:38
左を見ると木にテープが三重に巻かれ、その脇から東側山腹に踏跡が降りている。直進せずにここで左折すべし。要注意地点だ
 最初の480m圏コブに上ると、直進方向の南南東尾根に明瞭な踏跡が続き、赤テープも点在。しかし、ここで写真左の藪の隙間に入り、東に続く踏跡を辿るべし。第3の注意個所
最初の480m圏コブに上ると、直進方向の南南東尾根に明瞭な踏跡が続き、赤テープも点在。しかし、ここで写真左の藪の隙間に入り、東に続く踏跡を辿るべし。第3の注意個所
 0
0
4/13 16:06
最初の480m圏コブに上ると、直進方向の南南東尾根に明瞭な踏跡が続き、赤テープも点在。しかし、ここで写真左の藪の隙間に入り、東に続く踏跡を辿るべし。第3の注意個所
 直ぐ東に同じ高さの第2の480m圏コブがある。この写真の頂で、地形図の破線通りに直角に右折して南東に急降下する
直ぐ東に同じ高さの第2の480m圏コブがある。この写真の頂で、地形図の破線通りに直角に右折して南東に急降下する
 0
0
4/13 16:19
直ぐ東に同じ高さの第2の480m圏コブがある。この写真の頂で、地形図の破線通りに直角に右折して南東に急降下する
 450m圏まで降りると平坦地となる。ここで南に向きを変えると、400m圏で再びなだらかとなり、写真の幅広い道が続く
450m圏まで降りると平坦地となる。ここで南に向きを変えると、400m圏で再びなだらかとなり、写真の幅広い道が続く
 0
0
4/13 16:38
450m圏まで降りると平坦地となる。ここで南に向きを変えると、400m圏で再びなだらかとなり、写真の幅広い道が続く
 緩やかに下って行くと、東西に走る送電線JR古里線の25号鉄塔の脇を通る
緩やかに下って行くと、東西に走る送電線JR古里線の25号鉄塔の脇を通る
 0
0
4/13 16:45
緩やかに下って行くと、東西に走る送電線JR古里線の25号鉄塔の脇を通る
 榎峠を通る送電線の新所沢線が南北に走っていて、先ほどのJR古里線とこの先で交差する。これらの鉄塔の巡視路を辿って進む
榎峠を通る送電線の新所沢線が南北に走っていて、先ほどのJR古里線とこの先で交差する。これらの鉄塔の巡視路を辿って進む
 0
0
4/13 16:53
榎峠を通る送電線の新所沢線が南北に走っていて、先ほどのJR古里線とこの先で交差する。これらの鉄塔の巡視路を辿って進む
 超高圧送電線の新所沢線31号鉄塔を真下から仰ぐ。この系統の36号鉄塔が、朝方苦労した榎峠北の400m圏コブに立っていた
超高圧送電線の新所沢線31号鉄塔を真下から仰ぐ。この系統の36号鉄塔が、朝方苦労した榎峠北の400m圏コブに立っていた
 0
0
4/13 16:58
超高圧送電線の新所沢線31号鉄塔を真下から仰ぐ。この系統の36号鉄塔が、朝方苦労した榎峠北の400m圏コブに立っていた
 緩やかな尾根道を下って行くと社に出た。この辺りの沢井集落の守り神かしら
緩やかな尾根道を下って行くと社に出た。この辺りの沢井集落の守り神かしら
 1
1
4/13 17:07
緩やかな尾根道を下って行くと社に出た。この辺りの沢井集落の守り神かしら
 社の急な階段を降り、墓地を抜けると東光寺の境内、石燈籠の脇に降り立った
社の急な階段を降り、墓地を抜けると東光寺の境内、石燈籠の脇に降り立った
 1
1
4/13 17:13
社の急な階段を降り、墓地を抜けると東光寺の境内、石燈籠の脇に降り立った
 集落の中の道を適当に下って行くと、軍畑駅の直ぐ西にある踏切に出た。丁度上り電車が通って軍畑駅に停まった。ここから10分も歩けばゴール
集落の中の道を適当に下って行くと、軍畑駅の直ぐ西にある踏切に出た。丁度上り電車が通って軍畑駅に停まった。ここから10分も歩けばゴール
 2
2
4/13 17:17
集落の中の道を適当に下って行くと、軍畑駅の直ぐ西にある踏切に出た。丁度上り電車が通って軍畑駅に停まった。ここから10分も歩けばゴール


 gakukyourou
gakukyourou

 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大 拍手
拍手







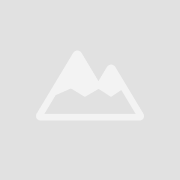









いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する