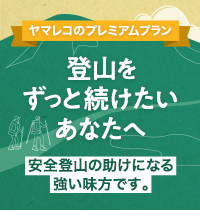懸垂下降(けんすいかこう) / ラペル(ラペリング、ラッペル)
最終更新:2015-06-02 21:46 - kamog
基本情報
ロープを支点に架け、下降器を使って降りる技術。
使われる支点には、クライミングエリアにおいてはラッペルステーションのラッペルリング等であったり、残置カラビナであったり、荷重に充分耐えうる木などナチュラルプロテクションであったりする。
下降器(ディッセンダー)には以前はエイト環が主流であったが、現在はビレイデバイス(確保器)を兼用することが多くなった。
慣れてくると容易に考えがちだが、ヒューマンエラーによる事故が多発している。
注意点として、
・支点が荷重に耐えられるものかどうか要チェック(下降時の荷重は自重の数倍かかる)
・セルフビレイ(自己確保)を行うこと。
・ロープの両末端は必ずエイトノットですっぽ抜け防止を施す。
・ロープの中間点がちょうど支点の折り返し点になっていること。
・2本のロープを結束する場合は、現在は一般的にオーバーハンドノットを使う。
2本の場合は、回収時にどちらのロープを引き抜けば結び目が引っ掛からないか、パーティ内に周知徹底しておくこと。
・ロープダウンの際は、下のパーティが確認できるように大声で知らせること。
(状況によりロープダウンせず、少しずつロープを繰り出しながら下りることもある)
・ロープダウンして両末端がきれいに下りたいポイントまで届いているのが視認できればよいが、果たして届いているか不明な場合や、途中の木や岩角、テラスなど障害物に引っ掛かっている場合、ロープが途中で絡まっている場合、下降一番手の者は、両手を使えるよう、フリクションヒッチ(主にマッシャー)でバックアップを取ること。
ロープが届いていない場合は登り返さなければならないこと(セルフライズアップ)もあるので、その技術もマスターしておく必要がある。
・先に下りた者は次の下降者に対するバックアップとして、2本のロープを軽く緩めて持ってあげること。
・地形等の状況により先に下りた者はロープを引いてみて回収が可能か確認すること。
・ロープ両末端が充分下まで届いていれば、両末端に施したすっぽ抜け防止のエイトノットは解除しておくこと。(ギリギリの場合は解除せずに残しておく)
・特に最終下降者はロープを回収する際に落ち口のクラックや木の根に引っ掛からないよう注意しながら下りること。
・継続して懸垂下降を行う場合、狭いテラスやバンドなどではロープ回収時にロープが重かったり、引っ掛かりの影響で身体がリバウンドすることもあるので、セルフビレイを取ってから回収作業した方がよい。
・ロープが引き抜かれる際は周囲に「ロープダウン!」と大声で周知すること。
・引き抜いた際、場所により落石が起こることがあるので、ロープが落ちてきてから数秒は上を見ておく。
etc
使われる支点には、クライミングエリアにおいてはラッペルステーションのラッペルリング等であったり、残置カラビナであったり、荷重に充分耐えうる木などナチュラルプロテクションであったりする。
下降器(ディッセンダー)には以前はエイト環が主流であったが、現在はビレイデバイス(確保器)を兼用することが多くなった。
慣れてくると容易に考えがちだが、ヒューマンエラーによる事故が多発している。
注意点として、
・支点が荷重に耐えられるものかどうか要チェック(下降時の荷重は自重の数倍かかる)
・セルフビレイ(自己確保)を行うこと。
・ロープの両末端は必ずエイトノットですっぽ抜け防止を施す。
・ロープの中間点がちょうど支点の折り返し点になっていること。
・2本のロープを結束する場合は、現在は一般的にオーバーハンドノットを使う。
2本の場合は、回収時にどちらのロープを引き抜けば結び目が引っ掛からないか、パーティ内に周知徹底しておくこと。
・ロープダウンの際は、下のパーティが確認できるように大声で知らせること。
(状況によりロープダウンせず、少しずつロープを繰り出しながら下りることもある)
・ロープダウンして両末端がきれいに下りたいポイントまで届いているのが視認できればよいが、果たして届いているか不明な場合や、途中の木や岩角、テラスなど障害物に引っ掛かっている場合、ロープが途中で絡まっている場合、下降一番手の者は、両手を使えるよう、フリクションヒッチ(主にマッシャー)でバックアップを取ること。
ロープが届いていない場合は登り返さなければならないこと(セルフライズアップ)もあるので、その技術もマスターしておく必要がある。
・先に下りた者は次の下降者に対するバックアップとして、2本のロープを軽く緩めて持ってあげること。
・地形等の状況により先に下りた者はロープを引いてみて回収が可能か確認すること。
・ロープ両末端が充分下まで届いていれば、両末端に施したすっぽ抜け防止のエイトノットは解除しておくこと。(ギリギリの場合は解除せずに残しておく)
・特に最終下降者はロープを回収する際に落ち口のクラックや木の根に引っ掛からないよう注意しながら下りること。
・継続して懸垂下降を行う場合、狭いテラスやバンドなどではロープ回収時にロープが重かったり、引っ掛かりの影響で身体がリバウンドすることもあるので、セルフビレイを取ってから回収作業した方がよい。
・ロープが引き抜かれる際は周囲に「ロープダウン!」と大声で周知すること。
・引き抜いた際、場所により落石が起こることがあるので、ロープが落ちてきてから数秒は上を見ておく。
etc
山の解説 - [出典:Wikipedia]
懸垂下降(けんすいかこう)は、ロープ(ザイル)を使って高所から下降する方法のことである。登山では、主に急峻な斜面や岩壁、軍事活動のヘリボーンや救助においては、ヘリコプターが着陸できない状況下にてホバリング中のヘリコプターなどから降りる際、またはCQBにおいて、建物屋上から内部に進入する際にも用いられる。ドイツ語からアプザイレン(Abseilen )、フランス語由来のアメリカ英語からラッペリング(rappelling )もしくはリ(ラ)ペリング、ラッペルとも言う。イギリス英語ではドイツ語由来のabseilenが多用される。クライミングロープにセットされた下降器を用い、ロープと懸垂下降器の摩擦を緩めながら後ろ歩きの要領で下降する。オーバーハングのある岩壁や、ヘリコプターからの降下などではロープを一気に滑り降りる場合もあるが、訓練を積んでいない者が行うのは極めて危険である。
「オーストラリアン・ラペル」と俗称される方法では、前向き(下向き)の姿勢で下降が行われる。