(はじめに)
この5−2章では、「ヴァリス山群」注1)の主な山々の地質について説明しています。
「ヴァリス山群」は説明したい山々の数が多いのと、一つ一つの山の地質構造が複雑で、説明内容が長くなるため、複数回に分けて投稿しています。
前の回(その1)では、「ヴァリス山群の概要」、および「マッターホルンの地質」について説明しました。
この回(その2)では、ツェルマットの南側、イタリアとの国境稜線にそびえる、「モンテローザ」、「ブライトホルン」などの4000m級の山々の地質、およびツェルマットのすぐ脇にある「ゴルナーグラート台地」(仮称)付近の地質について説明します。
※ 注;なお、当初の投稿 「5−2章(その1)」初稿では、読み返してみると、内容が長すぎて読みづらいため、初稿を2つに分割することとしました。
具体的には初稿のうち、第1節「ヴァリス山群の概要」、第2節「マッターホルン」までの部分を(その1)(改)とし、第3節「モンテローザ」〜第5節「ゴルナーグラートとその周辺」を、この(その2(新))へと、2分割しました。
この回の投稿は、その2分割したうちの後半部です。説明の内容は、初稿とほぼ同じです。
悪しからずご了承ください。
「ヴァリス山群」は説明したい山々の数が多いのと、一つ一つの山の地質構造が複雑で、説明内容が長くなるため、複数回に分けて投稿しています。
前の回(その1)では、「ヴァリス山群の概要」、および「マッターホルンの地質」について説明しました。
この回(その2)では、ツェルマットの南側、イタリアとの国境稜線にそびえる、「モンテローザ」、「ブライトホルン」などの4000m級の山々の地質、およびツェルマットのすぐ脇にある「ゴルナーグラート台地」(仮称)付近の地質について説明します。
※ 注;なお、当初の投稿 「5−2章(その1)」初稿では、読み返してみると、内容が長すぎて読みづらいため、初稿を2つに分割することとしました。
具体的には初稿のうち、第1節「ヴァリス山群の概要」、第2節「マッターホルン」までの部分を(その1)(改)とし、第3節「モンテローザ」〜第5節「ゴルナーグラートとその周辺」を、この(その2(新))へと、2分割しました。
この回の投稿は、その2分割したうちの後半部です。説明の内容は、初稿とほぼ同じです。
悪しからずご了承ください。
5−2章―第(3)節 「モンテローザ」の地質
「モンテローザ」(Monte Rosa;4634m)注2)は、ヨーロッパアルプスの中では、「モンブラン」(Mont Blanc;4810m)に次ぐ標高を誇り、また、主稜線部だけで約10kmの長さをもつその巨大な山体は、いくつものピークを擁し、一つの山というよりは、巨大な山塊という感じの山です。
「モンテローザ」の最高峰は、「デフィールシュピッシェ」(Dufour spitze;4634m)というピークですが、それ以外にも、「ノルトエント」(Nortend;4609m)、ジグナールクッペ(Signalkuppe;4556m)など、4000mを越えるピークが、約10個もあります。
この山は、頂上稜線やスイス側山腹に山小屋があり、「マッターホルン」を凌ぐ高峰ながら、スイス側、イタリア側いずれからも登攀ルートがある山です(文献10)、(文献11)、(文献12)。
「ツェルマット」付近の展望台、「ゴルナーグラート」(Gorner-grat)からは、その北側を覆う氷河を含めた全容が望めますが、孤高の尖峰である「マッターホルン」とは対照的で、大横綱のような堂々とした風格があります。(写真1)
余談ですが、「モンテローザ」(“Monte Rosa”)という名前のうち(“rosa“)は、現代イタリア語の「ばら色」や「ピンク色」を意味する言葉(フランス語の”rose”に対応)からきていると思われがちですが、(文献11)、(文献12)によると、古い北イタリア方言で「氷」や「氷河」を意味する(”roesa”)、あるいは(”rouese”)からきているそうです。
従って日本語に直訳すると「氷河の山」、「氷の山」という意味となります。広く氷河に覆われたこの山にふさわしい名前といえましょう。
さて「モンテローザ」の地質ですが、その主稜線は、スイス/イタリアの国境稜線ともなっているため、イタリア側の地質は、スイスのオンライン地質図のうち、(文献2A)では描かれていません((文献2B)では多少描かれている)。また山体の広い範囲が氷河で覆われていることもあり、この山の地質は、氷河の間から断片的に露出している岩場の地質が頼りです。
以下、地質図(文献2A)、(文献3)や、(文献4)、(文献5)などをもとに、「モンテローザ」の地質を説明します。
なお、同じスイスのオンライン地質図であっても、(文献2A)と(文献2B)では地質説明が少し違っています。以下では説明が詳しい(文献2A)を元に主に説明します。(文献2B)は補足程度で多少触れます。
具体的な地質の説明の前に、まず「モンテローザ」とその周辺のテクトニックな位置づけについてですが、(文献3)、(文献4)、(文献5)、(文献12)などによると、この一帯は、「モンテローザ・ナップ」(Monte Rosa nappe(英)/ Monte Rosa Decke(独))と呼ばれる古い(大陸性の)「地塊」からなります。テクトニックマップ(図3)もご参照ください。
なお「モンテローザ・ナップ」に関する詳細は、「補足説明1」の項で説明します。ご興味のある方は、ご覧ください。
さて、「モンテローザ」山頂部付近の地質を、地質図(文献2A)で見てみると、以外と構成は単純で、2種類の地質体が分布しているだけです。添付の図6もご参照ください。
具体的には、以下の2種類です。
(a);「古い変成岩類」
(b);「花崗岩類由来の変成岩類」
まず、(a);「古い変成岩類」ですが、山腹も含めた山体のあちこちに分布しています(図6でのベージュ色部分)。
地質図(文献2A)によると、岩石の種類(岩相)(lithology)としては「片麻岩」類(Gneis (独))です。(原岩が形成された)時代(chrono)の項は、原生代〜古生代、と書かれており、起源の古い大陸性の基盤岩体です。
この「地塊」は、複数回の変成作用を受けて、現在の「片麻岩」類になっていると推定されています。「アルプス造山運動」においても変成作用を受けています。
次に(b);「花崗岩類由来の変成岩類」ですが、これも山体のあちこちに分布しています(図6でのピンク色部分)。
地質図(文献2A)によると、岩相としては、「マグマ的片麻岩」(Gneis;magmatisch(独))と書かれており、「マグマ―>深成岩(花崗岩類)―>変成岩」、という経歴を意味していると思われます。
また(文献5)では、270〜330Ma(「石炭紀」〜「ペルム紀」)に貫入した「花崗岩類」、と説明されています。また(文献2A)でも「石炭紀」(Karbon(独))と書かれています。これはおそらく、深成岩体として形成された時代を意味していると思われます。
この連載の2−2章で説明しましたが、古生代後半期に生じた「ヴァリスカン造山運動」の少し後の「石炭紀」〜「ペルム紀」にかけての時代は、「ポスト・ヴァリスカン期」(post-Variscan)と呼ばれ、「アルプス地域」(the Alpine Domain)で広範囲に火成活動が活発化した時代です。
(文献5)の説明も踏まえると、この「モンテローザ・ナップ」における、変成した花崗岩類も、年代的には、この「ポスト・ヴァリスカン期」の火成活動に関連したものではないか、と思われます。
補足として、地質図(文献2B)に基づいての説明をします。(文献2B)でも、
(a)’ ;「アルプス造山運動」以前の基盤岩(pre-Alpine basements)としての変成岩類、
(b)’;古生代の「ヴァリスカン造山運動」に関連した「変成花崗岩」類(meta-granitoids)
の2種類の岩石が分布している、という点では、(文献2A)とほぼ同じです。
違うのは岩相(lithology)の項で、(a)‘ も、(b)’ も、「雲母片岩」(mica-shists)とされています。
「モンテローザ」の最高峰は、「デフィールシュピッシェ」(Dufour spitze;4634m)というピークですが、それ以外にも、「ノルトエント」(Nortend;4609m)、ジグナールクッペ(Signalkuppe;4556m)など、4000mを越えるピークが、約10個もあります。
この山は、頂上稜線やスイス側山腹に山小屋があり、「マッターホルン」を凌ぐ高峰ながら、スイス側、イタリア側いずれからも登攀ルートがある山です(文献10)、(文献11)、(文献12)。
「ツェルマット」付近の展望台、「ゴルナーグラート」(Gorner-grat)からは、その北側を覆う氷河を含めた全容が望めますが、孤高の尖峰である「マッターホルン」とは対照的で、大横綱のような堂々とした風格があります。(写真1)
余談ですが、「モンテローザ」(“Monte Rosa”)という名前のうち(“rosa“)は、現代イタリア語の「ばら色」や「ピンク色」を意味する言葉(フランス語の”rose”に対応)からきていると思われがちですが、(文献11)、(文献12)によると、古い北イタリア方言で「氷」や「氷河」を意味する(”roesa”)、あるいは(”rouese”)からきているそうです。
従って日本語に直訳すると「氷河の山」、「氷の山」という意味となります。広く氷河に覆われたこの山にふさわしい名前といえましょう。
さて「モンテローザ」の地質ですが、その主稜線は、スイス/イタリアの国境稜線ともなっているため、イタリア側の地質は、スイスのオンライン地質図のうち、(文献2A)では描かれていません((文献2B)では多少描かれている)。また山体の広い範囲が氷河で覆われていることもあり、この山の地質は、氷河の間から断片的に露出している岩場の地質が頼りです。
以下、地質図(文献2A)、(文献3)や、(文献4)、(文献5)などをもとに、「モンテローザ」の地質を説明します。
なお、同じスイスのオンライン地質図であっても、(文献2A)と(文献2B)では地質説明が少し違っています。以下では説明が詳しい(文献2A)を元に主に説明します。(文献2B)は補足程度で多少触れます。
具体的な地質の説明の前に、まず「モンテローザ」とその周辺のテクトニックな位置づけについてですが、(文献3)、(文献4)、(文献5)、(文献12)などによると、この一帯は、「モンテローザ・ナップ」(Monte Rosa nappe(英)/ Monte Rosa Decke(独))と呼ばれる古い(大陸性の)「地塊」からなります。テクトニックマップ(図3)もご参照ください。
なお「モンテローザ・ナップ」に関する詳細は、「補足説明1」の項で説明します。ご興味のある方は、ご覧ください。
さて、「モンテローザ」山頂部付近の地質を、地質図(文献2A)で見てみると、以外と構成は単純で、2種類の地質体が分布しているだけです。添付の図6もご参照ください。
具体的には、以下の2種類です。
(a);「古い変成岩類」
(b);「花崗岩類由来の変成岩類」
まず、(a);「古い変成岩類」ですが、山腹も含めた山体のあちこちに分布しています(図6でのベージュ色部分)。
地質図(文献2A)によると、岩石の種類(岩相)(lithology)としては「片麻岩」類(Gneis (独))です。(原岩が形成された)時代(chrono)の項は、原生代〜古生代、と書かれており、起源の古い大陸性の基盤岩体です。
この「地塊」は、複数回の変成作用を受けて、現在の「片麻岩」類になっていると推定されています。「アルプス造山運動」においても変成作用を受けています。
次に(b);「花崗岩類由来の変成岩類」ですが、これも山体のあちこちに分布しています(図6でのピンク色部分)。
地質図(文献2A)によると、岩相としては、「マグマ的片麻岩」(Gneis;magmatisch(独))と書かれており、「マグマ―>深成岩(花崗岩類)―>変成岩」、という経歴を意味していると思われます。
また(文献5)では、270〜330Ma(「石炭紀」〜「ペルム紀」)に貫入した「花崗岩類」、と説明されています。また(文献2A)でも「石炭紀」(Karbon(独))と書かれています。これはおそらく、深成岩体として形成された時代を意味していると思われます。
この連載の2−2章で説明しましたが、古生代後半期に生じた「ヴァリスカン造山運動」の少し後の「石炭紀」〜「ペルム紀」にかけての時代は、「ポスト・ヴァリスカン期」(post-Variscan)と呼ばれ、「アルプス地域」(the Alpine Domain)で広範囲に火成活動が活発化した時代です。
(文献5)の説明も踏まえると、この「モンテローザ・ナップ」における、変成した花崗岩類も、年代的には、この「ポスト・ヴァリスカン期」の火成活動に関連したものではないか、と思われます。
補足として、地質図(文献2B)に基づいての説明をします。(文献2B)でも、
(a)’ ;「アルプス造山運動」以前の基盤岩(pre-Alpine basements)としての変成岩類、
(b)’;古生代の「ヴァリスカン造山運動」に関連した「変成花崗岩」類(meta-granitoids)
の2種類の岩石が分布している、という点では、(文献2A)とほぼ同じです。
違うのは岩相(lithology)の項で、(a)‘ も、(b)’ も、「雲母片岩」(mica-shists)とされています。
5−2章―第(4)節 「ブライトホルン」とその周辺の地質
この第(4)節では、スイス/イタリアの国境稜線をなし、「マッターホルン」(Matterhorn)と「モンテローザ」(Monte Rosa)という両巨頭の間にある、4000m級の山々の地質について説明します。
具体的には、西側から順に、「クラインマッターホルン」(Kline Matterhorn)、「ブライトホルン」(Breithorn)、「ポリュックス」(Pollux)、「カストール」(Castor)、「リスカム」(Liskamm)の各山々です。
以下、それらの山々を、3つの項に分けて、その地質を説明します。
具体的には、西側から順に、「クラインマッターホルン」(Kline Matterhorn)、「ブライトホルン」(Breithorn)、「ポリュックス」(Pollux)、「カストール」(Castor)、「リスカム」(Liskamm)の各山々です。
以下、それらの山々を、3つの項に分けて、その地質を説明します。
4−A項) 「ブライトホルン」と「クラインマッターホルン」
「ブライトホルン」(Breithorn)という名の山は、「ヨーロッパアルプス」にいくつかありますが、ここでは「ヴァリス山群」の「ブライトホルン」(Breithorn; 4160m)(文献13)について説明します。
この山は、山頂の西側にある「クラインマッターホルン」(Kline Matterhorn;3883m)注4)という小さな岩峰まで、麓のツェルマットからロープウエイが伸びており、そこを起点とすると、雪原歩きで、4時間程度で登頂、往復ができる、お手軽な4000m峰として知られています(筆者も登りました)。
この山は、西側から見ると丸っこい雪山の姿ですが、その北壁は迫力ある険しい絶壁となっています(文献10)、(文献11)、(文献13)、(写真2)。
地質図(文献2A)を見ると、「ブライトホルン」の山頂部や険しい北壁、及び「クラインマッターホルン」付近は、広範囲に「蛇紋岩」(serpentinite(英))が分布しています。
なお(文献2B)や(文献7)によると、山稜の南側(イタリア側)にも、この蛇紋岩分布域が広がっています。図8の地質図、および(写真2)、(写真3)、(写真4)、(写真5)もご参照ください。
このほか、北側山腹の一部には、堆積物由来の変成岩である「石灰質雲母片岩」(kalkig glimmer-Schiefer(独))などが小規模に分布しています。この岩体は、(上部ペニン系)とは書かれていますが、蛇紋岩体との関係は良く解りません。(文献5)の説明からみると「ピエモンテ海」の海底に堆積した堆積物が、その起源のようです。
テクトニクス的には、この蛇紋岩分布域は、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」(Zermatt Saas-Fee zone)と呼ばれる「地塊」(地帯)の一部とされています(文献4)、(文献21)。添付の図3(テクトニックマップ)もご参照ください。
この「地塊」(地帯)は、中生代に存在した「ピエモンテ海」(the Piemont Ocean /the Piemonte-Liguria Ocean)という海洋域を形成していた「海洋性プレート」の断片と推定されています。
「海洋性プレート」のうち最下層である「リソスフェアマントル」を構成している岩体は「カンラン岩」と呼ばれる岩石ですが、それが水(H2O)と反応して変成したものが「蛇紋岩」です。
従って、「ブライトホルン」、「クラインマッターホルン」を構成している「蛇紋岩」は、元々は「ピエモンテ海」のプレート下部を構成していた岩体が、地表に現れていることを示しています。
「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」という「地塊」(地帯)に関しては、「補足説明2」の項でやや詳しく説明しました。ご興味のある方は、そちらもご覧ください。
この山は、山頂の西側にある「クラインマッターホルン」(Kline Matterhorn;3883m)注4)という小さな岩峰まで、麓のツェルマットからロープウエイが伸びており、そこを起点とすると、雪原歩きで、4時間程度で登頂、往復ができる、お手軽な4000m峰として知られています(筆者も登りました)。
この山は、西側から見ると丸っこい雪山の姿ですが、その北壁は迫力ある険しい絶壁となっています(文献10)、(文献11)、(文献13)、(写真2)。
地質図(文献2A)を見ると、「ブライトホルン」の山頂部や険しい北壁、及び「クラインマッターホルン」付近は、広範囲に「蛇紋岩」(serpentinite(英))が分布しています。
なお(文献2B)や(文献7)によると、山稜の南側(イタリア側)にも、この蛇紋岩分布域が広がっています。図8の地質図、および(写真2)、(写真3)、(写真4)、(写真5)もご参照ください。
このほか、北側山腹の一部には、堆積物由来の変成岩である「石灰質雲母片岩」(kalkig glimmer-Schiefer(独))などが小規模に分布しています。この岩体は、(上部ペニン系)とは書かれていますが、蛇紋岩体との関係は良く解りません。(文献5)の説明からみると「ピエモンテ海」の海底に堆積した堆積物が、その起源のようです。
テクトニクス的には、この蛇紋岩分布域は、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」(Zermatt Saas-Fee zone)と呼ばれる「地塊」(地帯)の一部とされています(文献4)、(文献21)。添付の図3(テクトニックマップ)もご参照ください。
この「地塊」(地帯)は、中生代に存在した「ピエモンテ海」(the Piemont Ocean /the Piemonte-Liguria Ocean)という海洋域を形成していた「海洋性プレート」の断片と推定されています。
「海洋性プレート」のうち最下層である「リソスフェアマントル」を構成している岩体は「カンラン岩」と呼ばれる岩石ですが、それが水(H2O)と反応して変成したものが「蛇紋岩」です。
従って、「ブライトホルン」、「クラインマッターホルン」を構成している「蛇紋岩」は、元々は「ピエモンテ海」のプレート下部を構成していた岩体が、地表に現れていることを示しています。
「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」という「地塊」(地帯)に関しては、「補足説明2」の項でやや詳しく説明しました。ご興味のある方は、そちらもご覧ください。
4−B項) 「ポリュックス」と「カストール」
「ブライトホルン」の東隣りには、「ポリュックス」(Pollux; 4089m)と「カストール」(Castor;4223m)いう双耳峰があり、2つ合わせて、「双子(峰)」を意味する、(Zwillinge(独)/「ツヴィリング」)とも呼ばれています(文献14)、(文献15)。(写真6)。
ところで、冬から春の夜空に浮かぶ星座である「双子座」の、α星、β星の名前も「ポリュックス」と「カストール」ですが、この双子峰の名前も、双子座の星の名前も、ギリシャ神話が由来だそうです。(文献16)
(文献10)によると、この2つのピークは「ブライトホルン」と同様、「クラインマッターホルン」のロープウエイを使って、比較的容易に登れる4000m峰として知られています。
まず「ポリュックス」の地質ですが、地質図(文献2A)によると、「ポリュックス」の山頂部や「ブライトホルン」から続く北壁には、「蛇紋岩」に加え、(変成)玄武岩(basalt(英))(「角閃岩」(Amphibolite(独))とも)、(変成)「ハンレイ岩」(gabllo(英))や、変成岩の一種「プラシナイト」(prasinit(独))が分布しています。
(なお、地質図(文献2B)では、まとめて「変成玄武岩類」(meta-basaltic rocks(英))としている)
(文献1―1)や(文献2A)によると、「ブライトホルン」から続く「蛇紋岩」や、「変成玄武岩」、「変成ハンレイ岩」類はまとめて、海洋プレート断片を意味する「オフィオライト(岩体)」(ophiolite)(文献22)と呼ばれるものです。
この「オフィオライト(岩体)」は、まとめて「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」(Zermatt-Saas-Fee zone(英))、(文献21) という「地塊」に属しています。添付の図3,図4(テクトニックマップ)もご参照ください。
なお「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」及び「オフィオライト(岩体)」については、「補足説明2」に少し詳しく解説しましたので、ご興味のある方はご覧ください。
次に「カストール」ですが、「ポリュックス」と近接した山頂で、2つ合わせて双耳峰をなしています。が、この2つのピークの間に、明瞭な地質境界があります。従って、地質的にも、テクトニックユニットとしても、全く異なります。つまりこの2つの峰は、地質学的には双子とはいえず、せいぜいが、遠縁の親戚程度の関係です。
「地塊」への帰属という観点からいうと、「カストール」は「モンテローザ・ナップ」に属しているので「モンテローザ」や「リスカム」に近く、「ポリュックス」は「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」に属しているので「ブライトホルン」に近い、という感じです。
地質図(文献2A)によると、「カストール」の地質は、「モンテローザ山塊」から続く、「モンテローザ・ナップ」(Monte rosa Decke(独))という「地塊」に属する、「古い片麻岩」類(gneiss(独))からなっています。(なお、地質図(文献2B)では、岩相としては「雲母片岩」(mica-schist)としている)。
ところで、冬から春の夜空に浮かぶ星座である「双子座」の、α星、β星の名前も「ポリュックス」と「カストール」ですが、この双子峰の名前も、双子座の星の名前も、ギリシャ神話が由来だそうです。(文献16)
(文献10)によると、この2つのピークは「ブライトホルン」と同様、「クラインマッターホルン」のロープウエイを使って、比較的容易に登れる4000m峰として知られています。
まず「ポリュックス」の地質ですが、地質図(文献2A)によると、「ポリュックス」の山頂部や「ブライトホルン」から続く北壁には、「蛇紋岩」に加え、(変成)玄武岩(basalt(英))(「角閃岩」(Amphibolite(独))とも)、(変成)「ハンレイ岩」(gabllo(英))や、変成岩の一種「プラシナイト」(prasinit(独))が分布しています。
(なお、地質図(文献2B)では、まとめて「変成玄武岩類」(meta-basaltic rocks(英))としている)
(文献1―1)や(文献2A)によると、「ブライトホルン」から続く「蛇紋岩」や、「変成玄武岩」、「変成ハンレイ岩」類はまとめて、海洋プレート断片を意味する「オフィオライト(岩体)」(ophiolite)(文献22)と呼ばれるものです。
この「オフィオライト(岩体)」は、まとめて「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」(Zermatt-Saas-Fee zone(英))、(文献21) という「地塊」に属しています。添付の図3,図4(テクトニックマップ)もご参照ください。
なお「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」及び「オフィオライト(岩体)」については、「補足説明2」に少し詳しく解説しましたので、ご興味のある方はご覧ください。
次に「カストール」ですが、「ポリュックス」と近接した山頂で、2つ合わせて双耳峰をなしています。が、この2つのピークの間に、明瞭な地質境界があります。従って、地質的にも、テクトニックユニットとしても、全く異なります。つまりこの2つの峰は、地質学的には双子とはいえず、せいぜいが、遠縁の親戚程度の関係です。
「地塊」への帰属という観点からいうと、「カストール」は「モンテローザ・ナップ」に属しているので「モンテローザ」や「リスカム」に近く、「ポリュックス」は「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」に属しているので「ブライトホルン」に近い、という感じです。
地質図(文献2A)によると、「カストール」の地質は、「モンテローザ山塊」から続く、「モンテローザ・ナップ」(Monte rosa Decke(独))という「地塊」に属する、「古い片麻岩」類(gneiss(独))からなっています。(なお、地質図(文献2B)では、岩相としては「雲母片岩」(mica-schist)としている)。
4−C項) 「リスカム」
「リスカム」(Liskamm;4532m)は、前記の「カストール」の東側、「モンテローザ」からみると、その西側に位置し、約5kmもの長い頂上稜線を持つ高峰です。(文献17)、(写真1)。
(文献10)によると、細い主稜線の南側(イタリア側)は険しい岩壁で、北側(スイス側)も岩と氷の絶壁です。また稜線部には雪庇ができやすく、難易度の高い山、とのことです。
さて「リスカム」の地質ですが、地質図(文献2A、2B)によると、前述の「カストール」や、その東にある「モンテローザ」と地質的にはほぼ同じで、テクトニックユニットとしては、前述の「モンテローザ・ナップ」という「地塊」に属します。
具体的には、地質図(文献2A)によると、原生代から古生代に起源を持つ、「古い片麻岩」類(gneiss(独))から成ります。(なお、地質図(文献2B)では、岩相としては「雲母片岩」(mica-schist)としている)。
(文献10)によると、細い主稜線の南側(イタリア側)は険しい岩壁で、北側(スイス側)も岩と氷の絶壁です。また稜線部には雪庇ができやすく、難易度の高い山、とのことです。
さて「リスカム」の地質ですが、地質図(文献2A、2B)によると、前述の「カストール」や、その東にある「モンテローザ」と地質的にはほぼ同じで、テクトニックユニットとしては、前述の「モンテローザ・ナップ」という「地塊」に属します。
具体的には、地質図(文献2A)によると、原生代から古生代に起源を持つ、「古い片麻岩」類(gneiss(独))から成ります。(なお、地質図(文献2B)では、岩相としては「雲母片岩」(mica-schist)としている)。
5−2章―第(5)節 「ゴルナーグラート」とその周辺の地質
「ゴルナーグラート」(Gorner- grat)とは、山の名前ではなく、「ツェルマット」東側の、台地状の地域にある観光拠点です(文献18)。
(※ ”grat” は、ドイツ語で「岩稜」の意味で、この一帯の地形図を見ると、「ゴルナーグラート駅」がある辺りの東西に伸びる岩稜に(”Gorner-grat”)という名前が付いている)。
「ツェルマット」からの登山鉄道の終着駅が、標高 約3100mの「ゴルナーグラート駅」で、そこは、「マッターホルン」や「モンテローザ」など、「ツェルマット」周辺の4000m級の山々を望む人気の展望台となっています。
またその周辺の、2500〜3000mの標高を持つ、台地状の部分(※ 以下、説明のため「ゴルナーグラート台地」と仮称します)は、夏にはお花畑となり、小さな氷河湖もある上、周辺の4000m級の山々の展望も楽しめるので、多くのハイキングコースがあります(文献8)、(文献9)。
この第(5)節では、観光客、ハイカーが多く訪れる、「ゴルナーグラート」とその周辺の地質について、スイスのオンライン地質図(文献2A)などを元に説明します((文献2B)は参考程度にします)。添付の地質図、図9や、写真7,写真8も、ご参照ください。
「ゴルナーグラート台地」付近の地質を、地質図(文献2A)で詳しく見ると、地形的には、氷河性堆積物(モレーン;moraine)が広範囲に広がる穏やかな高原ですが、見た目の穏やかさとは違い、地質的には、かなり複雑な地質構造になっています。
まず「ゴルナーグラート」駅付近や、そこから西へ続く岩稜(grat)、及びその岩稜の一角である「リッフェルホルン」(Riffelhorn;2930m)辺りの地質を、地質図(文献2A)で見ると、第(3)節の「ブライトホルン」の項で説明したのと同じく、「蛇紋岩」(serpentinit(独))から成っています。
この蛇紋岩体は「ゴルナー氷河」(the Gorner glacier)を間に挟んでいますが、「ブライトホルン」と「ゴルナーグラート」との中間部分にも点々と分布しており、氷河で覆われている部分も含め、かなり広い範囲に分布しているようです。
第(3)節でも説明したとおり、この蛇紋岩体は、海洋プレートの最下部を形成していた「カンラン岩」が変成作用を受けてできたもので、「ピエモンテ海」由来(=上部ペニン系)のものです。
「ゴルナーグラート台地」(仮称)は、広い範囲で氷河性堆積物(moraine)の岩屑に覆われていますが、それ以外の部分の地質は、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」(Zermatt-Saas Fee zone)(文献21)に属する「オフィオライト(岩体)」(ophiolite(英))(文献22)が分布しています。おそらく、氷河性堆積物の下にも同じように広がっているのでしょう。
さて、「ゴルナーグラート」の東側には、南側の「ゴルナー氷河」に沿うように岩稜が続き、「ストックホルン」(Stock horn;3532m)(文献19)、(写真9)という山に続いています。
この辺りの岩稜の地質は、地質図(文献2A)で見ると、「雲母片岩」(glimmer-schiefer(独))や「花崗岩質の結晶片岩」(granit-schiefer(独))が分布しており、前述の「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」とは岩石の種類が異なっています。(なお(文献2B)では主に「雲母片岩」(mica-schist)と書かれている)。
地質図(文献2A)のうちのテクトニックマップや、(文献4)、(文献5)によると、このゾーンは「ストックホルン・ナップ」(Stock horn nappe(英)/Stock horn Decke(独))と呼ばれる、東西 約6km、南北で最大3kmサイズの、独立した小さな「地塊」です。
(文献4)、(文献5)によると、この「地塊」は、「ブリアンソン・ライズ系」(=中部ペニン系)に属する、とされており、「ピエモンテ海系(=上部ペニン系)である「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」とは別ものです。むしろ「モンテローザ・ナップ」(=中部ペニン系)に近いといえます。
次に「ゴルナーグラート台地」」の北東側には、「ウンターロートホルン」(Unterrothorn;3103m)と、「オーバーロートホルン」(Oberrothorn;3414m)という2つの山があります(文献20)、(写真10)。
なお前者は山頂までロープウエイが通じており、後者も登山道があり、標高は3000mを越えていますが、ハイキング対象の山となっています(文献8)、(文献9)。
この2つの山の辺りの地質を、地質図(文献2A)で見ると、堆積岩由来の変成岩類が多く、具体的には、「石灰質の結晶片岩」(Kalgig-schefer(独))などが分布しています。
地質図(文献2A)によるとこれらは、「上部ペニン系」に属している中生代の堆積物由来の変成岩類です。
また、地質図(文献2A)のテクトニクスマップや、地質図(文献3)を見ると、この一帯は、5−2章―(2)節;「マッターホルン」の項でも出てきた、「ツァテ・ナップ」(Tsaté nappe)(文献4)に属しています。周辺の「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」とも、前述の「ストックホルン・ナップ」とも、所属が異なります。
なお、地質図(文献2A)をよく見ると、「オーバーロートホルン」の東面、南面には、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」に属する「オフィオライト」岩体(「蛇紋岩」、「変成ハンレイ岩」、「変成玄武岩」)が分布しているとともに、「オーバーロートホルン」のすぐ東どなりの「フルーホルン」(Fluehorn;3315m)という山には、高度変成岩である「エクロジャイト」(Eklogit(独))そのものが、わずかながら分布しています。
地質図(文献2A)を細かく見ると、その他に、「ゴルナーグラート・ナップ」(Gornergrat Decke(独))(文献4)、(文献5)という、紐のように幅が狭く、正体がはっきりしない「地塊」に属するとされる、「クオーツァイト」(quarzit(独))という石英質堆積物由来の変成岩や、(rauhwacke(独))という、「トリアス紀」の石灰岩質堆積岩も点在しており、なんとも複雑な地質構造となっています。
まとめると、「ゴルナーグラート台地」(仮称)と、その周辺の3000〜3500m程度の山々は、地形的にはハイキングに最適な高原状の穏やかな場所で、氷河性堆積物(モレーン)の岩屑に覆われていて険しい岩壁も少ないのですが、地質学的には、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」、「ツァテ・ナップ」「ストックホルン・ナップ」、「ゴルナーグラート・ナップ」といった、複数の「地塊」が入り混じっており、具体的な地質構成も含め、非常に複雑な地質分布となっています。
(※ ”grat” は、ドイツ語で「岩稜」の意味で、この一帯の地形図を見ると、「ゴルナーグラート駅」がある辺りの東西に伸びる岩稜に(”Gorner-grat”)という名前が付いている)。
「ツェルマット」からの登山鉄道の終着駅が、標高 約3100mの「ゴルナーグラート駅」で、そこは、「マッターホルン」や「モンテローザ」など、「ツェルマット」周辺の4000m級の山々を望む人気の展望台となっています。
またその周辺の、2500〜3000mの標高を持つ、台地状の部分(※ 以下、説明のため「ゴルナーグラート台地」と仮称します)は、夏にはお花畑となり、小さな氷河湖もある上、周辺の4000m級の山々の展望も楽しめるので、多くのハイキングコースがあります(文献8)、(文献9)。
この第(5)節では、観光客、ハイカーが多く訪れる、「ゴルナーグラート」とその周辺の地質について、スイスのオンライン地質図(文献2A)などを元に説明します((文献2B)は参考程度にします)。添付の地質図、図9や、写真7,写真8も、ご参照ください。
「ゴルナーグラート台地」付近の地質を、地質図(文献2A)で詳しく見ると、地形的には、氷河性堆積物(モレーン;moraine)が広範囲に広がる穏やかな高原ですが、見た目の穏やかさとは違い、地質的には、かなり複雑な地質構造になっています。
まず「ゴルナーグラート」駅付近や、そこから西へ続く岩稜(grat)、及びその岩稜の一角である「リッフェルホルン」(Riffelhorn;2930m)辺りの地質を、地質図(文献2A)で見ると、第(3)節の「ブライトホルン」の項で説明したのと同じく、「蛇紋岩」(serpentinit(独))から成っています。
この蛇紋岩体は「ゴルナー氷河」(the Gorner glacier)を間に挟んでいますが、「ブライトホルン」と「ゴルナーグラート」との中間部分にも点々と分布しており、氷河で覆われている部分も含め、かなり広い範囲に分布しているようです。
第(3)節でも説明したとおり、この蛇紋岩体は、海洋プレートの最下部を形成していた「カンラン岩」が変成作用を受けてできたもので、「ピエモンテ海」由来(=上部ペニン系)のものです。
「ゴルナーグラート台地」(仮称)は、広い範囲で氷河性堆積物(moraine)の岩屑に覆われていますが、それ以外の部分の地質は、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」(Zermatt-Saas Fee zone)(文献21)に属する「オフィオライト(岩体)」(ophiolite(英))(文献22)が分布しています。おそらく、氷河性堆積物の下にも同じように広がっているのでしょう。
さて、「ゴルナーグラート」の東側には、南側の「ゴルナー氷河」に沿うように岩稜が続き、「ストックホルン」(Stock horn;3532m)(文献19)、(写真9)という山に続いています。
この辺りの岩稜の地質は、地質図(文献2A)で見ると、「雲母片岩」(glimmer-schiefer(独))や「花崗岩質の結晶片岩」(granit-schiefer(独))が分布しており、前述の「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」とは岩石の種類が異なっています。(なお(文献2B)では主に「雲母片岩」(mica-schist)と書かれている)。
地質図(文献2A)のうちのテクトニックマップや、(文献4)、(文献5)によると、このゾーンは「ストックホルン・ナップ」(Stock horn nappe(英)/Stock horn Decke(独))と呼ばれる、東西 約6km、南北で最大3kmサイズの、独立した小さな「地塊」です。
(文献4)、(文献5)によると、この「地塊」は、「ブリアンソン・ライズ系」(=中部ペニン系)に属する、とされており、「ピエモンテ海系(=上部ペニン系)である「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」とは別ものです。むしろ「モンテローザ・ナップ」(=中部ペニン系)に近いといえます。
次に「ゴルナーグラート台地」」の北東側には、「ウンターロートホルン」(Unterrothorn;3103m)と、「オーバーロートホルン」(Oberrothorn;3414m)という2つの山があります(文献20)、(写真10)。
なお前者は山頂までロープウエイが通じており、後者も登山道があり、標高は3000mを越えていますが、ハイキング対象の山となっています(文献8)、(文献9)。
この2つの山の辺りの地質を、地質図(文献2A)で見ると、堆積岩由来の変成岩類が多く、具体的には、「石灰質の結晶片岩」(Kalgig-schefer(独))などが分布しています。
地質図(文献2A)によるとこれらは、「上部ペニン系」に属している中生代の堆積物由来の変成岩類です。
また、地質図(文献2A)のテクトニクスマップや、地質図(文献3)を見ると、この一帯は、5−2章―(2)節;「マッターホルン」の項でも出てきた、「ツァテ・ナップ」(Tsaté nappe)(文献4)に属しています。周辺の「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」とも、前述の「ストックホルン・ナップ」とも、所属が異なります。
なお、地質図(文献2A)をよく見ると、「オーバーロートホルン」の東面、南面には、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」に属する「オフィオライト」岩体(「蛇紋岩」、「変成ハンレイ岩」、「変成玄武岩」)が分布しているとともに、「オーバーロートホルン」のすぐ東どなりの「フルーホルン」(Fluehorn;3315m)という山には、高度変成岩である「エクロジャイト」(Eklogit(独))そのものが、わずかながら分布しています。
地質図(文献2A)を細かく見ると、その他に、「ゴルナーグラート・ナップ」(Gornergrat Decke(独))(文献4)、(文献5)という、紐のように幅が狭く、正体がはっきりしない「地塊」に属するとされる、「クオーツァイト」(quarzit(独))という石英質堆積物由来の変成岩や、(rauhwacke(独))という、「トリアス紀」の石灰岩質堆積岩も点在しており、なんとも複雑な地質構造となっています。
まとめると、「ゴルナーグラート台地」(仮称)と、その周辺の3000〜3500m程度の山々は、地形的にはハイキングに最適な高原状の穏やかな場所で、氷河性堆積物(モレーン)の岩屑に覆われていて険しい岩壁も少ないのですが、地質学的には、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」、「ツァテ・ナップ」「ストックホルン・ナップ」、「ゴルナーグラート・ナップ」といった、複数の「地塊」が入り混じっており、具体的な地質構成も含め、非常に複雑な地質分布となっています。
この連載の各項目へのリンクがあります
一つ前の連載へのリンクです
次の連載へのリンクです
【補足説明】の項
[補足説明1];「モンテローザ・ナップ」(地塊)について
この回ででてくる山のうち、「モンテローザ」、「リスカム」、「ポリュックス」といった山々は、「モンテローザ・ナップ」と呼ばれる「地塊」に属しています。
ここでは、その「モンテローザ・ナップ」について、補足説明します。
「モンテローザ・ナップ」(Monte Rosa nappe(英)/ Monte Rosa Decke(独))と呼ばれる「地塊」は、「ヴァリス山群」の中核部に広い面積を有する、大陸性の「地塊」です。(文献1−2)、(文献3)、(文献4)、(文献5)、(文献12)
この「地塊」の平面的な分布域は、テクトニックマップ(図3)もご参照ください。
また。推定地質断面図としては、添付の図7もご参照ください。この図は、(文献5)のFig.4から引用しました。
「モンテローザ・ナップ」のテクトニクス的な位置付けは、(文献4)、(文献5)、(文献12)や、(文献1−2)の古地理図によると、「ペニン系」地質グループのうち、「ブリアンソン・ライズ系」(Briançon rise)(=中部ペニン系)に属している大陸性の「地塊」です。
「モンテローザ・ナップ」を構成する具体的な地質としては、地質図(文献2A)を広域的に見てみると、大部分が古い起源を持ち、複数回の変成作用を受けた「片麻岩」類(gneisses)からなります。
具体的には、堆積岩起源の「パラ・片麻岩」(para genis(独))や、古生代の火成岩起源の片麻岩類からなります。
他には「雲母片岩」(glimmer-scheifer(独))も分布しています。また(文献5)の説明では、「片麻岩」類(gneisses)、「結晶片岩類」(schists)、及び部分的には「角閃岩」(amphibolite)や花崗岩類(granites)も分布している、とされています。
このうち深成岩体(大部分は後に「片麻岩」となっている)の形成時代は、(文献5)によると、約270〜330Maと測定されており、時代的には「石炭紀」〜「ペルム紀」に相当します。
ところで「モンテローザ・ナップ」と類似した「ブリアンソン・ライズ系」(=中部ペニン系)とされる大陸性の「地塊」としては、この「地塊」の北側にある「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」(Sivies Michabel nappe/Sivies Michabel Decke(独))という「地塊」があります。
また5−2章―(5)節に出てくる「ストックホルン・ナップ」(Stokhorn nappe(英)/Stockhorn Decke(独))という小型の「地塊」も、同じく「ブリアンソン・ライズ系」の「地塊」とされています。(文献4)、地質図(文献2A)、地質図(文献3)など。
なお、この「モンテローザ・ナップ」の位置付けとして、「ブリアンソン・ライズ系」ではなく、「ヨーロッパ大陸ブロック」の一部が分離したもの、という異説もあります。(文献6)
さて「ブリアンソン・ライズ」と呼ばれる、中生代の「ペニン系地質区」(Penninic realm)に存在した、この海台状の地域の形成メカニズムやその帰属には諸説ありますが、中生代のうち「ジュラ紀」から「白亜紀」前期には、海没して浅海域堆積物が形成されたり、隆起して陸化し、浸食を受けたりしていたと推定されています。
この連載の2−4章(「ジュラ紀」の「アルプス地域」)、2−5章(「白亜紀」の「アルプス地域」)も、ご参照ください。
その後、「モンテローザ・ナップ」(地塊)を含めた「ブリアンソン・ライズ系」の地質体は、「アルプス造山運動」の際には、「白亜紀」後期から「古第三紀」初頭に形成されていた沈み込み帯から地下深部に沈み込み、高圧型の変成作用を受けたのち、再び地表へと上がって来たものと考えられています(文献1−1)、(文献5)。
「モンテローザ・ナップ」については、地下深部に沈み込んだ際に受けた変成作用の度合いを示す「変成相」でいうと、(文献4)、(文献12)では、「エクロジャイト相」(eclogite facies)相当の変成作用を受けたとされています。(文献5)では「変成相」について明記されていませんが、変成作用のピークは、古第三紀「始新世」と推定しています。
ここでは、その「モンテローザ・ナップ」について、補足説明します。
「モンテローザ・ナップ」(Monte Rosa nappe(英)/ Monte Rosa Decke(独))と呼ばれる「地塊」は、「ヴァリス山群」の中核部に広い面積を有する、大陸性の「地塊」です。(文献1−2)、(文献3)、(文献4)、(文献5)、(文献12)
この「地塊」の平面的な分布域は、テクトニックマップ(図3)もご参照ください。
また。推定地質断面図としては、添付の図7もご参照ください。この図は、(文献5)のFig.4から引用しました。
「モンテローザ・ナップ」のテクトニクス的な位置付けは、(文献4)、(文献5)、(文献12)や、(文献1−2)の古地理図によると、「ペニン系」地質グループのうち、「ブリアンソン・ライズ系」(Briançon rise)(=中部ペニン系)に属している大陸性の「地塊」です。
「モンテローザ・ナップ」を構成する具体的な地質としては、地質図(文献2A)を広域的に見てみると、大部分が古い起源を持ち、複数回の変成作用を受けた「片麻岩」類(gneisses)からなります。
具体的には、堆積岩起源の「パラ・片麻岩」(para genis(独))や、古生代の火成岩起源の片麻岩類からなります。
他には「雲母片岩」(glimmer-scheifer(独))も分布しています。また(文献5)の説明では、「片麻岩」類(gneisses)、「結晶片岩類」(schists)、及び部分的には「角閃岩」(amphibolite)や花崗岩類(granites)も分布している、とされています。
このうち深成岩体(大部分は後に「片麻岩」となっている)の形成時代は、(文献5)によると、約270〜330Maと測定されており、時代的には「石炭紀」〜「ペルム紀」に相当します。
ところで「モンテローザ・ナップ」と類似した「ブリアンソン・ライズ系」(=中部ペニン系)とされる大陸性の「地塊」としては、この「地塊」の北側にある「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」(Sivies Michabel nappe/Sivies Michabel Decke(独))という「地塊」があります。
また5−2章―(5)節に出てくる「ストックホルン・ナップ」(Stokhorn nappe(英)/Stockhorn Decke(独))という小型の「地塊」も、同じく「ブリアンソン・ライズ系」の「地塊」とされています。(文献4)、地質図(文献2A)、地質図(文献3)など。
なお、この「モンテローザ・ナップ」の位置付けとして、「ブリアンソン・ライズ系」ではなく、「ヨーロッパ大陸ブロック」の一部が分離したもの、という異説もあります。(文献6)
さて「ブリアンソン・ライズ」と呼ばれる、中生代の「ペニン系地質区」(Penninic realm)に存在した、この海台状の地域の形成メカニズムやその帰属には諸説ありますが、中生代のうち「ジュラ紀」から「白亜紀」前期には、海没して浅海域堆積物が形成されたり、隆起して陸化し、浸食を受けたりしていたと推定されています。
この連載の2−4章(「ジュラ紀」の「アルプス地域」)、2−5章(「白亜紀」の「アルプス地域」)も、ご参照ください。
その後、「モンテローザ・ナップ」(地塊)を含めた「ブリアンソン・ライズ系」の地質体は、「アルプス造山運動」の際には、「白亜紀」後期から「古第三紀」初頭に形成されていた沈み込み帯から地下深部に沈み込み、高圧型の変成作用を受けたのち、再び地表へと上がって来たものと考えられています(文献1−1)、(文献5)。
「モンテローザ・ナップ」については、地下深部に沈み込んだ際に受けた変成作用の度合いを示す「変成相」でいうと、(文献4)、(文献12)では、「エクロジャイト相」(eclogite facies)相当の変成作用を受けたとされています。(文献5)では「変成相」について明記されていませんが、変成作用のピークは、古第三紀「始新世」と推定しています。
[補足説明2];「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」(地塊/地帯)、及び 「オフィオライト(岩体)」について
この5−2章で紹介している山々のうち、第(4)節で説明している「ブライトホルン」、「クラインマッターホルン」、「ポリュックス」には、「蛇紋岩」が広く分布しています。また第(5)節で説明している「ゴルナーグラート」周辺にも広く分布しています。
これらの「蛇紋岩」は、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」と呼ばれる「地塊」(地帯)に属します。
ここでは、5−2章のあちこちに出てくる、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」(Zermatt-Saas Fee Zone(英)/ Zermatt-Saas Fee Decke(独))と、それに関連する「オフィオライト(岩体)」(ophiolite(英)/Ophiolit、Ophiolith(独))について、まとめて説明します。
(文献1−1)、(文献1−2)、(文献4)、(文献5)、(文献7)、(文献21)などによると、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」という「地塊」(地帯)は、中生代のうち「ジュラ紀」〜「白亜紀」に存在した「ピエモンテ海」(the Piemont Ocean /the Piemonte-Liguria Ocean)という海洋域にあった「海洋性プレート」の断片と推定されています。
「海洋性プレート」は、3層からなります。最上部が「上部地殻」であり、「玄武岩」(basalt)からなります。その下が「下部地殻」であり、「ハンレイ岩」(gabbro)からなります。最下層が「リソスフェアマントル」と呼ばれる、上部マントルの一部であり、「カンラン岩」(peridotite)からなります(文献22)。
「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」には、「玄武岩」が変成作用を受けた「変成玄武岩」(meta-basalt)、(一部には「枕状溶岩構造」(pillow lava structure)が残っている(文献5))、「ハンレイ岩」が変成作用を受けた「変成ハンレイ岩」(meta-gabbro)、及び「カンラン岩」が水(H2O)と反応して化学組成が変化した「蛇紋岩」(serpentinite)が分布しています。
逆に、これらの岩石の存在から、この「地塊」(地帯)が、かつての「海洋性プレート」由来の「地塊」(地帯)である、と考えられているわけです。
(文献5)によると、上記の岩石の他にも、海底堆積物由来の変成岩と考えられる、「(変成)チャート」(meta-chert)、「雲母片岩」(mica-shist)、「石灰質片岩」(calc-schist)、「石英片岩」(quartzite schist)、「結晶質石灰岩(大理石)」(marble)、また、海洋性プレート本体由来の変成岩と考えられる、 「エクロジャイト」(eclogite)、「プラシナイト」(prasinite)、「角閃岩」(amphibolite)も含まれる、とされています。
(※注;上記の各種岩石のうち、海底の堆積物由来の岩石は、「ピエモンテ海」が沈み込んでいた場所に形成された「付加体」由来の「地塊」である、「ツァテ・ナップ」(Tsaté nappe )と区別が難しいので、「ツァテ・ナップ」に入れるべきかもしれません(私見です)。なお「ツァテ・ナップ」については、前回投稿の「補足説明」の項で説明しています。)
また「(変成)玄武岩」、「(変成)ハンレイ岩」、「蛇紋岩」(カンラン岩由来)の3種の岩石の組み合わせをもって、一般的には「オフィオライト(岩体)」(ophiolite(英)/Ophiolit、Ophiolith(独))と呼びます。(文献22)
(※ その上部に堆積した「チャート」(chert)などの堆積物も構成要素とする場合もあり、「オフィオライト」の定義はややあいまいです) (文献22)
「オフィオライト(岩体)」は、かつての「海洋性プレートの断片」と考えられるので、その地域の過去のテクトニクスを考察するうえで、重要なものです。「ヨーロッパアルプス」などの衝突型造山帯や、「海嶺」が「沈み込み帯」へと沈み込んだと推定される場所など、世界のあちこちに分布しています。
「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」の分布域を、地質図(文献2A)のテクトニックレイヤーや、地質図(文献3)などで見ると、「ブライトホルン」などのスイス/イタリア国境稜線にそびえる4000m級の山々の他、スイス側では「ゴルナーグラート周辺」、また南のイタリア側にも広がっています。
「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」の元となった「ピエモンテ海」は、「白亜紀」に、その南側に形成された、海洋プレート沈み込み帯によって「アドリア大陸ブロック」の下へと地下深くへと沈み込み、地表からは消滅しました(文献1−2)。
その後、「アルプス造山運動」の際に、上昇に転じ、その結果、現在のように再び地表に現れています(※ この地塊も含め、「ペニン系」の各「地塊」の上昇メカニズムは、はっきりとはしていません)。
地下深部に沈み込んだ際には、上記の岩体は高圧型の変成作用を受け、変成岩となりました。
変成作用のグレードを示す「変成相」としては、(文献4)、(文献5)では「エクロジャイト相」(eclogite facies)としています。また地質図(文献2A)や(文献4)、(文献5)によると、岩石としての「エクロジャイト」(eclogite)そのものもが残存しており、その点からも、この「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」は、「エクロジャイト相」という、かなり地下深部(圧力で、1.5GP以上、大まかにいうと、地下50km以下)の高圧条件の場所まで沈み込んだことがわかります。
但し(文献21)によると、上昇時の「後退変成作用」(retrograde metamorphism)により、見かけ上は「緑色片岩相」(green-schist facies)、「青色片岩相」(blue-schist facies)になっている、とされています。
また変成ピーク年代は、(文献5)によると、87〜93Ma(U-Pb法/zircon)(=「白亜紀」後期)と推定されています。
これらの「蛇紋岩」は、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」と呼ばれる「地塊」(地帯)に属します。
ここでは、5−2章のあちこちに出てくる、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」(Zermatt-Saas Fee Zone(英)/ Zermatt-Saas Fee Decke(独))と、それに関連する「オフィオライト(岩体)」(ophiolite(英)/Ophiolit、Ophiolith(独))について、まとめて説明します。
(文献1−1)、(文献1−2)、(文献4)、(文献5)、(文献7)、(文献21)などによると、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」という「地塊」(地帯)は、中生代のうち「ジュラ紀」〜「白亜紀」に存在した「ピエモンテ海」(the Piemont Ocean /the Piemonte-Liguria Ocean)という海洋域にあった「海洋性プレート」の断片と推定されています。
「海洋性プレート」は、3層からなります。最上部が「上部地殻」であり、「玄武岩」(basalt)からなります。その下が「下部地殻」であり、「ハンレイ岩」(gabbro)からなります。最下層が「リソスフェアマントル」と呼ばれる、上部マントルの一部であり、「カンラン岩」(peridotite)からなります(文献22)。
「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」には、「玄武岩」が変成作用を受けた「変成玄武岩」(meta-basalt)、(一部には「枕状溶岩構造」(pillow lava structure)が残っている(文献5))、「ハンレイ岩」が変成作用を受けた「変成ハンレイ岩」(meta-gabbro)、及び「カンラン岩」が水(H2O)と反応して化学組成が変化した「蛇紋岩」(serpentinite)が分布しています。
逆に、これらの岩石の存在から、この「地塊」(地帯)が、かつての「海洋性プレート」由来の「地塊」(地帯)である、と考えられているわけです。
(文献5)によると、上記の岩石の他にも、海底堆積物由来の変成岩と考えられる、「(変成)チャート」(meta-chert)、「雲母片岩」(mica-shist)、「石灰質片岩」(calc-schist)、「石英片岩」(quartzite schist)、「結晶質石灰岩(大理石)」(marble)、また、海洋性プレート本体由来の変成岩と考えられる、 「エクロジャイト」(eclogite)、「プラシナイト」(prasinite)、「角閃岩」(amphibolite)も含まれる、とされています。
(※注;上記の各種岩石のうち、海底の堆積物由来の岩石は、「ピエモンテ海」が沈み込んでいた場所に形成された「付加体」由来の「地塊」である、「ツァテ・ナップ」(Tsaté nappe )と区別が難しいので、「ツァテ・ナップ」に入れるべきかもしれません(私見です)。なお「ツァテ・ナップ」については、前回投稿の「補足説明」の項で説明しています。)
また「(変成)玄武岩」、「(変成)ハンレイ岩」、「蛇紋岩」(カンラン岩由来)の3種の岩石の組み合わせをもって、一般的には「オフィオライト(岩体)」(ophiolite(英)/Ophiolit、Ophiolith(独))と呼びます。(文献22)
(※ その上部に堆積した「チャート」(chert)などの堆積物も構成要素とする場合もあり、「オフィオライト」の定義はややあいまいです) (文献22)
「オフィオライト(岩体)」は、かつての「海洋性プレートの断片」と考えられるので、その地域の過去のテクトニクスを考察するうえで、重要なものです。「ヨーロッパアルプス」などの衝突型造山帯や、「海嶺」が「沈み込み帯」へと沈み込んだと推定される場所など、世界のあちこちに分布しています。
「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」の分布域を、地質図(文献2A)のテクトニックレイヤーや、地質図(文献3)などで見ると、「ブライトホルン」などのスイス/イタリア国境稜線にそびえる4000m級の山々の他、スイス側では「ゴルナーグラート周辺」、また南のイタリア側にも広がっています。
「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」の元となった「ピエモンテ海」は、「白亜紀」に、その南側に形成された、海洋プレート沈み込み帯によって「アドリア大陸ブロック」の下へと地下深くへと沈み込み、地表からは消滅しました(文献1−2)。
その後、「アルプス造山運動」の際に、上昇に転じ、その結果、現在のように再び地表に現れています(※ この地塊も含め、「ペニン系」の各「地塊」の上昇メカニズムは、はっきりとはしていません)。
地下深部に沈み込んだ際には、上記の岩体は高圧型の変成作用を受け、変成岩となりました。
変成作用のグレードを示す「変成相」としては、(文献4)、(文献5)では「エクロジャイト相」(eclogite facies)としています。また地質図(文献2A)や(文献4)、(文献5)によると、岩石としての「エクロジャイト」(eclogite)そのものもが残存しており、その点からも、この「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」は、「エクロジャイト相」という、かなり地下深部(圧力で、1.5GP以上、大まかにいうと、地下50km以下)の高圧条件の場所まで沈み込んだことがわかります。
但し(文献21)によると、上昇時の「後退変成作用」(retrograde metamorphism)により、見かけ上は「緑色片岩相」(green-schist facies)、「青色片岩相」(blue-schist facies)になっている、とされています。
また変成ピーク年代は、(文献5)によると、87〜93Ma(U-Pb法/zircon)(=「白亜紀」後期)と推定されています。
[補足説明3];岩石に関する説明
この連載の回でも、色々な種類の岩石が出てきますので、(文献23)、(文献24)などに基づき、ザックリと説明しておきます。詳しくは岩石図鑑や専門書をご覧ください。
(1) 「片麻岩」類(gneisses):変成岩のうち、見た目が濃い色(黒っぽい)の部分と、淡い色(白っぽい)の部分が縞模様(片麻状組織)となっている岩石。
どちらかというと、高温型の変成岩。
日本では分布が限定的だが、「ヨーロッパアルプス」や世界各地の造山帯、及び古い地塊(クラトン)では良く見られる。
元となった岩石や、含まれる鉱物によって、細かく種類が分けられている。
原岩が花崗岩類(深成岩)と推定されるものは、「正片麻岩」(ortho-gneiss)、原岩が堆積岩(泥岩、砂岩など)と推定されるものは、「パラ片麻岩」(「準片麻岩」とも)(para-gneiss)という、2種類に区分するやり方も良く使われる。
(2) 「雲母片岩」(mica-schist);変成岩のうち、「結晶片岩」類の一つ。
結晶片岩類は「片理構造」と呼ばれる、ペラペラしたシートが重なったような構造をもつが、その中に雲母(mica)が多く含まれるものを「雲母片岩」と呼ぶ。
「結晶片岩」類は、多くの名称があって、文献によって同じものが別の名前で呼ばれることもあるが、(文献23)では、「白雲母片岩」(muscovite-schist)が「雲母片岩」類の代表として記載されている。日本では「泥質片岩」や「黒色片岩」と呼ばれる結晶片岩類も、白雲母が多く含まれることが多いので、「雲母片岩」と同類と言える。
(3) 「石灰質片岩」(calc-schist);「結晶片岩」類のうち、原岩が石灰岩類(ドロマイトを含む)と推定されるもの。日本では少ないのか、岩石図鑑(文献23)には載っていない。
(4) 「角閃岩」(amphibolite);変成岩のうち、「角閃石」(類)(hornblende など)と呼ばれる鉱物が多い変成岩。
新鮮面はグレー〜ダークグレーで、風化した表面はやや緑色を帯びる。赤茶色をした鉱物ザクロ石が表れている場合もある。
「角閃岩」の原岩は、「玄武岩」、「ハンレイ岩」などの苦鉄質の火成岩と推定されている。また「角閃岩」の一部は、海洋プレート沈み込み帯で、海洋プレート上部の玄武岩、ハンレイ岩が地下深部で変成作用を受けたもの、と解釈されている。
なお岩石としての「角閃岩」も、鉱物としての「角閃石」も、細かく言うと単一の名称ではなく、元素組成によって多数の種類に分類される。
また、原岩が「ハンレイ岩」(gabbro)であることが明確な場合は、「変成ハンレイ岩」(meta-gabbro)と呼ばれることもある。意味的にはほぼ同じである。
(5) 「エクロジャイト」(eclogite);「玄武岩」、「ハンレイ岩」などの苦鉄質火成岩が、地下深部(圧力で約1.5GPa以上、だいたいの深さでは約50km以下)で高圧型変成作用を受けてできる岩石。
逆に高圧型変成作用(変成相としての「エクロジャイト相」)の指標となる岩石、という意味あいもある。
鉱物としては、緑色の「オンファス輝石」と、赤茶色の「ザクロ石」(ガーネット;garnet)からなる(文献23)。
地下深部の高圧化で安定な岩石であるため、地表に向かって上昇する場合、その過程で「後退変成作用」という変化が起きて鉱物組成が変化し、別の岩石となってしまうことが多く、「エクロジャイト」としての大きな岩体は、世界的にも少ない。
文献や地質図では、「エクロジャイト的な岩石」(eclogetic rocks)や、「エクロジャイト相」(eclogite fasies)(の変成岩)という感じで使われていることが多い。
(6) 「クオーツアイト」(quartzite);岩石図鑑(文献23)には載っていないが、地学事典(文献24)によると、いくつかの意味あいで使われている岩石の名前。日本語では「珪岩」(けいがん)。
広義には「石英」(quartz)が多い岩石という意味あいであり、この章では、おそらく、砂岩由来の、「石英」成分の多い変成岩という意味あいで使われている。
(7) 「プラシナイト」(prasinite);変成岩の一種で、鉱物組成として、アルバイト、緑れん石、バロア閃石からなるもの(文献24)。
この変成岩は日本には少ないのか、岩石図鑑(文献23)にも載っていない。インターネットで調べると、「緑色片岩」の一種という説明もある。
(8) 「蛇紋岩」(serpentinite);上部マントルを構成している主な岩石である、「カンラン岩」が、水分(H2O)と反応して形成された、一種の変成岩。
地表では、新鮮な「カンラン岩」はあまりなく、部分的に蛇紋岩化していたり、完全に「蛇紋岩」となっていることが多い。
外観は緑がかっており、白い部分もあって複雑な模様を呈していることが多い。
鉱物組成としては、「蛇紋石」(serpentine)が主であるが、「カンラン石」(olivine)が残っている場合もある。
(9) 「カンラン岩」(peridotite);「カンラン石」(olivine)を主とし、「直方輝石」(ortho-pyroxene)、「単斜輝石」(clino-pyroxyne)を含む岩石。
見た目は、新鮮なもの緑色〜濃い緑色だが、通常は風化(鉄分の酸化)により、赤茶色をしていることが多い。
上部マントルは全て、この「カンラン岩」からできていると考えられており、いわゆる「プレート」(plate)も、その下部の「リソスフェアマントル」と呼ばれる部分は、「カンラン岩」で出来ていると考えられている。
「蛇紋岩」の項で述べたように、地中で水分(H2O)と反応して蛇紋岩となることが多いため、地表では、蛇紋岩化していない(新鮮な)「カンラン岩」を見かけることは少ない。
(10) 「花崗岩」類(granites);マグマが地下深くで固まった深成岩のうち、シリカ分(SiO2)が多い(=フェルシックな;felsic)深成岩。
鉱物組成としては普通、石英、長石類、黒雲母からなる。
「花崗岩類」と呼ぶ場合は、(狭義の)「花崗岩」(granite)のほか、「花崗閃緑岩」(grano-diorite)、「トーナル岩」(tonalite)、「石英閃緑岩」(quartz diorite)なども含む。
文献や地質図において、英語では(granites),あるいは(granitoids)と書かれている場合があるが、どちらも「花崗岩類」と訳した。
なお、花崗岩類が高度な変成作用を受け、片麻状組織を持つものは、片麻岩類の一種、「正片麻岩」(ortho-gneiss)と呼ばれる。「変成花崗岩類」(meta-granites、meta-granitoids)と呼ぶこともある。
(11) 「玄武岩」(basalt);マグマが地表や海底で固まった火山岩のうち、シリカ分(SiO2)が少ない(=マフィックな;mafic)火山岩。見た目は普通、黒っぽい。
火山から噴出する場合も多いが、海洋地殻の上部は玄武岩からなっており、この章での「玄武岩」は、海洋地殻上部(海洋性プレート上部)由来の玄武岩である。
変成作用を受けた「変成・玄武岩」(meta-basalts)となっていることも多い。
その場合、「角閃石」(hornblende、など)が主要鉱物であるもの、あるいは原岩が「玄武岩」か「ハンレイ岩」か不明な場合は、「角閃岩」(amphibolite)と呼ぶことも多い。
(12) 「ハンレイ岩」(gabbro);マグマが地下深くで固まった深成岩のうち、シリカ分(SiO2)が少ない(=マフィックな;mafic)深成岩。
海洋地殻の下部は「ハンレイ岩」で出来ている。
火山岩の「玄武岩」と化学組成的には同じ。見た目は、白っぽい鉱物(主に長石類)と黒っぽい鉱物(角閃石や輝石類)が入り混じっている感じ。
地表では変成した「変成・ハンレイ岩」(meta-gabbro)となっていることも多い。この章での「ハンレイ岩」は、海洋地殻下部由来の「ハンレイ岩」である。
「変成・ハンレイ岩」は、「玄武岩」と同様に、「変成相」での「角閃岩相」の条件化で変成作用を受け、「角閃石」が主要鉱物であるもの、あるいは原岩が不明は、「角閃岩」と呼ぶことも多い。
(1) 「片麻岩」類(gneisses):変成岩のうち、見た目が濃い色(黒っぽい)の部分と、淡い色(白っぽい)の部分が縞模様(片麻状組織)となっている岩石。
どちらかというと、高温型の変成岩。
日本では分布が限定的だが、「ヨーロッパアルプス」や世界各地の造山帯、及び古い地塊(クラトン)では良く見られる。
元となった岩石や、含まれる鉱物によって、細かく種類が分けられている。
原岩が花崗岩類(深成岩)と推定されるものは、「正片麻岩」(ortho-gneiss)、原岩が堆積岩(泥岩、砂岩など)と推定されるものは、「パラ片麻岩」(「準片麻岩」とも)(para-gneiss)という、2種類に区分するやり方も良く使われる。
(2) 「雲母片岩」(mica-schist);変成岩のうち、「結晶片岩」類の一つ。
結晶片岩類は「片理構造」と呼ばれる、ペラペラしたシートが重なったような構造をもつが、その中に雲母(mica)が多く含まれるものを「雲母片岩」と呼ぶ。
「結晶片岩」類は、多くの名称があって、文献によって同じものが別の名前で呼ばれることもあるが、(文献23)では、「白雲母片岩」(muscovite-schist)が「雲母片岩」類の代表として記載されている。日本では「泥質片岩」や「黒色片岩」と呼ばれる結晶片岩類も、白雲母が多く含まれることが多いので、「雲母片岩」と同類と言える。
(3) 「石灰質片岩」(calc-schist);「結晶片岩」類のうち、原岩が石灰岩類(ドロマイトを含む)と推定されるもの。日本では少ないのか、岩石図鑑(文献23)には載っていない。
(4) 「角閃岩」(amphibolite);変成岩のうち、「角閃石」(類)(hornblende など)と呼ばれる鉱物が多い変成岩。
新鮮面はグレー〜ダークグレーで、風化した表面はやや緑色を帯びる。赤茶色をした鉱物ザクロ石が表れている場合もある。
「角閃岩」の原岩は、「玄武岩」、「ハンレイ岩」などの苦鉄質の火成岩と推定されている。また「角閃岩」の一部は、海洋プレート沈み込み帯で、海洋プレート上部の玄武岩、ハンレイ岩が地下深部で変成作用を受けたもの、と解釈されている。
なお岩石としての「角閃岩」も、鉱物としての「角閃石」も、細かく言うと単一の名称ではなく、元素組成によって多数の種類に分類される。
また、原岩が「ハンレイ岩」(gabbro)であることが明確な場合は、「変成ハンレイ岩」(meta-gabbro)と呼ばれることもある。意味的にはほぼ同じである。
(5) 「エクロジャイト」(eclogite);「玄武岩」、「ハンレイ岩」などの苦鉄質火成岩が、地下深部(圧力で約1.5GPa以上、だいたいの深さでは約50km以下)で高圧型変成作用を受けてできる岩石。
逆に高圧型変成作用(変成相としての「エクロジャイト相」)の指標となる岩石、という意味あいもある。
鉱物としては、緑色の「オンファス輝石」と、赤茶色の「ザクロ石」(ガーネット;garnet)からなる(文献23)。
地下深部の高圧化で安定な岩石であるため、地表に向かって上昇する場合、その過程で「後退変成作用」という変化が起きて鉱物組成が変化し、別の岩石となってしまうことが多く、「エクロジャイト」としての大きな岩体は、世界的にも少ない。
文献や地質図では、「エクロジャイト的な岩石」(eclogetic rocks)や、「エクロジャイト相」(eclogite fasies)(の変成岩)という感じで使われていることが多い。
(6) 「クオーツアイト」(quartzite);岩石図鑑(文献23)には載っていないが、地学事典(文献24)によると、いくつかの意味あいで使われている岩石の名前。日本語では「珪岩」(けいがん)。
広義には「石英」(quartz)が多い岩石という意味あいであり、この章では、おそらく、砂岩由来の、「石英」成分の多い変成岩という意味あいで使われている。
(7) 「プラシナイト」(prasinite);変成岩の一種で、鉱物組成として、アルバイト、緑れん石、バロア閃石からなるもの(文献24)。
この変成岩は日本には少ないのか、岩石図鑑(文献23)にも載っていない。インターネットで調べると、「緑色片岩」の一種という説明もある。
(8) 「蛇紋岩」(serpentinite);上部マントルを構成している主な岩石である、「カンラン岩」が、水分(H2O)と反応して形成された、一種の変成岩。
地表では、新鮮な「カンラン岩」はあまりなく、部分的に蛇紋岩化していたり、完全に「蛇紋岩」となっていることが多い。
外観は緑がかっており、白い部分もあって複雑な模様を呈していることが多い。
鉱物組成としては、「蛇紋石」(serpentine)が主であるが、「カンラン石」(olivine)が残っている場合もある。
(9) 「カンラン岩」(peridotite);「カンラン石」(olivine)を主とし、「直方輝石」(ortho-pyroxene)、「単斜輝石」(clino-pyroxyne)を含む岩石。
見た目は、新鮮なもの緑色〜濃い緑色だが、通常は風化(鉄分の酸化)により、赤茶色をしていることが多い。
上部マントルは全て、この「カンラン岩」からできていると考えられており、いわゆる「プレート」(plate)も、その下部の「リソスフェアマントル」と呼ばれる部分は、「カンラン岩」で出来ていると考えられている。
「蛇紋岩」の項で述べたように、地中で水分(H2O)と反応して蛇紋岩となることが多いため、地表では、蛇紋岩化していない(新鮮な)「カンラン岩」を見かけることは少ない。
(10) 「花崗岩」類(granites);マグマが地下深くで固まった深成岩のうち、シリカ分(SiO2)が多い(=フェルシックな;felsic)深成岩。
鉱物組成としては普通、石英、長石類、黒雲母からなる。
「花崗岩類」と呼ぶ場合は、(狭義の)「花崗岩」(granite)のほか、「花崗閃緑岩」(grano-diorite)、「トーナル岩」(tonalite)、「石英閃緑岩」(quartz diorite)なども含む。
文献や地質図において、英語では(granites),あるいは(granitoids)と書かれている場合があるが、どちらも「花崗岩類」と訳した。
なお、花崗岩類が高度な変成作用を受け、片麻状組織を持つものは、片麻岩類の一種、「正片麻岩」(ortho-gneiss)と呼ばれる。「変成花崗岩類」(meta-granites、meta-granitoids)と呼ぶこともある。
(11) 「玄武岩」(basalt);マグマが地表や海底で固まった火山岩のうち、シリカ分(SiO2)が少ない(=マフィックな;mafic)火山岩。見た目は普通、黒っぽい。
火山から噴出する場合も多いが、海洋地殻の上部は玄武岩からなっており、この章での「玄武岩」は、海洋地殻上部(海洋性プレート上部)由来の玄武岩である。
変成作用を受けた「変成・玄武岩」(meta-basalts)となっていることも多い。
その場合、「角閃石」(hornblende、など)が主要鉱物であるもの、あるいは原岩が「玄武岩」か「ハンレイ岩」か不明な場合は、「角閃岩」(amphibolite)と呼ぶことも多い。
(12) 「ハンレイ岩」(gabbro);マグマが地下深くで固まった深成岩のうち、シリカ分(SiO2)が少ない(=マフィックな;mafic)深成岩。
海洋地殻の下部は「ハンレイ岩」で出来ている。
火山岩の「玄武岩」と化学組成的には同じ。見た目は、白っぽい鉱物(主に長石類)と黒っぽい鉱物(角閃石や輝石類)が入り混じっている感じ。
地表では変成した「変成・ハンレイ岩」(meta-gabbro)となっていることも多い。この章での「ハンレイ岩」は、海洋地殻下部由来の「ハンレイ岩」である。
「変成・ハンレイ岩」は、「玄武岩」と同様に、「変成相」での「角閃岩相」の条件化で変成作用を受け、「角閃石」が主要鉱物であるもの、あるいは原岩が不明は、「角閃岩」と呼ぶことも多い。
【注釈の項】
注1) 「ヴァリス」(山群、州)の読み方、表記について
このスイスの州は、ドイツ語圏とフランス語圏にまたがっている為、以下2つの表記、読み方があります。
・ドイツ語では、”Wallis” 、読み方(日本語表記)は、(ヴァリス)
・フランス語では、”Valais” 、読み方(日本語表記)は、(ヴァレー)
この章では、日本語表記としては、(文献8)、(文献10)など日本のガイドブックでよく使われている、「ヴァリス」とし、現地語表記を併用する場合は、地質学の文献などで多く使われている、フランス語由来の(Valais)を使用します。
注2) 山々の標高について
この章で記載した山々などの標高は、スイスのオンライン地質図(文献2A)のうち、地形図レイヤーの値を採用し、記載しています。文献、ガイドブックなどによっては、数m程度違う値となっている場合があります。
注3) スイスのオンライン地質図について
スイスのオンライン地質図は、パソコン等で見る「ウエブ版」(文献2A)と、スマホのアプリとなっている「アプリ版」(文献2B)(アプリ名;“Swiss topo”)とがあります。
どちらも(Swiss topo)という機関がデータ元ですが、「ウエブ版」(文献2A)は、説明が詳しく、解像度も高い一方で、ポップアップの地質解説がドイツ語なのでちょっと解りにくい、という短所もあります。
一方「アプリ版」(文献2B)は、地質解説が英語で解りやすいのですが、解像度が低く、かつ、場所が違っていても似たような地質体をグループ化して説明している点は、短所だと思います。
また細かく見ると、地質説明に、けっこう違いがあります。
この章では、主に(文献2A)を参照し、(文献2B)は参考程度としました。
それぞれの地質図の使い方、見方などは、「参考文献」の項をご覧ください。
注4) 「クラインマッターホルン」(Kline Matterhorn)という地名について
「クラインマッターホルン」は元々、ツェルマットからのロープウエイの終点にある小さな岩峰の名前です。そこにあるロープウエイの駅名も、以前は「クラインマッターホルン駅」でしたが(文献9)、最近では、「マッターホルン・グレッシャーパラダイス(駅)」(Matterhorn Glacier Paradise)という、いかにも観光地的な名称に変更されています(文献8)。
この章では、地名も岩峰の名称も、「クラインマッターホルン」に統一しています。
注5) “Ma”は、百万年前を意味する単位です。?
このスイスの州は、ドイツ語圏とフランス語圏にまたがっている為、以下2つの表記、読み方があります。
・ドイツ語では、”Wallis” 、読み方(日本語表記)は、(ヴァリス)
・フランス語では、”Valais” 、読み方(日本語表記)は、(ヴァレー)
この章では、日本語表記としては、(文献8)、(文献10)など日本のガイドブックでよく使われている、「ヴァリス」とし、現地語表記を併用する場合は、地質学の文献などで多く使われている、フランス語由来の(Valais)を使用します。
注2) 山々の標高について
この章で記載した山々などの標高は、スイスのオンライン地質図(文献2A)のうち、地形図レイヤーの値を採用し、記載しています。文献、ガイドブックなどによっては、数m程度違う値となっている場合があります。
注3) スイスのオンライン地質図について
スイスのオンライン地質図は、パソコン等で見る「ウエブ版」(文献2A)と、スマホのアプリとなっている「アプリ版」(文献2B)(アプリ名;“Swiss topo”)とがあります。
どちらも(Swiss topo)という機関がデータ元ですが、「ウエブ版」(文献2A)は、説明が詳しく、解像度も高い一方で、ポップアップの地質解説がドイツ語なのでちょっと解りにくい、という短所もあります。
一方「アプリ版」(文献2B)は、地質解説が英語で解りやすいのですが、解像度が低く、かつ、場所が違っていても似たような地質体をグループ化して説明している点は、短所だと思います。
また細かく見ると、地質説明に、けっこう違いがあります。
この章では、主に(文献2A)を参照し、(文献2B)は参考程度としました。
それぞれの地質図の使い方、見方などは、「参考文献」の項をご覧ください。
注4) 「クラインマッターホルン」(Kline Matterhorn)という地名について
「クラインマッターホルン」は元々、ツェルマットからのロープウエイの終点にある小さな岩峰の名前です。そこにあるロープウエイの駅名も、以前は「クラインマッターホルン駅」でしたが(文献9)、最近では、「マッターホルン・グレッシャーパラダイス(駅)」(Matterhorn Glacier Paradise)という、いかにも観光地的な名称に変更されています(文献8)。
この章では、地名も岩峰の名称も、「クラインマッターホルン」に統一しています。
注5) “Ma”は、百万年前を意味する単位です。?
【参考文献】
(文献1) O. A. Pfiffner 著 “Geology of the Alps”, 2nd edition ,Wiley Blackball社刊,
(2014); (原著はドイツ語版で、2014年にドイツの出版社刊)
(文献1−1) (文献1)のうち、第5−2章 「中部アルプスのテクトニックな構造」
(Tectonic structure of the Alps ; the Central Alps)の項
(文献1−2) (文献1)のうち、第3−2章
「中生代のアルプス地域におけるテクトニックな進化」
(the Alpine domain in the Mesozoic; Plate Tectonic evolution)の項の、
図3-16,図3-28(「ジュラ紀」、「白亜紀」の古地理図)。
(文献2A) スイスのオンライン地質図(ウエブ版)
https://map.geo.admin.ch/
※ 地質図は、メニューより、 > Geocatalog > Nature and Environment > Geology
> GeoCover Vector Datasets 、より見ることができる。
※ 断層、テクトニック構造、「地塊」分布図などは、メニューより、> Geocatalog >
Nature and Environment > Geology > Tectonics 500 、より見ることができる。
※ 地形図も兼ねているので、地形図レイヤーより、山名、標高なども確認できる。
※ 地図自体は(EN)を選ぶと英語表記になるが、ポップアップの地質解説はドイツ語
なので、ちょっと解りにくい。
※ 利用したバージョンは、v 1.59.0
(文献2B) スイスのオンライン地質図(スマホアプリ版)
※ スマホに、“Swiss topo” というアプリをインストールして利用する。
※ メニューより、”geology” > “Gological Map” を選ぶと地質図を見ることができる。
※ 地図自体も、ポップアップの地質解説も全て英語なので、解りやすい。
※ 利用したバージョンは、v 1.19.1
(文献3) スイスのテクトニックマップ(紙媒体)
“Tectonische Karte der Schweiz”
50万分の1 図幅、”Swiss topo”発行、(発行年度不明)
ISBN 3-906723-56-9 (“Swiss topo” のインターネットサイトより購入)
(文献4) スイスの地質に関する解説サイト
“ Strati CH;Lithostratigraphic Lexicon of Switzerland ”
https://www.strati.ch/en/
のうち、(Monte Rosa-Decke)、(Zermatt Saas-Decke)、(Tsate-Decke)、
(Stockhorn-Decke (Zermatt))、(Gornergrat-Decke) などの各項
(文献5) A. Steck、 H. Masson、 M Robyr 、共著
“Tectonics of the Monte Rosa and surrounding nappes (Switzerland and Italy):
Tertiary phases of subduction, thrusting and folding in the Pennine Alps”
Swiss Journal of Geosciences誌、vol. 108, p3?34 (2015)
https://sjg.springeropen.com/articles/10.1007/s00015-015-0188-x
(DOIアドレス; 10.1007/s00015-015-0188-x)
※ 上記のサイトから、PDF版が無料でダウンロードできる。
※ 「モンテローザ」地塊と、その周辺の地質構造についての論文
(文献6) N.Froitzheim 著
“ Origin of the Monte Rosa nappe in the Pennine Alps ; a new working hypothesis”
Geological Society of America Bulletin誌、vol. 113、 page 604-614、 (2001)
https://www.researchgate.net/publication/249527067_Origin_of_the_Monte_Rosa_nappe_in_the_Pennine_Alps-A_new_working_hypothesis
(DOIアドレス; 10.1130/0016-7606(2001)113<0604:OOTMRN>2.0.CO;2)
※ 上記のサイトから、PDF版が無料でダウンロードできる。
※ 「モンテローザ・ナップ」の起源に関する仮説
(文献7) M. Marthaler、H. Rougier 著、
“ An Outstanding Mountain: The Matterhorn”
(内容からの意訳;「マッターホルンの地質と地形」))
書籍;“Landscapes and Landforms of Switzerland ”、pp.187-199 (2021)の一部
https://www.researchgate.net/publication/342847689_An_Outstanding_Mountain_The_Matterhorn
(DOIアドレス; https///www.DOI:10.1007/978-3-030-43203-4_13 )
※ このサイトより、PDFファイルが無料でダウンロードできる。
※ 「マッターホルン」の地質、地形のほか、周辺の地質についての解説もある
(文献8) 「地球の歩き方;スイス(2024-2025年版)」 Gakken社 刊 (2023)
(文献9) 小川 清美 著
「ヨーロッパアルプス ハイキングガイド(2);ツェルマット、周辺を歩く」
山と渓谷社 刊 (2000)
(文献10) リヒャルト・ゲーデケ著、島田荘平、島田陽子 共訳
「アルプス4000m峰 登山ガイド」 山と渓谷社 刊 (1997)
(文献11) 近藤 等 著 「アルプスの名峰」 山と渓谷社 版 (1984)
(文献12) ウイキペディア英語版の、(Monte Rosa)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Rosaが
(2025年10月 閲覧)
(文献13) ウイキペディア英語版の、(Breithorn)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Breithorn
(2025年10月 閲覧)
(文献14) ウイキペディア英語版の、(Pollux)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Pollux_(mountain)
(2025年10月 閲覧)
(文献15) ウイキペディア英語版の、(Castor)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Castor_(mountain)
(2025年10月 閲覧)
(文献16) ウイキペディア日本語版の、「双子座」の項、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B5%E3%81%9F%E3%81%94%E5%BA%A7
(2025年10月 閲覧
(文献17) ウイキペディア英語版の、(Liskamm)の項、
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyskamm
(2025年10月 閲覧)
(文献18) ウイキペディア英語版の、(Gornergrat)の項、
https://en.wikipedia.org/wiki/Gornergrat
(2025年10月 閲覧)
(文献19) ウイキペディア英語版の、(Stockhorn (Zermatt))の項、
https://en.wikipedia.org/wiki/Stockhorn_(Zermatt)
(2025年10月 閲覧)
(文献20) ウイキペディ・ドイツ語版の、(Oberrothorn)の項、
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberrothorn
(2025年10月 閲覧)
(文献21) ウイキペディア英語版の、(Zermatt-Saas zone)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Zermatt-Saas_zone
(2025年10月 閲覧)
(文献22) ウイキペディア英語版の、(ophiolite)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Ophiolite
(2025年10月 閲覧)
(文献23) 西本 著「観察を楽しむ、特徴がわかる 岩石図鑑」 ナツメ社刊 (2020)
のうち、「蛇紋岩」、「片麻岩」、「エクロジャイト」、「カンラン岩」、「ハンレイ岩」、などの各項
(文献24) 地質団体研究会 編 「新版 地質事典」 平凡社 刊(1996)のうち、
「オフィオライト」、「プラシナイト」、「クオーツアイト」、「雲母片岩」などの各項
(2014); (原著はドイツ語版で、2014年にドイツの出版社刊)
(文献1−1) (文献1)のうち、第5−2章 「中部アルプスのテクトニックな構造」
(Tectonic structure of the Alps ; the Central Alps)の項
(文献1−2) (文献1)のうち、第3−2章
「中生代のアルプス地域におけるテクトニックな進化」
(the Alpine domain in the Mesozoic; Plate Tectonic evolution)の項の、
図3-16,図3-28(「ジュラ紀」、「白亜紀」の古地理図)。
(文献2A) スイスのオンライン地質図(ウエブ版)
https://map.geo.admin.ch/
※ 地質図は、メニューより、 > Geocatalog > Nature and Environment > Geology
> GeoCover Vector Datasets 、より見ることができる。
※ 断層、テクトニック構造、「地塊」分布図などは、メニューより、> Geocatalog >
Nature and Environment > Geology > Tectonics 500 、より見ることができる。
※ 地形図も兼ねているので、地形図レイヤーより、山名、標高なども確認できる。
※ 地図自体は(EN)を選ぶと英語表記になるが、ポップアップの地質解説はドイツ語
なので、ちょっと解りにくい。
※ 利用したバージョンは、v 1.59.0
(文献2B) スイスのオンライン地質図(スマホアプリ版)
※ スマホに、“Swiss topo” というアプリをインストールして利用する。
※ メニューより、”geology” > “Gological Map” を選ぶと地質図を見ることができる。
※ 地図自体も、ポップアップの地質解説も全て英語なので、解りやすい。
※ 利用したバージョンは、v 1.19.1
(文献3) スイスのテクトニックマップ(紙媒体)
“Tectonische Karte der Schweiz”
50万分の1 図幅、”Swiss topo”発行、(発行年度不明)
ISBN 3-906723-56-9 (“Swiss topo” のインターネットサイトより購入)
(文献4) スイスの地質に関する解説サイト
“ Strati CH;Lithostratigraphic Lexicon of Switzerland ”
https://www.strati.ch/en/
のうち、(Monte Rosa-Decke)、(Zermatt Saas-Decke)、(Tsate-Decke)、
(Stockhorn-Decke (Zermatt))、(Gornergrat-Decke) などの各項
(文献5) A. Steck、 H. Masson、 M Robyr 、共著
“Tectonics of the Monte Rosa and surrounding nappes (Switzerland and Italy):
Tertiary phases of subduction, thrusting and folding in the Pennine Alps”
Swiss Journal of Geosciences誌、vol. 108, p3?34 (2015)
https://sjg.springeropen.com/articles/10.1007/s00015-015-0188-x
(DOIアドレス; 10.1007/s00015-015-0188-x)
※ 上記のサイトから、PDF版が無料でダウンロードできる。
※ 「モンテローザ」地塊と、その周辺の地質構造についての論文
(文献6) N.Froitzheim 著
“ Origin of the Monte Rosa nappe in the Pennine Alps ; a new working hypothesis”
Geological Society of America Bulletin誌、vol. 113、 page 604-614、 (2001)
https://www.researchgate.net/publication/249527067_Origin_of_the_Monte_Rosa_nappe_in_the_Pennine_Alps-A_new_working_hypothesis
(DOIアドレス; 10.1130/0016-7606(2001)113<0604:OOTMRN>2.0.CO;2)
※ 上記のサイトから、PDF版が無料でダウンロードできる。
※ 「モンテローザ・ナップ」の起源に関する仮説
(文献7) M. Marthaler、H. Rougier 著、
“ An Outstanding Mountain: The Matterhorn”
(内容からの意訳;「マッターホルンの地質と地形」))
書籍;“Landscapes and Landforms of Switzerland ”、pp.187-199 (2021)の一部
https://www.researchgate.net/publication/342847689_An_Outstanding_Mountain_The_Matterhorn
(DOIアドレス; https///www.DOI:10.1007/978-3-030-43203-4_13 )
※ このサイトより、PDFファイルが無料でダウンロードできる。
※ 「マッターホルン」の地質、地形のほか、周辺の地質についての解説もある
(文献8) 「地球の歩き方;スイス(2024-2025年版)」 Gakken社 刊 (2023)
(文献9) 小川 清美 著
「ヨーロッパアルプス ハイキングガイド(2);ツェルマット、周辺を歩く」
山と渓谷社 刊 (2000)
(文献10) リヒャルト・ゲーデケ著、島田荘平、島田陽子 共訳
「アルプス4000m峰 登山ガイド」 山と渓谷社 刊 (1997)
(文献11) 近藤 等 著 「アルプスの名峰」 山と渓谷社 版 (1984)
(文献12) ウイキペディア英語版の、(Monte Rosa)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Rosaが
(2025年10月 閲覧)
(文献13) ウイキペディア英語版の、(Breithorn)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Breithorn
(2025年10月 閲覧)
(文献14) ウイキペディア英語版の、(Pollux)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Pollux_(mountain)
(2025年10月 閲覧)
(文献15) ウイキペディア英語版の、(Castor)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Castor_(mountain)
(2025年10月 閲覧)
(文献16) ウイキペディア日本語版の、「双子座」の項、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B5%E3%81%9F%E3%81%94%E5%BA%A7
(2025年10月 閲覧
(文献17) ウイキペディア英語版の、(Liskamm)の項、
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyskamm
(2025年10月 閲覧)
(文献18) ウイキペディア英語版の、(Gornergrat)の項、
https://en.wikipedia.org/wiki/Gornergrat
(2025年10月 閲覧)
(文献19) ウイキペディア英語版の、(Stockhorn (Zermatt))の項、
https://en.wikipedia.org/wiki/Stockhorn_(Zermatt)
(2025年10月 閲覧)
(文献20) ウイキペディ・ドイツ語版の、(Oberrothorn)の項、
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberrothorn
(2025年10月 閲覧)
(文献21) ウイキペディア英語版の、(Zermatt-Saas zone)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Zermatt-Saas_zone
(2025年10月 閲覧)
(文献22) ウイキペディア英語版の、(ophiolite)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Ophiolite
(2025年10月 閲覧)
(文献23) 西本 著「観察を楽しむ、特徴がわかる 岩石図鑑」 ナツメ社刊 (2020)
のうち、「蛇紋岩」、「片麻岩」、「エクロジャイト」、「カンラン岩」、「ハンレイ岩」、などの各項
(文献24) 地質団体研究会 編 「新版 地質事典」 平凡社 刊(1996)のうち、
「オフィオライト」、「プラシナイト」、「クオーツアイト」、「雲母片岩」などの各項
【書記事項】
・経緯;元の投稿;本内容は、2025年10月10日に、「5−2章 ヴァリス山群の地質(その1)」(初稿)として投稿したものの一部。
それとは別に、5−2章(その2)として、「ヴァイスホルン」などの説明を、2025年10月18日に投稿。(ー>この投稿分は、後に、5−2章(その3)と改題)
△改訂1;(2025年10月21日)
・ 元の、5−2章(その1;初稿)の分量が多すぎて読みづらいので、2分割することとした。 2分割のうち、5−2章(その1;改)は、初稿のうち、第(1)節、第(2)節とした。
よってこの5−2章(その2;新)は、(その1;初稿)のうち、第(3)、(4)、(5)節をまとめ直したものである。
・5−2章の各節に説明が分散していた、「モンテローザ・ナップ」 及び「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」、「オフィオライト(岩体)」、について、それぞれ「補足説明1」,「補足説明2:としてまとめた。
・岩石に関する説明を、「注釈」の項から、「補足説明3」の項に移動させた。
・最新改訂年月日;2025年10月21日
それとは別に、5−2章(その2)として、「ヴァイスホルン」などの説明を、2025年10月18日に投稿。(ー>この投稿分は、後に、5−2章(その3)と改題)
△改訂1;(2025年10月21日)
・ 元の、5−2章(その1;初稿)の分量が多すぎて読みづらいので、2分割することとした。 2分割のうち、5−2章(その1;改)は、初稿のうち、第(1)節、第(2)節とした。
よってこの5−2章(その2;新)は、(その1;初稿)のうち、第(3)、(4)、(5)節をまとめ直したものである。
・5−2章の各節に説明が分散していた、「モンテローザ・ナップ」 及び「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」、「オフィオライト(岩体)」、について、それぞれ「補足説明1」,「補足説明2:としてまとめた。
・岩石に関する説明を、「注釈」の項から、「補足説明3」の項に移動させた。
・最新改訂年月日;2025年10月21日
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
ベルクハイルさんの記事一覧
※この記事はヤマレコの「ヤマノート」機能を利用して作られています。
どなたでも、山に関する知識や技術などのノウハウを簡単に残して共有できます。
ぜひご協力ください!

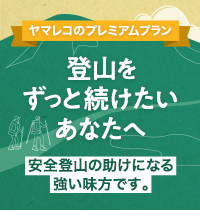












コメントを編集
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する