吉備中山〜大平山〜龍王山☆吉備路の山と神社を巡る

- GPS
- 03:44
- 距離
- 16.2km
- 登り
- 696m
- 下り
- 693m
コースタイム
- 山行
- 3:26
- 休憩
- 0:17
- 合計
- 3:43
| 天候 | 快晴 |
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2020年01月の天気図 |
| アクセス |
利用交通機関:
電車
下山は備中高松駅へ |
写真
感想
三連休初日は晴天が約束されるというのにこの日も岡山へ出張である。仕事は午後からなので午前中のうちに岡山近郊の山を散策することにする。吉備路の山は縦走大会が毎年行われているようで、吉備人出版から大会のための地図が発行されている。その縦走大会の後半のコース、吉備津中山から龍王山までを辿るコースを考える。
吉備津駅を降りるとすぐに吉備津神社への松の樹が両側に立ち並ぶ長い参道に出る。参道の途中を吉備線の線路が横切る。ところでこの吉備線は桃太郎線と名前が変更されている。その是非はともかく、走る沿線の土地を反映しないこの命名はどうもしっくりと来ない。
参道を辿って吉備津神社に詣でると、かなりの人である。この山の北東の山麓には吉備津彦神社があるのだが、なぜ山麓に寄り添うように二つの神社があるのかというその経緯はなんとも興味深い歴史的な背景があるようだ。かつて吉備の国が広大であり豊かな国であったことから律令制が始まるとこの国が大きな力を有することを怖れた大和朝廷により備前、備中、備後に分割されることになる。この吉備の中山は備前と備中の国境となり、吉備随一の神社であった吉備津神社は備中側になったので、その備前側に吉備津神社から分社された吉備津彦神社が新たに建立されることになったらしい。
ちなみに明治の廃藩置県に当たっても文化的には岡山に近い備後の福山が広島県に含められたのも、岡山に含めると近隣の県との均衡が著しく悪くなるからという理由だったらしく、改めて吉備の国の豊かさに思い至るのであった。
参詣の人々で賑わう吉備津神社の社殿の右手に続く長い廻廊へと入るとそれまでの雑踏が嘘のように静かで人影がない。ただ、廻廊の途中にあるえびす社からは絶え間なく喧しいスピーカーの音が聞こえてくる。この日は十日えびすの日らしい。
廻廊を通り抜けると吉備中山への登山口がある。遊歩道に入ると樹高の自然林の林の中を緩やかに登ってゆく。しかし、雰囲気の良い林は唐突に終わり、車道に出る。右手の林の中には細い踏み跡が見える。以前の登山道なのだろう。やがて車道の左手には幅広い階段の道が現れる。階段を登り詰めるとすぐ左手には御陵がある。孝霊天皇の皇子、大吉備津彦命の墓とされているらしい。
御陵の前には吉備中山の山名標と備前と備中を境する国境石がある。御陵の右手から登山路が先に伸びている。登山路はピークを東にトラバースしてゆくが、左手のピークに登る道へと入ると樹林に囲まれた山頂広場に三角点を見出す。鏡岩の案内標に導かれるままに南に下って見ると、山中に忽然と幾つもの巨石が現れる。おそらく古墳を造成するために担ぎあげられた石のようだ。石の表面には不自然な無数の傷がある。石の表面を平らにするための古代の技術によるものだろうが、それは巨大な石に描かれた現代的な現代的な美術作品のように思われて仕方がないのであった。
尾根道を先に進むと鏡石ほどではないが大きな石が散見する。環状石籬(ストーンサークル)と命名された石の集簇は古墳の造成のために担ぎ上げたものの使用されなかった石が無造作に抛擲されているようにも思われた。
吉備中山から下ると吉備津彦神社の裏手にはいくつもの末社が現れる。
吉備津彦神社は先の吉備津神社をさらに上回る参詣客で賑わっている。吉備津神社から分社されたというにしては吉備津神社よりも社殿がかなり壮麗に思われた。
吉備津神社からは自転車専用道路を歩いて次の大平山へと向かう。自転車専用道路のすぐ脇には水路が流れているが、さすがに水路との間にはガードレールが設けられている。岡山県のこの地域には水路が縦横無尽に走っているが、水路と道路との間にガードレールが設けられておらず、故に水路に落ちて重傷を負う人が後を絶たないらしい。
ため池を過ぎると車止めを過ぎると、林道となる。道は大平山の北側の暗部を目指して雑木林の中を緩やかに登ってゆく。大平山に北斜面から登りに入ると一面のススキの原となり、龍王山や鬼ノ城といった吉備路の山々の展望が広がり始める。大平山の山頂は吉備路の縦走路の東側の山々の中では随一の展望台である。龍王山の山麓にはいくつもの幟がはためく最上(さいじょう)稲荷が目に入る。
大平山から北上するとここからはようやく登山道らしくなる。樹高の低い広葉樹林の中を延々を進むことになる。吉備中山がいかに樹高の高い樹々が多かったかということに改めて思い到る。尾根を緩やかに下り、次の三光山のとの間に鞍部に至ると大坪越であり、峠越えの道と交差する。峠の手前には古い石積みの土台がある。かつてはお地蔵様が鎮座していたのではないかと思われる。
峠からは先は送電線巡視路のようだ。三光山のなだらかな山頂は山名標がなければ山頂と分からずに通過してしまいそうな樹林の中の地味な場所である。山頂の北東に送電線鉄塔があるので眺望を期待して降りてみる。正面には岡山の北に位置する金山が見えるが樹林が邪魔をする。三光山から北に尾根を辿ると、ようやく次の送電線鉄塔ではようやく眺望が開け、東側に岡山の北の金山を大きく望む。
三光山から降りると長野の集落を抜けて、龍王山の東麓にある最上稲荷山グランドの裏手から龍王山への登山道がはじまる。静かな自然林の尾根を登ってゆく。一気に250m近くを登るので、低山でありながら、それなりの急登である。1月とは思えぬ陽気に汗ばみ始める。
山頂部に至ると突然、舗装路に飛び出し、人が多く往来している。最上稲荷の奥の院への参道らしい。南無妙法蓮華経と刻まれた石碑が多く立ち並ぶ参道を山頂の方へ進むと社殿が現れる。稲荷というから神社かと思っていたが、どう見ても寺院のように思われる。後で調べてわかったのだが、最上稲荷は正確には最上稲荷山妙教寺であり、明治になって神仏分離令により神社から寺院が切り離され、いわゆる神宮寺の形態をとるものは締め出されたのだが、ここは例外的に神仏習合の合祀が許されたらしい。
多くの人で賑わう山頂部を一人、GPSを頼りに三角点を探す。人気のない境内の片隅に人目をはばかるかのように三角点の石標と国土地理院の白いポールと立っていた。ここで備中高松から岡山に戻る帰りの列車の時間を確認すると、便は1時間に一本しかなく、次の12時31分を逃すとその次は13時19分までない。のんびりと三角点を探している場合ではなかった。ここからはランニングで、次の12時31分の列車に間に合うことを試みることにする。
山道を駆け下り始めるが、右手に八畳岩の案内が目に入る。立ち寄っている場合ではないのだが、眺望が気になる。登山道をそれて展望台に至ると岡山方面に至るまで広大な展望が広がっている。右手には倉敷北部の山々が目に入る。昨日の朝に登った福山は最高峰であり、標高は500mにも満たないのであるが、その山容はなんとも大きく見えるのだった。
下山したところは最上稲荷の本殿であり、吉備津神社、吉備津彦神社をはるかに上回る多くの参詣客で大賑わいである。両脇に店が立ち並ぶ参道はおよそ走れたものではない。参道の西側の道を走る。広大な駐車場も車で埋め尽くされているようだ。正月はどうれほど多くの初詣客で賑わったことだろうか。
備中高松の駅に向けて車道をひた走りに走るが、距離を考えるとどうもギリギリ間に合わなさそうだ。駅の近くにきたところで、二両編成の朱色の気動車が岡山方面へと進んでいくのが目に入る。幸い、駅の近くにイートイン・スペースのあるA-coopがあったので、弁当を食べながら次の列車を待つ。備中高松の駅に向かうと仕事に向かうのが嫌気がさすほどの雲ひとつない澄み切った青空がどこまでも広がっているのだった。
コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
 山猫
山猫

 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大 拍手
拍手



















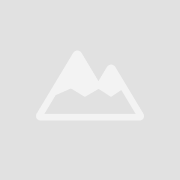







いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する