(はじめに)
「ヨーロッパアルプス」における地質構造の複雑さは、大部分が、新生代の「アルプス造山運動」の最中に、地質体が色々な応力を受けて、変形したためにできたものです。
代表的な変形構造としては、日本の山地でも一般的な褶曲構造(fold)のほか、スラスト断層(thrust)によって分断され、かつ水平方向へと移動した地質体である「ナップ」(nappe)があげられます。その他にも、逆断層、正断層など、断層によって分断された構造も多数あります。
(文献1)では、「アルプス造山運動」に関連する、各種変形構造について、まとまった説明はないのですが、多数の図や写真で、それらを確認できますので、この章ではそれらを紹介します。
なお、この章で用いる用語の意味、定義については、「補足説明」の項にまとめました。
代表的な変形構造としては、日本の山地でも一般的な褶曲構造(fold)のほか、スラスト断層(thrust)によって分断され、かつ水平方向へと移動した地質体である「ナップ」(nappe)があげられます。その他にも、逆断層、正断層など、断層によって分断された構造も多数あります。
(文献1)では、「アルプス造山運動」に関連する、各種変形構造について、まとまった説明はないのですが、多数の図や写真で、それらを確認できますので、この章ではそれらを紹介します。
なお、この章で用いる用語の意味、定義については、「補足説明」の項にまとめました。
4−3章―第(1)節 「地質グループ」のナップ群としての移動
特に中生代に形成された堆積物性の各「地質グループ」は、新生代の「アルプス造山運動」の最中に、「ナップ群」として水平方向に移動していることが推定されています。そのことが、4−1章で説明した地質平面図において、各「地質グループ」の複雑な配置に表われています。
例として「中部アルプス」の各「地質グループ」を表した地質平面図を、図1((文献1)の5-2-1)を添付しますので、ご参照ください。
図2では、「ナップ群」の水平方向への移動の模式図を示します。これは、(文献1−1)の図5-2-15(b)を引用したもので、「中部アルプス」の「ヘルベチカ系」、「ドーフィネ系」地質グループに属する各「地質体」(ナップ)群が移動した様子を模式図として表したものです。
これによると、黄緑色で色分けされた、「中部アルプス」における、「ヘルベチカ系」、「ドーフィネ系」地質グループに属する各「地質体」(ナップ)は、「アルプス造山運動」が始まる前から現世に至る間に、北〜北西方向に、約50〜95kmも移動が起こったと推定されています。
なおこの図では、黄緑色で色分けされた数十kmサイズの「地質体」を、一つの「ナップ」としていますが、個々の「ナップ」は、細かい構造としては、多数のスラスト断層群によって多数の「ナップ群」として切り刻まれています。さらにそれらが重なり合った、「インブリケート構造」(imbricate structure/「覆瓦構造」)を構成しています。
例として「中部アルプス」の各「地質グループ」を表した地質平面図を、図1((文献1)の5-2-1)を添付しますので、ご参照ください。
図2では、「ナップ群」の水平方向への移動の模式図を示します。これは、(文献1−1)の図5-2-15(b)を引用したもので、「中部アルプス」の「ヘルベチカ系」、「ドーフィネ系」地質グループに属する各「地質体」(ナップ)群が移動した様子を模式図として表したものです。
これによると、黄緑色で色分けされた、「中部アルプス」における、「ヘルベチカ系」、「ドーフィネ系」地質グループに属する各「地質体」(ナップ)は、「アルプス造山運動」が始まる前から現世に至る間に、北〜北西方向に、約50〜95kmも移動が起こったと推定されています。
なおこの図では、黄緑色で色分けされた数十kmサイズの「地質体」を、一つの「ナップ」としていますが、個々の「ナップ」は、細かい構造としては、多数のスラスト断層群によって多数の「ナップ群」として切り刻まれています。さらにそれらが重なり合った、「インブリケート構造」(imbricate structure/「覆瓦構造」)を構成しています。
4−3章―第(2)節 スラスト断層とナップ構造の実例
この項では、(文献1)に記載されている図や写真に基づいて、ナップ構造の実例をご紹介します。
図3は、「グラールス・スラスト」(the Glarus thrust) (注1)と呼ばれる、有名なスラスト断層の写真です。これは(文献2)より引用したものです(撮影は、 Christian Heine氏)。
写真上部のギザギザした稜線部はダークグレーの色合いですが、中腹に水平な境界線があり、それより下部はライトグレーの色合いです。この境界線が「グラールス・スラスト断層」で、ほぼ水平方向の断層であることが良く解ります。(文献1−1)の説明によると、上部のダークグレー部分は「ペルム紀」(約2.5〜2.0億年)の堆積物で、下部のライトグレー部分は、「ジュラ紀」(約2.0〜1.45億年)の堆積物層(「クインテン石灰岩」)です。さらにその下の崩れた感じの部分は、新生代(約50Ma=約0.5億年前)のフリッシュ性堆積物です。地質体の上下関係で見ると、古い「地質体」が、若い「地質体」の上に乗っていることになります。これは、スラスト断層の活動によって、構造的上位の「ペルム紀」の「地質体」が「ナップ」として水平方向へと移動して、「ジュラ紀」の「地質体」の上に定置したことを示しています。
また、この写真ではスラスト断層としては明確ではありませんが、「ジュラ系」とその下位の「新生代 フリッシュ性堆積物」との間も、時代的に逆転しているので、スラスト断層があると推定されます。
図3は、「グラールス・スラスト」(the Glarus thrust) (注1)と呼ばれる、有名なスラスト断層の写真です。これは(文献2)より引用したものです(撮影は、 Christian Heine氏)。
写真上部のギザギザした稜線部はダークグレーの色合いですが、中腹に水平な境界線があり、それより下部はライトグレーの色合いです。この境界線が「グラールス・スラスト断層」で、ほぼ水平方向の断層であることが良く解ります。(文献1−1)の説明によると、上部のダークグレー部分は「ペルム紀」(約2.5〜2.0億年)の堆積物で、下部のライトグレー部分は、「ジュラ紀」(約2.0〜1.45億年)の堆積物層(「クインテン石灰岩」)です。さらにその下の崩れた感じの部分は、新生代(約50Ma=約0.5億年前)のフリッシュ性堆積物です。地質体の上下関係で見ると、古い「地質体」が、若い「地質体」の上に乗っていることになります。これは、スラスト断層の活動によって、構造的上位の「ペルム紀」の「地質体」が「ナップ」として水平方向へと移動して、「ジュラ紀」の「地質体」の上に定置したことを示しています。
また、この写真ではスラスト断層としては明確ではありませんが、「ジュラ系」とその下位の「新生代 フリッシュ性堆積物」との間も、時代的に逆転しているので、スラスト断層があると推定されます。
4−3章―第(3)節 複雑な褶曲構造
「ヨーロッパアルプス」では、新生代の「アルプス造山運動」の最中に、「地質体」が「スラスト断層」に切られる現象や、「スラスト断層」による「ナップ」としての移動の他に、複雑な褶曲構造が発達しています。「褶曲構造」は、「ヨーロッパアルプス」のような「造山帯」に限らず、いわゆる「変動帯」には一般的で、様々な種類があります(文献3)。
ただし日本のような、山地であっても、森林や土壌で覆われている場所が多い地域では、教科書的な褶曲構造にはなかなか出会えません。一方、「ヨーロッパアルプス」では、そもそも標高が高くて森林も草すらにも覆われていない場所が多いうえに、氷期の氷河による浸食によって、表層の土壌や岩屑までもが取り除かれているため、あちこちで、褶曲構造をみることができます。
ただし日本のような、山地であっても、森林や土壌で覆われている場所が多い地域では、教科書的な褶曲構造にはなかなか出会えません。一方、「ヨーロッパアルプス」では、そもそも標高が高くて森林も草すらにも覆われていない場所が多いうえに、氷期の氷河による浸食によって、表層の土壌や岩屑までもが取り除かれているため、あちこちで、褶曲構造をみることができます。
3−A)項 「ジュラ山脈」における、褶曲構造とスラスト断層との複合的変形構造
図4は、「ジュラ山脈」に見られる、複雑な褶曲構造と、スラスト断層が複合したゾーンの、模式的な地質断面図です。「ジュラ山脈」を横断する「グレンチェンベルクトンネル」(the Grenchenberg tunnel)工事の際に作られた地質図が元となっています((文献1−1)の図5-2-4を引用)。
「ジュラ山脈」(the Jura mountains)は「ヨーロッパアルプス」から少し離れた独立した山脈ですが、「アルプス造山運動」の影響によって複雑な褶曲構造を持つことで良く知られ、(文献1)でも、かなりのページを割いて説明がなされています。
図4では、様々な色に色分けされた地層(黄色、オレンジ色系はトリアス系、水色、青色系はジュラ系、黄色は新生代モラッセ性堆積物)が、大きく上下に波打った褶曲構造を取っているとともに、赤い線で示したスラスト断層群が、その褶曲構造に参加しており、褶曲した地層群を分断してブロック化している一方で、スラスト断層自体も褶曲しているという、複雑な構造となっています。
(文献1-1)の説明によると、これはスラスト断層による変形作用(thrust tectonics)と、褶曲による変形作用(fold tectonics)の両方が作用したことを示している、とのことです。このような構造の形成は、褶曲構造が先にできてから、後にスラスト断層によって分断されたケース、逆にスラスト断層によって分断された後、褶曲構造が形成され、スラスト断層も褶曲しているケースなど、様々なケースがあるようです。
なお、教科書的な定義では、「スラスト断層」(thrust)は、水平方向に近い走向を持つ逆断層、ということになっていますが、この図4の実例のように、実際にはかならずしも水平走向とは限りません。
また、この図で一番下の基盤岩体(ベージュ色)と、それより上の褶曲した堆積物層との間には、赤い線で示された、ほぼ水平方向の断層が描かれています。これは「デコルマン(断層)」(decollment(仏、英)(日本語では、「デコルマ」、「基底スラスト断層」とも)と呼ばれる断層で、いわば「スラスト断層」群の親玉のようなものです。「デコルマン断層」から「スラスト断層」群が分岐しています(詳細は(文献4)をご覧ください)。
「ジュラ山脈」(the Jura mountains)は「ヨーロッパアルプス」から少し離れた独立した山脈ですが、「アルプス造山運動」の影響によって複雑な褶曲構造を持つことで良く知られ、(文献1)でも、かなりのページを割いて説明がなされています。
図4では、様々な色に色分けされた地層(黄色、オレンジ色系はトリアス系、水色、青色系はジュラ系、黄色は新生代モラッセ性堆積物)が、大きく上下に波打った褶曲構造を取っているとともに、赤い線で示したスラスト断層群が、その褶曲構造に参加しており、褶曲した地層群を分断してブロック化している一方で、スラスト断層自体も褶曲しているという、複雑な構造となっています。
(文献1-1)の説明によると、これはスラスト断層による変形作用(thrust tectonics)と、褶曲による変形作用(fold tectonics)の両方が作用したことを示している、とのことです。このような構造の形成は、褶曲構造が先にできてから、後にスラスト断層によって分断されたケース、逆にスラスト断層によって分断された後、褶曲構造が形成され、スラスト断層も褶曲しているケースなど、様々なケースがあるようです。
なお、教科書的な定義では、「スラスト断層」(thrust)は、水平方向に近い走向を持つ逆断層、ということになっていますが、この図4の実例のように、実際にはかならずしも水平走向とは限りません。
また、この図で一番下の基盤岩体(ベージュ色)と、それより上の褶曲した堆積物層との間には、赤い線で示された、ほぼ水平方向の断層が描かれています。これは「デコルマン(断層)」(decollment(仏、英)(日本語では、「デコルマ」、「基底スラスト断層」とも)と呼ばれる断層で、いわば「スラスト断層」群の親玉のようなものです。「デコルマン断層」から「スラスト断層」群が分岐しています(詳細は(文献4)をご覧ください)。
3−B)項 横倒しとなった褶曲構造(横臥褶曲)
褶曲構造には様々なタイプがありますが(文献3)、そのうち褶曲軸が横倒しになったものを、横臥褶曲(おうがしゅうきょく;recumbent structure)と呼びます。
図5に、そのような事例を示します。これは(文献1―1)の図5-2-7の引用です。この図の場所は、スイス西部の「ヘルベチカ系」ナップ群の一部で、上から「ヴィルドホルン」ナップ(Wildhorn nappe)、「ディアブルレ」ナップ(Diablerets nappe)、「モルクル」ナップ(Morcle nappe)の、3つのナップが積み重なったような複雑な構造となっています(「インブリケート構造」(imbricate structure)とも言える)。なお図の赤い線はスラスト断層で、ここでは、スラスト断層がこの積み重ね構造の形成に役割を果たしているとともに、褶曲構造に参加している部分も見て取れます。
どのナップも、内部は、ぐちゃぐちゃな褶曲構造となっていますが、一番下の「モルクル」ナップでは、褶曲軸がほとんど横倒しになって、いわゆる「横臥褶曲」構造を取っていることが解ります。また中間部分の「ディアブルレ」ナップは、その先端部の褶曲軸が、横向きどころか、斜め下向きになっています。
「造山運動」に伴う、「ナップ」群の内部の変形のすさまじさを表しています。
図5に、そのような事例を示します。これは(文献1―1)の図5-2-7の引用です。この図の場所は、スイス西部の「ヘルベチカ系」ナップ群の一部で、上から「ヴィルドホルン」ナップ(Wildhorn nappe)、「ディアブルレ」ナップ(Diablerets nappe)、「モルクル」ナップ(Morcle nappe)の、3つのナップが積み重なったような複雑な構造となっています(「インブリケート構造」(imbricate structure)とも言える)。なお図の赤い線はスラスト断層で、ここでは、スラスト断層がこの積み重ね構造の形成に役割を果たしているとともに、褶曲構造に参加している部分も見て取れます。
どのナップも、内部は、ぐちゃぐちゃな褶曲構造となっていますが、一番下の「モルクル」ナップでは、褶曲軸がほとんど横倒しになって、いわゆる「横臥褶曲」構造を取っていることが解ります。また中間部分の「ディアブルレ」ナップは、その先端部の褶曲軸が、横向きどころか、斜め下向きになっています。
「造山運動」に伴う、「ナップ」群の内部の変形のすさまじさを表しています。
3−C)項 基盤岩体の隆起と関連した褶曲構造
図6は、スイス中部 グリンデルワルトの近くにある山、「ヴェッターホルン」(Wetter horn)付近の地質断面図です。この図は、(文献1−1)の図5-2-9より引用しました。
以下、(文献1−1)により解説します。
この図を見ると、右手のうす紫色で描かれた「アール地塊」(Aar massif)の一部としての基盤岩体を、渦巻きのように巻き込むように、ヘルベチカ系の現地性の(autochthonous)堆積物層(図では緑色、水色系)が大きく褶曲し、褶曲軸は横倒し(recumbent)や、下向き(plunging)にまでなっていることが見て取れます。また基盤岩体自体も、大きく褶曲しているように見えます。このような「アール地塊」付近の「ヘルベチカ系」地質グループが取っている褶曲構造は、「アール地塊」が隆起したことで、その上部に乗っかっていた現地性の中生代堆積物層が、褶曲しながらズレ落ちた、と解釈できます。つまり、この褶曲構造は間接的には、「アール地塊」の隆起を表している、とも言えます
図に赤い線で描かれているのは、「アクセン・スラスト断層」(the Axen thrust)と呼ばれるスラスト断層です。この赤い線より左側の藍色の地質体は、「アクセン」ナップ(Axen nappe)と呼ばれる、スラスト断層によって運ばれてきた、異地性の地質体(ジュラ紀堆積物)です。
本来、スラスト断層は水平に近い走向を持つ逆断層として形成されますが、この図での「アクセン・スラスト断層」は、ヘルベチカ系の褶曲構造に沿っており、図の左側では、ほとんど垂直に立っています。これもまた「アール地塊」の隆起に関連しています。つまりこの断層は、最初は水平に近い走向を持つスラスト断層として形成された後に、「アール地塊」側が大きく隆起したために2次的に変形したもの、と考えられます。
図7は、筆者がグリンデルワルトの街中から撮影した、「ヴェッターホルン」の褶曲構造です。角度にして90度ほど、カーブを描いて大きく褶曲していることがわかります。この図6に示された、「アール地塊」の隆起に伴う褶曲が、街中から容易に観察できました。
以下、(文献1−1)により解説します。
この図を見ると、右手のうす紫色で描かれた「アール地塊」(Aar massif)の一部としての基盤岩体を、渦巻きのように巻き込むように、ヘルベチカ系の現地性の(autochthonous)堆積物層(図では緑色、水色系)が大きく褶曲し、褶曲軸は横倒し(recumbent)や、下向き(plunging)にまでなっていることが見て取れます。また基盤岩体自体も、大きく褶曲しているように見えます。このような「アール地塊」付近の「ヘルベチカ系」地質グループが取っている褶曲構造は、「アール地塊」が隆起したことで、その上部に乗っかっていた現地性の中生代堆積物層が、褶曲しながらズレ落ちた、と解釈できます。つまり、この褶曲構造は間接的には、「アール地塊」の隆起を表している、とも言えます
図に赤い線で描かれているのは、「アクセン・スラスト断層」(the Axen thrust)と呼ばれるスラスト断層です。この赤い線より左側の藍色の地質体は、「アクセン」ナップ(Axen nappe)と呼ばれる、スラスト断層によって運ばれてきた、異地性の地質体(ジュラ紀堆積物)です。
本来、スラスト断層は水平に近い走向を持つ逆断層として形成されますが、この図での「アクセン・スラスト断層」は、ヘルベチカ系の褶曲構造に沿っており、図の左側では、ほとんど垂直に立っています。これもまた「アール地塊」の隆起に関連しています。つまりこの断層は、最初は水平に近い走向を持つスラスト断層として形成された後に、「アール地塊」側が大きく隆起したために2次的に変形したもの、と考えられます。
図7は、筆者がグリンデルワルトの街中から撮影した、「ヴェッターホルン」の褶曲構造です。角度にして90度ほど、カーブを描いて大きく褶曲していることがわかります。この図6に示された、「アール地塊」の隆起に伴う褶曲が、街中から容易に観察できました。
【他の連載へのリンク】
この連載の各項目へのリンクがあります
一つ前の連載へのリンクです
次の連載へのリンクです
【補足説明】; この章での用語の説明
この章では色々な地質学的な用語がでてきます。教科書的な意味で使用するもののほか、説明のために、この連載で独自に使う用語もあります。それらを以下にまとめました。(文献3)も参照しました。なお以下の項で( )内の英語は、(文献1)で使用されているものです。
・「スラスト断層」(thrust);本来は、水平に近い走向を持つ逆断層のことですが、(文献1)では、低角な逆断層もスラストとしていますので、低角な逆断層も含めます。なお日本語では「スラスト」と呼びますが、この連載では、断層であることを明確にするため、あえて「スラスト断層」と呼んでいます。
・「ナップ」(nappe);スラスト断層によって切り刻まれて形成されたブロック状の「地質体」を意味する用語として使用します。同義の用語として「スラストシート」(thrust sheet)という用語もありますが、「ナップ」で統一します。なおこれは通常の定義のままですが、(文献1)では、この意味とは異なり、下記の「地質体」の意味でも、(nappe)という用語が使用されています。
・「地質体」(nappe);地質的な類似性を持ち、かつ地史も類似した一塊のブロックを意味する、広い意味を持つ用語として使用します。文脈によって、違った意味あいで使う場合もあります。「ナップ」も「地質体」の一種という扱いになります。
・「ナップ群」(nappes);多数の「ナップ」が、ある地域にまとまっているものとして使用します。
・「インブリケート構造」(imbricate structure);多数の「ナップ」が折り重なって、瓦を並べたような構造。日本語では「覆瓦構造」(ふくがこうぞう)。「ナップ群」が造る構造の一つで、同一「地質グループ」内での構造として使います。またこの連載では、以下の「ナップパイル構造」とは区別して使います。
・「地質グループ」(nappe system、complex);第3部で説明したもので、中生代のうち特に「ジュラ紀」「白亜紀」にかけ、類似した地質環境で、そのため類似した地質体が形成されたゾーンを、(文献1)では「地質区」(realm)と呼んでいます。
それぞれの「地質区」で形成された地質体のグループを、「地質グループ」と呼んで使用します。それぞれの「地質グループ」は、多数の「地質体」から構成されています。
また「ヨーロッパアルプス」における主な「地質グループ」としては、以下5つがあります。
「ヘルベチカ系」(Hervetic)、「ドーフィネ系」(Dauphnois)、「ペニン系」(Penninic)、「オーストロアルパイン系」(Austro-alpine)、「サウスアルパイン系」(South-alpine)
・「ナップパイル構造」(nappe pile);この連載では独自の定義として、複数の「地質グループ」が、更に、座布団を重ねたように積み重なっているもの、として使用します。本来の(nappe pile)の意味は、「ナップ」が多数折り重なったものという意味で、(文献1)でもその定義として使用されているようですが、ここではそういう構造体は、「ナップ群」と呼ぶことし、「ナップパイル構造」という用語と区別します。これはあくまで、説明を解りやすくするための方便です。
・褶曲(fold);地質体(地層)が、応力によって変形し、波打ったような構造全般。
・横臥褶曲(おうがしゅうきょく;recumbent fold);横倒しになったような褶曲構造、褶曲の軸がほとんど水平方向になっているもの。
・「スラスト断層」(thrust);本来は、水平に近い走向を持つ逆断層のことですが、(文献1)では、低角な逆断層もスラストとしていますので、低角な逆断層も含めます。なお日本語では「スラスト」と呼びますが、この連載では、断層であることを明確にするため、あえて「スラスト断層」と呼んでいます。
・「ナップ」(nappe);スラスト断層によって切り刻まれて形成されたブロック状の「地質体」を意味する用語として使用します。同義の用語として「スラストシート」(thrust sheet)という用語もありますが、「ナップ」で統一します。なおこれは通常の定義のままですが、(文献1)では、この意味とは異なり、下記の「地質体」の意味でも、(nappe)という用語が使用されています。
・「地質体」(nappe);地質的な類似性を持ち、かつ地史も類似した一塊のブロックを意味する、広い意味を持つ用語として使用します。文脈によって、違った意味あいで使う場合もあります。「ナップ」も「地質体」の一種という扱いになります。
・「ナップ群」(nappes);多数の「ナップ」が、ある地域にまとまっているものとして使用します。
・「インブリケート構造」(imbricate structure);多数の「ナップ」が折り重なって、瓦を並べたような構造。日本語では「覆瓦構造」(ふくがこうぞう)。「ナップ群」が造る構造の一つで、同一「地質グループ」内での構造として使います。またこの連載では、以下の「ナップパイル構造」とは区別して使います。
・「地質グループ」(nappe system、complex);第3部で説明したもので、中生代のうち特に「ジュラ紀」「白亜紀」にかけ、類似した地質環境で、そのため類似した地質体が形成されたゾーンを、(文献1)では「地質区」(realm)と呼んでいます。
それぞれの「地質区」で形成された地質体のグループを、「地質グループ」と呼んで使用します。それぞれの「地質グループ」は、多数の「地質体」から構成されています。
また「ヨーロッパアルプス」における主な「地質グループ」としては、以下5つがあります。
「ヘルベチカ系」(Hervetic)、「ドーフィネ系」(Dauphnois)、「ペニン系」(Penninic)、「オーストロアルパイン系」(Austro-alpine)、「サウスアルパイン系」(South-alpine)
・「ナップパイル構造」(nappe pile);この連載では独自の定義として、複数の「地質グループ」が、更に、座布団を重ねたように積み重なっているもの、として使用します。本来の(nappe pile)の意味は、「ナップ」が多数折り重なったものという意味で、(文献1)でもその定義として使用されているようですが、ここではそういう構造体は、「ナップ群」と呼ぶことし、「ナップパイル構造」という用語と区別します。これはあくまで、説明を解りやすくするための方便です。
・褶曲(fold);地質体(地層)が、応力によって変形し、波打ったような構造全般。
・横臥褶曲(おうがしゅうきょく;recumbent fold);横倒しになったような褶曲構造、褶曲の軸がほとんど水平方向になっているもの。
【注釈の項】
注1)「グラールス」、「グラールス・スラスト断層」について
「グラールス」(Glarus)は、スイス中東部の州の名前です。
「グラールス・スラスト断層」は、古くから有名だったらしく、(文献1−1)や(文献2)では、19世紀初頭に、この場所を描いた絵画も載せられています。またこの場所は、2008年にユネスコの「世界自然遺産」に選ばれています。なお「グラールス・スラスト断層」の露頭は、この写真の場所だけでなく、スイスの「グラールス州」のあちこちに露頭があるそうです。(文献2)もご参照ください。
「グラールス」(Glarus)は、スイス中東部の州の名前です。
「グラールス・スラスト断層」は、古くから有名だったらしく、(文献1−1)や(文献2)では、19世紀初頭に、この場所を描いた絵画も載せられています。またこの場所は、2008年にユネスコの「世界自然遺産」に選ばれています。なお「グラールス・スラスト断層」の露頭は、この写真の場所だけでなく、スイスの「グラールス州」のあちこちに露頭があるそうです。(文献2)もご参照ください。
【参考文献】
(文献1) O. A. Pfiffer 著 “Geology of the Alps”, 2nd edition ,Wiley Blackball社刊,
(2014); (原著はドイツ語版で、2014年にドイツの出版社刊)
(文献1−1); (文献1)のうち、第5部(tectonic structure of the Alps)の項
(文献2) ウイキペディア英語版の、「グラールス・スラスト」(Glarus thrust)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Glarus_thrust
(2025年8月 閲覧)
(文献3) ウイキペディア英語版の、「褶曲」(fold(geology))の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Fold_(geology)
(2025年8月 閲覧)
(文献4) ウイキペディア英語版の、「デコルマン」(Décollement)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9collement
(2025年8月 閲覧)
(文献5) 地学団体研究会 編 「新版・地学事典」 平凡社 刊(1996)
のうち、「スラスト」、「ナップ」、「デコルマン」、
「覆瓦構造」、「褶曲」、「横臥褶曲」などの項
(2014); (原著はドイツ語版で、2014年にドイツの出版社刊)
(文献1−1); (文献1)のうち、第5部(tectonic structure of the Alps)の項
(文献2) ウイキペディア英語版の、「グラールス・スラスト」(Glarus thrust)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Glarus_thrust
(2025年8月 閲覧)
(文献3) ウイキペディア英語版の、「褶曲」(fold(geology))の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Fold_(geology)
(2025年8月 閲覧)
(文献4) ウイキペディア英語版の、「デコルマン」(Décollement)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9collement
(2025年8月 閲覧)
(文献5) 地学団体研究会 編 「新版・地学事典」 平凡社 刊(1996)
のうち、「スラスト」、「ナップ」、「デコルマン」、
「覆瓦構造」、「褶曲」、「横臥褶曲」などの項
【書記事項】
初版リリース;2025年8月31日
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
ベルクハイルさんの記事一覧
-
「ヨーロッパアルプスの地質学」;5−2章 「ヴァリス山群」の地質 (その2、新);「モンテローザ」、「ブライトホルン」、及び「ゴルナーグラート」付近の地質 3 更新日:2025年10月21日
-
「ヨーロッパアルプスの地質学」;5−2章 「ヴァリス山群」の地質(その3);ヴァイスホルンとその周辺 3 更新日:2025年10月23日
-
 「ヨーロッパアルプスの地質学」;5−2章 「ヴァリス山群」の地質(その1(改));ヴァリス山群の概要、及び「マッターホルン」の地質
4
更新日:2025年10月20日
「ヨーロッパアルプスの地質学」;5−2章 「ヴァリス山群」の地質(その1(改));ヴァリス山群の概要、及び「マッターホルン」の地質
4
更新日:2025年10月20日
※この記事はヤマレコの「ヤマノート」機能を利用して作られています。
どなたでも、山に関する知識や技術などのノウハウを簡単に残して共有できます。
ぜひご協力ください!

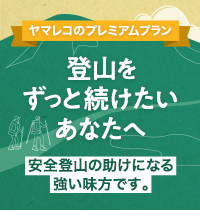





コメントを編集
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する