(はじめに)
この5−2章「ヴァリス山群の地質」は、説明したい山々が多いので、複数回に分けて連載しています。
前回の投稿;「ヴァリス山群の地質」(その1)では、ヴァリス州最大の観光拠点といえる「ツェルマット」(Zermatt)の南側にそびえる「マッターホルン」までを、(その2)では、「モンテローザ」などの高峰群や、「ゴルナーグラート」(Gornergrat)付近の地質について説明しました。
この回(その3)では、「ツェルマット」のあるU字谷;「マッタ―タール」(Mattertal)の西側、「マッタ―タール」と並走して南北に並んでいる4000m級の高峰のうち、「ヴァイスホルン」(Weisshorn;4505m)、「ツィナールロートホルン」(Zinalrothorn;4221m)、「オーバーガーベルホルン」(Obergabelhorn;4063m)という3つの4000m級の高峰とその周辺について、その地質を説明します。注1)
なお、以下では、これらの山々を、説明のために「ヴァイスホルン山群」と仮称します。これはあくまでも、ここでの説明用の仮称で、オーソライズされた用語ではありません。
なお地質図としては、スイスのオンライン地質図のうち、より詳しい(文献2A)の地質図を主に元とし、(文献2B)の地質図は参照程度にしました。注2)
この「ヴァイスホルン山群」(仮称)の山々も、前回「ヴァリス山群の地質」(その1)の投稿で説明した、「マッターホルン」、「ツェルマットとその周辺」などの地質構成と同様に、複数の「地塊」 注5)がせめぎあっている、複雑な地質構造となっています。
具体的には、「ダンブランシュ・ナップ」(Dent Blanche nappe)地塊、「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」(Siviez-Mischabel nappe)地塊、「ツァテ・ナップ」(Tsate nappe)地塊、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」(Zermatt Saas-Fee zone)など、いくつもの「地塊」群が、戦国時代さながらに、自らの領域を持っています(文献2A)、(文献3)。
ここで説明する「ヴァイスホルン山群」(仮称)の地理、位置関係は、添付の図1(「ヴァリス山群」西部の広域地形図)、図3(ツェルマット北西部の地形図)もご参照ください。
また、テクトニクス的にみた、各「地塊」の位置関係は、添付の図2(「ヴァリス山群」西部の広域テクトニックマップ)、図4(ツエルマット周辺のテクトニックマップ)もご参照ください。
前回の投稿;「ヴァリス山群の地質」(その1)では、ヴァリス州最大の観光拠点といえる「ツェルマット」(Zermatt)の南側にそびえる「マッターホルン」までを、(その2)では、「モンテローザ」などの高峰群や、「ゴルナーグラート」(Gornergrat)付近の地質について説明しました。
この回(その3)では、「ツェルマット」のあるU字谷;「マッタ―タール」(Mattertal)の西側、「マッタ―タール」と並走して南北に並んでいる4000m級の高峰のうち、「ヴァイスホルン」(Weisshorn;4505m)、「ツィナールロートホルン」(Zinalrothorn;4221m)、「オーバーガーベルホルン」(Obergabelhorn;4063m)という3つの4000m級の高峰とその周辺について、その地質を説明します。注1)
なお、以下では、これらの山々を、説明のために「ヴァイスホルン山群」と仮称します。これはあくまでも、ここでの説明用の仮称で、オーソライズされた用語ではありません。
なお地質図としては、スイスのオンライン地質図のうち、より詳しい(文献2A)の地質図を主に元とし、(文献2B)の地質図は参照程度にしました。注2)
この「ヴァイスホルン山群」(仮称)の山々も、前回「ヴァリス山群の地質」(その1)の投稿で説明した、「マッターホルン」、「ツェルマットとその周辺」などの地質構成と同様に、複数の「地塊」 注5)がせめぎあっている、複雑な地質構造となっています。
具体的には、「ダンブランシュ・ナップ」(Dent Blanche nappe)地塊、「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」(Siviez-Mischabel nappe)地塊、「ツァテ・ナップ」(Tsate nappe)地塊、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」(Zermatt Saas-Fee zone)など、いくつもの「地塊」群が、戦国時代さながらに、自らの領域を持っています(文献2A)、(文献3)。
ここで説明する「ヴァイスホルン山群」(仮称)の地理、位置関係は、添付の図1(「ヴァリス山群」西部の広域地形図)、図3(ツェルマット北西部の地形図)もご参照ください。
また、テクトニクス的にみた、各「地塊」の位置関係は、添付の図2(「ヴァリス山群」西部の広域テクトニックマップ)、図4(ツエルマット周辺のテクトニックマップ)もご参照ください。
5−2章―(6)節 「ヴァイスホルン」の地質
「ヴァイスホルン」(Weisshorn;4505m)は、「ツェルマット」のある谷;「マッタ―タール」(Mattertal)の西側に、南北に並ぶ山なみのうちの一つで、ここで言う「ヴァイスホルン山群」のうち最も標高が高い峰です(かつ「マッターホルン」よりも少しだけ高い)。(文献14)
「ヴァイスホルン」は、美しい三角錐の形状をしており、特に雪で覆われている時の姿は、(Weiss horn)の名前の通り、気高き貴婦人のような姿です(※ ドイツ語の “weiss” は、英語の”white” と同義なので、「白き峰」という意味)。
(文献9)によると、初登頂者の一人、J.ティンダルは、その著書にて「ヴァイスホルンこそは、全ての山々をその脚下に踏み従える総帥である」と述べたそうです。また(文献10)では「アルプス中で最も美しい山」と讃えています。添付の(写真1)、(写真2)もご参照ください。
一方でこの山は、ロープウエイなどの便利な交通手段がなく、麓となる「マッタ―タール」の谷にある「ランダ」(Randa)という集落から、標高差 約3000mを全て自分の足で登り降りする体力が必要な山であり、かつ上部の三角錐部分は、険しい岩稜登攀となるため、「マッターホルン」よりも難易度が高いと言われている山です(文献9)、(文献10)。
さて「ヴァイスホルン」の地質ですが、まず、「ヴァイスホルン」とその周辺における、各「地塊」の分布状況を確認してみます。
地質図(文献2A)の地質図レイヤー(図5)や、(文献2A)のテクトニックレイヤー(図4)、及び(文献3)を見てみると、「ヴァイスホルン」山頂や西側、及び東面の上部あたりは、「ダンブランシュ・ナップ」(Dent Blanche nappe)(地塊)(文献18)に属しています(図5では青色の線より西側)。
一方、「マッタ―タール」から「ヴァイスホルン」の下半分にかけては、「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」(Siviez-Mischabel nappe)と呼ばれる、別の「地塊」に属するゾーンです(図5では赤い線より東側)。
その間は、両方の「地塊」に挟まれ、狭い範囲にいろいろな地質体が分布している複雑なゾーンです。このゾーンを以下、説明用に「中間ゾーン」と仮称します。
以下、登山口となる「ランダ」(Randa;標高 約1400m)から、途中の「ヴァイスホルン小屋」を経由し、東稜を伝って「ヴァイスホルン」の山頂に至るルートぞいに、地質構成を説明します。(図5では、紫色のラインで示しています)
「ランダ」から「ヴァイスホルン小屋」(Weisshorn hutte;標高 約2900m)までは、地質図(文献2A)でみると、「片麻岩」類(Gneis(独))が多く、所々に変成岩の一種「角閃岩」(Amphiborit(独))が分布しています。この一帯は前述のとおり「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」とよばれる「地塊」に属しています。
なお「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」という「地塊」については、この連載のうち、「補足説明1」の項で説明していますので、ご参照ください。
さて、「ヴァイスホルン小屋」(約2900m)から、東稜(Ostgrat)の取りつきにあたる標高 約3500mあたりまでは、色々な小岩体が入り混じっている複雑なゾーンです(仮称「中間ゾーン」)。
地質図(文献2A)を詳しく見ると、この「中間ゾーン」には、以下の地質体が分布しています。
1);「結晶片岩」類(Schiefer(独)));(Col de Chassoure層、中部ペニン系)、
2);「クオーツアイト」(Quarztit(独))など;(Bruneggjoch層、中部ペニン系)、
3);(変成)「石灰岩」類(Kalkstein, Marmor(独));(Klippen Deckeグループ、ジュラ紀)、
4);「オフィオライト岩体」(Ophiolith(独))(蛇紋岩、変成ハンレイ岩、変成玄武岩);(上部ペニン系)。注4)
(文献2A)のテクトニックレイヤーや、(文献5)のテクトニックマップを見ると、この「中間ゾーン」を構成している各種地質体は、「ツァテ・ナップ」(Tsate nappe)という「地塊」に属するものと、「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」のうち、被覆層(cover nappes)に属するもの、2系統が混在しているようです。
このうち「ツァテ・ナップ」については、この連載のうち、5−2章(その1)の項の「補足説明」の項で、少し詳しく解説していますので、ご参照ください。
この「中間ゾーン」に分布する各種地質体の帰属は明確ではありませんが、このうち「石灰岩」類は、地質図(文献2A)では、「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」(の被覆層)に属している、と書いてあります。また「オフィオライト岩体」はおそらく「ツァテ・ナップ」に属するものです。
さて話を戻します。東稜の取りつき、標高 約3500mより頂上(4505m)までは、テクトニクス的には「ダンブランシュ・ナップ」(地塊)に属します(図5)。
ここでの岩石は、地質図(文献2A)によると主に「片麻岩」類(Gneis(独))で、「雲母片岩」(glimmer-scheifer(独))も含まれているようです。また地質グループとしては「ダンブランシュ・ナップ」のうちの「アローラユニット」(Arolla unit)に属します。
この、標高 約3500mにある地質境界線は、スラスト断層によってできた、「ダンブランシュ・ナップ」の下を区切る重要な地質境界線です(文献5)、(文献6)。
この章の「マッターホルン」の項でも出てきましたが、この「アローラユニット」に属する変成岩類は、「マッターホルン」のピラミッド状の部分を形成している岩体でした。
「ヴァイスホルン」と「マッターホルン」とは直線距離で約15kmは離れていますが、「マッターホルン」のピラミッド状部分(四角錐)と、「ヴァイスホルン」の三角錐部分は、同じ岩石類でできている、ということになります。
なお「ダンブランシュ・ナップ」という「地塊」は、この回の連載で何回も出てきますが、説明が簡単ではないので、次の連載で詳しく説明する予定です。
さて、「ヴァイスホルン」のうち、東面以外の部分を、地質図(文献2A)で確認します。
この山も「マッターホルン」と地質構成はよく似ていて、前述の東面側は複雑ですが、西面、北面、南面は比較的単純な地質構造となっており、「ダンブランシュ・ナップ」(の「アローラユニット」)に属する「片麻岩」類、「結晶片岩類」が多くを占めています。
ただし西面だけは、(変成)「ハンレイ岩」(Gabbro(独))、(変成)「閃緑岩」(Diorit(独))などからなる、複合深成岩体が分布しています。この複合深成岩体は、西面の約4000mから約2500m辺りまで分布しています。添付の図5もご参照ください。
この複合深成岩体の形成時代は、(文献2A)によると原生代〜古生代となっていますが、(文献7)によると、「ダンブランシュ・ナップ」に点在する「(変成)ハンレイ岩体」は、「ペルム紀」に形成された深成岩体とされており、ここの複合深成岩体も「ペルム紀」に形成されたと思われます。
「ヴァイスホルン」は、美しい三角錐の形状をしており、特に雪で覆われている時の姿は、(Weiss horn)の名前の通り、気高き貴婦人のような姿です(※ ドイツ語の “weiss” は、英語の”white” と同義なので、「白き峰」という意味)。
(文献9)によると、初登頂者の一人、J.ティンダルは、その著書にて「ヴァイスホルンこそは、全ての山々をその脚下に踏み従える総帥である」と述べたそうです。また(文献10)では「アルプス中で最も美しい山」と讃えています。添付の(写真1)、(写真2)もご参照ください。
一方でこの山は、ロープウエイなどの便利な交通手段がなく、麓となる「マッタ―タール」の谷にある「ランダ」(Randa)という集落から、標高差 約3000mを全て自分の足で登り降りする体力が必要な山であり、かつ上部の三角錐部分は、険しい岩稜登攀となるため、「マッターホルン」よりも難易度が高いと言われている山です(文献9)、(文献10)。
さて「ヴァイスホルン」の地質ですが、まず、「ヴァイスホルン」とその周辺における、各「地塊」の分布状況を確認してみます。
地質図(文献2A)の地質図レイヤー(図5)や、(文献2A)のテクトニックレイヤー(図4)、及び(文献3)を見てみると、「ヴァイスホルン」山頂や西側、及び東面の上部あたりは、「ダンブランシュ・ナップ」(Dent Blanche nappe)(地塊)(文献18)に属しています(図5では青色の線より西側)。
一方、「マッタ―タール」から「ヴァイスホルン」の下半分にかけては、「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」(Siviez-Mischabel nappe)と呼ばれる、別の「地塊」に属するゾーンです(図5では赤い線より東側)。
その間は、両方の「地塊」に挟まれ、狭い範囲にいろいろな地質体が分布している複雑なゾーンです。このゾーンを以下、説明用に「中間ゾーン」と仮称します。
以下、登山口となる「ランダ」(Randa;標高 約1400m)から、途中の「ヴァイスホルン小屋」を経由し、東稜を伝って「ヴァイスホルン」の山頂に至るルートぞいに、地質構成を説明します。(図5では、紫色のラインで示しています)
「ランダ」から「ヴァイスホルン小屋」(Weisshorn hutte;標高 約2900m)までは、地質図(文献2A)でみると、「片麻岩」類(Gneis(独))が多く、所々に変成岩の一種「角閃岩」(Amphiborit(独))が分布しています。この一帯は前述のとおり「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」とよばれる「地塊」に属しています。
なお「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」という「地塊」については、この連載のうち、「補足説明1」の項で説明していますので、ご参照ください。
さて、「ヴァイスホルン小屋」(約2900m)から、東稜(Ostgrat)の取りつきにあたる標高 約3500mあたりまでは、色々な小岩体が入り混じっている複雑なゾーンです(仮称「中間ゾーン」)。
地質図(文献2A)を詳しく見ると、この「中間ゾーン」には、以下の地質体が分布しています。
1);「結晶片岩」類(Schiefer(独)));(Col de Chassoure層、中部ペニン系)、
2);「クオーツアイト」(Quarztit(独))など;(Bruneggjoch層、中部ペニン系)、
3);(変成)「石灰岩」類(Kalkstein, Marmor(独));(Klippen Deckeグループ、ジュラ紀)、
4);「オフィオライト岩体」(Ophiolith(独))(蛇紋岩、変成ハンレイ岩、変成玄武岩);(上部ペニン系)。注4)
(文献2A)のテクトニックレイヤーや、(文献5)のテクトニックマップを見ると、この「中間ゾーン」を構成している各種地質体は、「ツァテ・ナップ」(Tsate nappe)という「地塊」に属するものと、「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」のうち、被覆層(cover nappes)に属するもの、2系統が混在しているようです。
このうち「ツァテ・ナップ」については、この連載のうち、5−2章(その1)の項の「補足説明」の項で、少し詳しく解説していますので、ご参照ください。
この「中間ゾーン」に分布する各種地質体の帰属は明確ではありませんが、このうち「石灰岩」類は、地質図(文献2A)では、「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」(の被覆層)に属している、と書いてあります。また「オフィオライト岩体」はおそらく「ツァテ・ナップ」に属するものです。
さて話を戻します。東稜の取りつき、標高 約3500mより頂上(4505m)までは、テクトニクス的には「ダンブランシュ・ナップ」(地塊)に属します(図5)。
ここでの岩石は、地質図(文献2A)によると主に「片麻岩」類(Gneis(独))で、「雲母片岩」(glimmer-scheifer(独))も含まれているようです。また地質グループとしては「ダンブランシュ・ナップ」のうちの「アローラユニット」(Arolla unit)に属します。
この、標高 約3500mにある地質境界線は、スラスト断層によってできた、「ダンブランシュ・ナップ」の下を区切る重要な地質境界線です(文献5)、(文献6)。
この章の「マッターホルン」の項でも出てきましたが、この「アローラユニット」に属する変成岩類は、「マッターホルン」のピラミッド状の部分を形成している岩体でした。
「ヴァイスホルン」と「マッターホルン」とは直線距離で約15kmは離れていますが、「マッターホルン」のピラミッド状部分(四角錐)と、「ヴァイスホルン」の三角錐部分は、同じ岩石類でできている、ということになります。
なお「ダンブランシュ・ナップ」という「地塊」は、この回の連載で何回も出てきますが、説明が簡単ではないので、次の連載で詳しく説明する予定です。
さて、「ヴァイスホルン」のうち、東面以外の部分を、地質図(文献2A)で確認します。
この山も「マッターホルン」と地質構成はよく似ていて、前述の東面側は複雑ですが、西面、北面、南面は比較的単純な地質構造となっており、「ダンブランシュ・ナップ」(の「アローラユニット」)に属する「片麻岩」類、「結晶片岩類」が多くを占めています。
ただし西面だけは、(変成)「ハンレイ岩」(Gabbro(独))、(変成)「閃緑岩」(Diorit(独))などからなる、複合深成岩体が分布しています。この複合深成岩体は、西面の約4000mから約2500m辺りまで分布しています。添付の図5もご参照ください。
この複合深成岩体の形成時代は、(文献2A)によると原生代〜古生代となっていますが、(文献7)によると、「ダンブランシュ・ナップ」に点在する「(変成)ハンレイ岩体」は、「ペルム紀」に形成された深成岩体とされており、ここの複合深成岩体も「ペルム紀」に形成されたと思われます。
5−2章―(7)節 「ツィナールロートホルン」の地質
「ツィナールロートホルン」(Zinalrothorn;4221m)(文献15)は、ここでいう「ヴァイスホルン山群」に属し、「ヴァイスホルン」の南 約5kmにある4000m級の高峰です。
この一帯は「マッターホルン」と「ヴァイスホルン」という、高くて有名な山があるため、さほど有名ではありませんが、「ツェルマット」の東側の展望台「ゴルナーグラート」(gornergrat)や「スネガ」(sunnegga)付近から見ると、中腹に氷河をまとって、その上に尖峰が立っているような、特徴的な姿をしているのが望めます。
添付の(写真4)、(写真5)もご参照ください。
(文献9)、(文献10)、(文献15)によると、この山の名前のうち「ツィナール」(“Zinal”)とは、この山の西側、「ツィナール谷」(Val de Zinal(仏))にある小さな集落の名前です。初登頂は西の「ツェナール」側から行われましたが、現在は東側の中腹に山小屋(ロートホルン小屋;Rothorn Hutte、約3200m)があるという利便性により、東側の「ツェルマット」側から登られることが多いようです(文献9)、(文献10)。
また「ロート」(“rot”)はドイツ語で、赤い色(英語の“red”に相当)を意味します。写真や実物を見ると、特に赤っぽい感じではありませんが、朝日、夕日を浴びて赤く染まる(モルゲンロート/アーベントロート)のかも知れません。
さて「ツィナールロートホルン」の地質ですが、テクトニクス的には、前述の「ヴァイスホルン」とよく似ています。
図4,図6に示すように、山頂部、西面、北面、南面のすべて、および東面の中腹部(標高 約3000m付近まで)は、「ダンブランシュ・ナップ」(Dent Blanche nappe)(地塊)に属しています。この領域では、地質図(文献2A)によると「片麻岩」類(Gneis(独))が多く、一部には「結晶片岩」類(主に「雲母片岩」(glimmer schiefer(独)))を含むと書かれています。
(文献2A)を細かく見ると、「片麻岩」類には数種類あり、山頂部、西面、北面、南面の「片麻岩」類は、「ペルム紀」の深成岩体が変成作用を受けてできた、(“Arolla Ortho-gneises”)と呼ばれる「片麻岩」です。一方、東面の中腹部の「片麻岩」は、「ヴァイスホルン」山体を構成しているものと同種の「片麻岩」類が分布しています。この2種類の「片麻岩」類は、どちらも「ダンブランシュ・ナップ」(地塊)のうち、「アローラユニット」(Arolla unit)に属しています。
東側のうち標高 約2800mあたりより下部、山麓部までは、「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」(Siviez Mischabel Decke(独))(地塊)に属しています。この領域には、「ヴァイスホルン」の東面と同様に、「古い片麻岩」類と「角閃岩」(Amphiborit(独))が分布しています。形成(変成)年代は、原生代〜古生代となっています。
さて、この山の地質で特徴的な点は、ツェルマットの街に面した南東面、標高 約3000m辺りから、ツェルマットの街付近(標高 約1600m)までの「マッタ―タール」西側斜面に、色々な地質体が散在していて、非常に複雑なゾーンとなっている点です(以下、説明のため「南東ゾーン」と仮称します)。
地質図(文献2A)でこの「南東ゾーン」の地質を詳しく見ると、以下のような地質体が、大小さまざまな岩体として散在しています。(※ ( )内は、(文献2A)による説明)
1);(マイロナイト化した)「ハンレイ岩」(Gabbro;mylonitisch(独)、
ダンブランシュ・ナップ系)
2);「石灰岩」類(Kalkstein(独)、シヴィエ・ミシャベル・ナップ系)
3);「結晶質石灰岩(大理石)」(Marmor(独)、中部ペニン系)
4);「クオーツアイト」(Quarzit(独)、中部ペニン系)
5);「(変成)礫岩」(Konglomerat(独)、中部ペニン系)
6);「オフィオライト岩体」(Ophiolith(独)、ツェルマット・ザースフェー・ゾーン系)
7);「結晶片岩」類(Kalkig-Schiefer、Tonig-Schiefer(独)、上部ペニン系)
この「南東ゾーン」のテクトニクス的な帰属は、地質図(文献2A)に加え、(文献5)などによると、「ダンブランシュ・ナップ」(地塊)、「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」(地塊)、「ツァテ・ナップ」(地塊)に加え、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」(Zermatt Saas-Fee zone)(地塊)、「シムズ・ブランシュ・ナップ」(地塊)(Cimes Blanche nappe)、「フリリホルン・ナップ」(地塊)(Frilihorn nappe)といった「地塊」に帰属するものもあるようで、非常に複雑です。
添付の(写真4)には、この「南東ゾーン」が写っていますので、ご参照ください。「マッタ―タール」の西側斜面に、層状の構造が見られます。また(文献5)には、この「南東ゾーン」の地質構造を解釈したものがありましたので、図7として添付しています。これは(文献5)の(Fig.11)を引用したものです。
この図7と(写真4)とは、同じ「スネガ」(sunnegga)という地点から写したもので、照合が可能です。
(写真4)に見える、マッタ―タール西側斜面に見える層状構造部分のほとんどは、「ツァテ・ナップ」に属する「石灰質片岩」(calc-schist)のようです。
この一帯は「マッターホルン」と「ヴァイスホルン」という、高くて有名な山があるため、さほど有名ではありませんが、「ツェルマット」の東側の展望台「ゴルナーグラート」(gornergrat)や「スネガ」(sunnegga)付近から見ると、中腹に氷河をまとって、その上に尖峰が立っているような、特徴的な姿をしているのが望めます。
添付の(写真4)、(写真5)もご参照ください。
(文献9)、(文献10)、(文献15)によると、この山の名前のうち「ツィナール」(“Zinal”)とは、この山の西側、「ツィナール谷」(Val de Zinal(仏))にある小さな集落の名前です。初登頂は西の「ツェナール」側から行われましたが、現在は東側の中腹に山小屋(ロートホルン小屋;Rothorn Hutte、約3200m)があるという利便性により、東側の「ツェルマット」側から登られることが多いようです(文献9)、(文献10)。
また「ロート」(“rot”)はドイツ語で、赤い色(英語の“red”に相当)を意味します。写真や実物を見ると、特に赤っぽい感じではありませんが、朝日、夕日を浴びて赤く染まる(モルゲンロート/アーベントロート)のかも知れません。
さて「ツィナールロートホルン」の地質ですが、テクトニクス的には、前述の「ヴァイスホルン」とよく似ています。
図4,図6に示すように、山頂部、西面、北面、南面のすべて、および東面の中腹部(標高 約3000m付近まで)は、「ダンブランシュ・ナップ」(Dent Blanche nappe)(地塊)に属しています。この領域では、地質図(文献2A)によると「片麻岩」類(Gneis(独))が多く、一部には「結晶片岩」類(主に「雲母片岩」(glimmer schiefer(独)))を含むと書かれています。
(文献2A)を細かく見ると、「片麻岩」類には数種類あり、山頂部、西面、北面、南面の「片麻岩」類は、「ペルム紀」の深成岩体が変成作用を受けてできた、(“Arolla Ortho-gneises”)と呼ばれる「片麻岩」です。一方、東面の中腹部の「片麻岩」は、「ヴァイスホルン」山体を構成しているものと同種の「片麻岩」類が分布しています。この2種類の「片麻岩」類は、どちらも「ダンブランシュ・ナップ」(地塊)のうち、「アローラユニット」(Arolla unit)に属しています。
東側のうち標高 約2800mあたりより下部、山麓部までは、「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」(Siviez Mischabel Decke(独))(地塊)に属しています。この領域には、「ヴァイスホルン」の東面と同様に、「古い片麻岩」類と「角閃岩」(Amphiborit(独))が分布しています。形成(変成)年代は、原生代〜古生代となっています。
さて、この山の地質で特徴的な点は、ツェルマットの街に面した南東面、標高 約3000m辺りから、ツェルマットの街付近(標高 約1600m)までの「マッタ―タール」西側斜面に、色々な地質体が散在していて、非常に複雑なゾーンとなっている点です(以下、説明のため「南東ゾーン」と仮称します)。
地質図(文献2A)でこの「南東ゾーン」の地質を詳しく見ると、以下のような地質体が、大小さまざまな岩体として散在しています。(※ ( )内は、(文献2A)による説明)
1);(マイロナイト化した)「ハンレイ岩」(Gabbro;mylonitisch(独)、
ダンブランシュ・ナップ系)
2);「石灰岩」類(Kalkstein(独)、シヴィエ・ミシャベル・ナップ系)
3);「結晶質石灰岩(大理石)」(Marmor(独)、中部ペニン系)
4);「クオーツアイト」(Quarzit(独)、中部ペニン系)
5);「(変成)礫岩」(Konglomerat(独)、中部ペニン系)
6);「オフィオライト岩体」(Ophiolith(独)、ツェルマット・ザースフェー・ゾーン系)
7);「結晶片岩」類(Kalkig-Schiefer、Tonig-Schiefer(独)、上部ペニン系)
この「南東ゾーン」のテクトニクス的な帰属は、地質図(文献2A)に加え、(文献5)などによると、「ダンブランシュ・ナップ」(地塊)、「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」(地塊)、「ツァテ・ナップ」(地塊)に加え、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」(Zermatt Saas-Fee zone)(地塊)、「シムズ・ブランシュ・ナップ」(地塊)(Cimes Blanche nappe)、「フリリホルン・ナップ」(地塊)(Frilihorn nappe)といった「地塊」に帰属するものもあるようで、非常に複雑です。
添付の(写真4)には、この「南東ゾーン」が写っていますので、ご参照ください。「マッタ―タール」の西側斜面に、層状の構造が見られます。また(文献5)には、この「南東ゾーン」の地質構造を解釈したものがありましたので、図7として添付しています。これは(文献5)の(Fig.11)を引用したものです。
この図7と(写真4)とは、同じ「スネガ」(sunnegga)という地点から写したもので、照合が可能です。
(写真4)に見える、マッタ―タール西側斜面に見える層状構造部分のほとんどは、「ツァテ・ナップ」に属する「石灰質片岩」(calc-schist)のようです。
5−2章―(8)節 「オーバーガーベルホルン」の地質
「オーバーガーベルホルン」(Ober Gabelhorn;4063m)(文献16)は、ここでいう「ヴァイスホルン山群」のうち、前述の「ツィナールロートホルン」(Zinalrothorn)から南に約4km、「マッターホルン」(Mattehorn)からは、間に氷河を挟んで、北へ約6kmの位置にある4000m峰です(図1,図3もご参照ください)。
この山は、標高が4000mを少し超える程度ですが、前述の「ツィナールロートホルン」と同じく、「ツェルマット」の東側の展望台「ゴルナーグラート」付近からは、わりと目立つ峰です。東側中腹には、大きなカール状の氷河(Gabelhorn glacier)を持っており、周辺にいくつもの衛星峰を従えた特徴的な姿をしており、標高以上にスケール感の大きな高峰という印象です。 (写真4)、(写真6)もご参照ください。また西の「ツィナール」側は氷雪をまとった姿で、東側の姿とはだいぶ違うそうです(文献9)。
「オーバーガーベルホルン」の(“Ober”)とは、ドイツ語で「上」を意味し、英語の(“upper”)にほぼ対応する言葉です。また(“Gabel”)はドイツ語で「熊手」を意味し、実際は、「熊手状」の農機具の名前だそうで、東側の山容から付けられた名前と推定されています(文献9)。
この山は、多数の衛星峰を擁しており、東側には「ミッテラーガーベルホルン」(Mitteler Gaberhorn;3685m)、「ウンターガーベルホルン」(Unter Gabelhorn;3391m)があります。また北東には、山頂部に雪の帽子をかぶって特徴的な「ヴェレンクッペ」(Wellenkuppe;3900m)があり、主峰と並ぶ姿は双耳峰のようにも見えます。他には、西側には「モン・デュラン」(Mont Durand)あるいは「アルベールホルン」(Arbelhorn)(3712m)と呼ばれるピークがあります。これらの衛星峰も含めて、大きな山塊を作っています。
この山も、一般的な登頂ルートは、前述の「ツィナールロートホルン」と同じく、東側の「ツェルマット」からです。まず中腹の(ロートホルン小屋;Rothorn Hutte、約3200m)に至り、その後、「トリフト氷河」上部を渡って、前衛峰の「ヴェレンクッペ」(Wellnkuppe;3900m)に登り、更にそこから延びる険しい岩稜である北東稜をたどる、長いルートです(文献9)、(文献10)。
さて「オーバーガーベルホルン」の地質ですが、山頂部、および上記の衛星峰は、「ダンブランシュ・ナップ」(地塊)に属し、そのうちの「アローラユニット」(Arolla unit)の「片麻岩」(Gneis(独))からなっています。この「片麻岩」は、前節の「ツィナールロートホルン」の項でもでてきた、「ペルム紀」の深成岩体由来の、(“Arolla Ortho-gneiss”)と呼ばれる「片麻岩」です。
「オーバーガーベルホルン」の山体は、北に隣接する「ツィナールロートホルン」、南に隣接する「マッターホルン」と同じく、東側の中腹に、重要な地質境界線(スラスト断層;thrust)があり、そのラインより上が「ダンブランシュ・ナップ」に属し、そのラインより下は「ペニン系」の各種地質体、地塊からなります。
添付の(写真3)は、(文献6)からの引用ですが、「マッターホルン」から、ここでいう「ヴァイスホルン山群」の中腹に、その地質境界線が伸びている様子が、明確に描かれています。
「オーバーガーベルホルン」の地質構造は、上記のように「ダンブランシュ・ナップ」に属する「片麻岩」がほとんどで、わりと単調ですが、南側の山麓部だけは、「ツィナールロートホルン」」の「南東ゾーン」から続く、複雑な地質構造となっています。なおこの付近は地形的には、「マッターホルン」との間を区切る「ツムット氷河」(Zmutt glecere)があるU字谷となっています。
地質図としては、添付の図6をご参照ください。
このゾーンには、地質図(文献2A)を見ると、以下のような地質体が分布しています。
1);(変成)「ハンレイ岩」(Gabblo)
2);(変成)「ドロマイト」(Dolomitstein(独))
3);「オフィオライト岩体」(Ophiolith(独))
4);「結晶片岩」類(Kalgig-Schiefer(独))
地質図(文献2A)のテクトニックレイヤーや、(文献5)などによると、この辺りは、テクトニクス的には、「ダンブランシュ・ナップ」(地塊)、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」(地塊)、「ツァテ・ナップ」(地塊)に加え、「フリリホルン・ナップ」(Frilihorn nappe)や「シムズ・ブランシュ・ナップ」(Cimes Blanches nappe)という小さな「地塊」もあるとされており、どの地質体がどの「地塊」に属しているのかも、はっきりしません。
この山は、標高が4000mを少し超える程度ですが、前述の「ツィナールロートホルン」と同じく、「ツェルマット」の東側の展望台「ゴルナーグラート」付近からは、わりと目立つ峰です。東側中腹には、大きなカール状の氷河(Gabelhorn glacier)を持っており、周辺にいくつもの衛星峰を従えた特徴的な姿をしており、標高以上にスケール感の大きな高峰という印象です。 (写真4)、(写真6)もご参照ください。また西の「ツィナール」側は氷雪をまとった姿で、東側の姿とはだいぶ違うそうです(文献9)。
「オーバーガーベルホルン」の(“Ober”)とは、ドイツ語で「上」を意味し、英語の(“upper”)にほぼ対応する言葉です。また(“Gabel”)はドイツ語で「熊手」を意味し、実際は、「熊手状」の農機具の名前だそうで、東側の山容から付けられた名前と推定されています(文献9)。
この山は、多数の衛星峰を擁しており、東側には「ミッテラーガーベルホルン」(Mitteler Gaberhorn;3685m)、「ウンターガーベルホルン」(Unter Gabelhorn;3391m)があります。また北東には、山頂部に雪の帽子をかぶって特徴的な「ヴェレンクッペ」(Wellenkuppe;3900m)があり、主峰と並ぶ姿は双耳峰のようにも見えます。他には、西側には「モン・デュラン」(Mont Durand)あるいは「アルベールホルン」(Arbelhorn)(3712m)と呼ばれるピークがあります。これらの衛星峰も含めて、大きな山塊を作っています。
この山も、一般的な登頂ルートは、前述の「ツィナールロートホルン」と同じく、東側の「ツェルマット」からです。まず中腹の(ロートホルン小屋;Rothorn Hutte、約3200m)に至り、その後、「トリフト氷河」上部を渡って、前衛峰の「ヴェレンクッペ」(Wellnkuppe;3900m)に登り、更にそこから延びる険しい岩稜である北東稜をたどる、長いルートです(文献9)、(文献10)。
さて「オーバーガーベルホルン」の地質ですが、山頂部、および上記の衛星峰は、「ダンブランシュ・ナップ」(地塊)に属し、そのうちの「アローラユニット」(Arolla unit)の「片麻岩」(Gneis(独))からなっています。この「片麻岩」は、前節の「ツィナールロートホルン」の項でもでてきた、「ペルム紀」の深成岩体由来の、(“Arolla Ortho-gneiss”)と呼ばれる「片麻岩」です。
「オーバーガーベルホルン」の山体は、北に隣接する「ツィナールロートホルン」、南に隣接する「マッターホルン」と同じく、東側の中腹に、重要な地質境界線(スラスト断層;thrust)があり、そのラインより上が「ダンブランシュ・ナップ」に属し、そのラインより下は「ペニン系」の各種地質体、地塊からなります。
添付の(写真3)は、(文献6)からの引用ですが、「マッターホルン」から、ここでいう「ヴァイスホルン山群」の中腹に、その地質境界線が伸びている様子が、明確に描かれています。
「オーバーガーベルホルン」の地質構造は、上記のように「ダンブランシュ・ナップ」に属する「片麻岩」がほとんどで、わりと単調ですが、南側の山麓部だけは、「ツィナールロートホルン」」の「南東ゾーン」から続く、複雑な地質構造となっています。なおこの付近は地形的には、「マッターホルン」との間を区切る「ツムット氷河」(Zmutt glecere)があるU字谷となっています。
地質図としては、添付の図6をご参照ください。
このゾーンには、地質図(文献2A)を見ると、以下のような地質体が分布しています。
1);(変成)「ハンレイ岩」(Gabblo)
2);(変成)「ドロマイト」(Dolomitstein(独))
3);「オフィオライト岩体」(Ophiolith(独))
4);「結晶片岩」類(Kalgig-Schiefer(独))
地質図(文献2A)のテクトニックレイヤーや、(文献5)などによると、この辺りは、テクトニクス的には、「ダンブランシュ・ナップ」(地塊)、「ツェルマット・ザースフェー・ゾーン」(地塊)、「ツァテ・ナップ」(地塊)に加え、「フリリホルン・ナップ」(Frilihorn nappe)や「シムズ・ブランシュ・ナップ」(Cimes Blanches nappe)という小さな「地塊」もあるとされており、どの地質体がどの「地塊」に属しているのかも、はっきりしません。
【他の連載へのリンク】
この連載の各項目へのリンクがあります
【補足説明】の項
(補足説明1) 「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」という地塊について
「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」(Siviez Mischabel Decke(独))という「地塊」は、この5−2章では初めて名前が出てくる「地塊」なので、この項で説明します。
この「地塊」は、地質図(文献2A)のテクトニックレイヤーや(文献3)で見ると、「ヴァリス山群」の中〜北部に、比較的広く分布している「地塊」です。
(文献1―1)、(文献1−2)、(文献3)、(文献4)によると、この「地塊」は「ペニン系」地質グループのうち、「ブリアンソン・ライズ系」(Brianson rise)(=中部ペニン系)に属する、大陸性の「地塊」です。
この「地塊」の大部分を占める「片麻岩」類(gneisses)は、原生代〜古生代の堆積岩及び火成岩を起源とし、その後、(おそらく複数回の)変成作用を受けて「片麻岩」類となった「古い片麻岩」で、この「地塊」の基盤岩体(crystalline basement)となっています。
この「地塊」全域を地質図(文献2A)で見ると、上記の「古い片麻岩」のほか、「ペルム紀」の花崗岩質貫入岩体が変成作用を受けてできた、(Randa Augen gneis(独))と呼ばれる花崗岩質の「片麻岩」や、「角閃岩」(Amphibolit(独))、「結晶片岩」類(Scheifer(独))、「クオーツアイト」(Quarztit(独))といった変成岩類も分布しています。これらはまとめて、「基盤岩体」の構成要素です。
それ以外に、被覆層(cover nappes)と呼ばれる、この「地塊」が海面下にあった時代(中生代)の、堆積物由来の地質体があります。
地質図(文献2A)で詳しく見ると、「トリアス紀」の「ドロマイト」(Dolomitstein(独))や、「ジュラ紀」〜「白亜紀」の「石灰岩」(Kalkstein(独))などが、この「地塊」の所々に分布しています。
これらの堆積物は、「アルプス造山運動」の際の変成作用を受けて変成岩となっています。
(文献5)、(文献7)によると、「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」の変成度(グレード)は、「緑色片岩相」とされています。
なお「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」に関する解りやすい研究論文は、ネット上に少なかったのですが、(文献8)には、ある程度、説明があります。
この「地塊」は、地質図(文献2A)のテクトニックレイヤーや(文献3)で見ると、「ヴァリス山群」の中〜北部に、比較的広く分布している「地塊」です。
(文献1―1)、(文献1−2)、(文献3)、(文献4)によると、この「地塊」は「ペニン系」地質グループのうち、「ブリアンソン・ライズ系」(Brianson rise)(=中部ペニン系)に属する、大陸性の「地塊」です。
この「地塊」の大部分を占める「片麻岩」類(gneisses)は、原生代〜古生代の堆積岩及び火成岩を起源とし、その後、(おそらく複数回の)変成作用を受けて「片麻岩」類となった「古い片麻岩」で、この「地塊」の基盤岩体(crystalline basement)となっています。
この「地塊」全域を地質図(文献2A)で見ると、上記の「古い片麻岩」のほか、「ペルム紀」の花崗岩質貫入岩体が変成作用を受けてできた、(Randa Augen gneis(独))と呼ばれる花崗岩質の「片麻岩」や、「角閃岩」(Amphibolit(独))、「結晶片岩」類(Scheifer(独))、「クオーツアイト」(Quarztit(独))といった変成岩類も分布しています。これらはまとめて、「基盤岩体」の構成要素です。
それ以外に、被覆層(cover nappes)と呼ばれる、この「地塊」が海面下にあった時代(中生代)の、堆積物由来の地質体があります。
地質図(文献2A)で詳しく見ると、「トリアス紀」の「ドロマイト」(Dolomitstein(独))や、「ジュラ紀」〜「白亜紀」の「石灰岩」(Kalkstein(独))などが、この「地塊」の所々に分布しています。
これらの堆積物は、「アルプス造山運動」の際の変成作用を受けて変成岩となっています。
(文献5)、(文献7)によると、「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」の変成度(グレード)は、「緑色片岩相」とされています。
なお「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」に関する解りやすい研究論文は、ネット上に少なかったのですが、(文献8)には、ある程度、説明があります。
[補足説明;2] 岩石の種類について
この回でも、色々な種類の岩石が出てきますので、(文献19)、(文献20)などに基づき説明しておきます。詳しくは、上記の文献などをご参照ください。
(1) 「片麻岩」類(gneisses(英)、Gneis(独)):
変成岩のうち、見た目が濃い色(黒っぽい)の部分と、淡い色(白っぽい)の部分が縞模様(片麻状組織)となっている岩石。どちらかというと、高温型の変成岩。日本では分布が限定的だが、ヨーロッパアルプスや世界各地の造山帯、古い地塊(クラトン)では良く見られる。
元となった岩石や、含まれる鉱物によって、細かく種類が分けられている。
原岩が花崗岩類(深成岩)と推定されるものは、「正片麻岩」(ortho-gneiss)、原岩が堆積岩(泥岩、砂岩など)と推定されるものは、「パラ片麻岩」(「準片麻岩」とも)(para-gneiss)という、2種類に区分するやり方も良く使われる。
(2) 「結晶片岩」類(schist(英)、scheifer(独))
変成岩のうち、「片理構造」と呼ばれる、ペラペラしたシートが重なったような構造をもつものの総称。見た目、含まれる主要鉱物、あるいは推定される原岩によって、多数の種類がある。
この回ででてくる「結晶片岩」類では、「雲母片岩」(mica-schist(英)、Glimmer- scheifer(独))は、鉱物として雲母(mica)が目立つもので、「泥質片岩」と同種と思われる。
また「石灰質片岩」(calc-schist(英)、Kalgig-scheifer(独))は、原岩が石灰岩やドロマイトと推定されるもの。
なお(“tonig-schefer”(独))という用語も、地質図(文献2A)に記載されているが、(文献19)、(文献20)などには記載されておらず、よく解らない。
(3) 「角閃岩」(amphibolite(英)、Amphibolit(独));
変成岩のうち、「角閃石」(類)と呼ばれる鉱物が多い変成岩。新鮮面はグレー〜ダークグレーで、風化した表面はやや緑色を帯びる。赤茶色をしたザクロ石という鉱物が含まれる場合もある。
「角閃岩」の原岩は、「玄武岩」、「ハンレイ岩」などの苦鉄質の火成岩と考えられている。
「角閃岩」は、海洋プレート沈み込み帯で、海洋プレートを構成している玄武岩、ハンレイ岩が地下深部で変成作用を受けたものと、マグマ由来の深成岩体としての「ハンレイ岩」が、後に変成作用を受けてできたものがある。
なお岩石としての「角閃岩」も、鉱物としての「角閃石」も、細かく言うと単一の名称ではなく、元素組成によって多数の種類に分類される。
また、原岩が「ハンレイ岩」(gabbro)であることが明確な場合は、「変成ハンレイ岩」(meta-gabbro)と呼ばれることも多い。
(4) 「クオーツアイト」(quartzite(英)、Quarzit(独));
岩石図鑑(文献19)には載っていないが、地学事典(文献20)によると、いくつかの意味あいで使われている岩石の名前。日本語では「珪岩」(けいがん)。
広義には「石英」(quartz)が多い岩石という意味あいで、この章では、おそらく、砂岩由来の、「石英」成分の多い変成岩という意味あいで使われている。
(5) 「結晶質石灰岩」(crystalline limestone);
「石灰岩」類(「ドロマイト」も含む)が変形作用を受けて、「方解石」(calcite)の結晶を多く含む、結晶質となった変成岩。
慣用的に日本語では「大理石」と呼ばれることが多い。英語でも(marble)と呼ぶことも多いが、装飾用石材としての「大理石」のような「マーブル模様」があることはむしろ少ない。
(6) 「ドロマイト」(dolomite、dolostone(英)、Dolomit(独));
「石灰岩」(limestone)の親戚で、化学組成として、Caの代わりにMgが一部あるいは大部分入れ替わったもの。見た目は石灰岩に似ている。
この連載では、「石灰岩類」と呼ぶときは、「ドロマイト」も含む意味で使用している。
(7) 「花崗岩」類(granites、granitoids(英)、Granit(独));
マグマが地下で固まった深成岩のうち、シリカ分(SiO2)が多い(=フェルシックな;felsic)深成岩。
狭義の「花崗岩」の鉱物組成としては、石英、長石類、黒雲母からなる。「花崗岩類」と呼ぶ場合は、(狭義の)「花崗岩」(granite)のほか、「花崗閃緑岩」(grano-diorite)、「トーナル岩」(tonalite)、「石英閃緑岩」(quartz diorite)なども含む。
なお、花崗岩類が高度な変成作用を受け、片麻状組織を持つものは、片麻岩類の一種、「正片麻岩」(ortho-gneiss)と呼ばれることが多い。「変成花崗岩類」(meta-granites、meta-granitoids)と呼ぶこともある。
英語の(granites)は「花崗岩類」、(granitoids)は「花崗岩的な岩石」、というニュアンスの違いがあると思われるが、この連載では区別せず「花崗岩類」と訳した。
(8) 「閃緑岩」(diorite(英)、(Diorit(独));
マグマが地下で固まった深成岩のうち、シリカ分(SiO2)が「花崗岩」と「玄武岩」の間くらい(=intermediate)の深成岩。
(9) 「玄武岩」(basalt);
マグマが地表や海底で固まった火山岩のうち、シリカ分(SiO2)が少ない(=マフィックな;mafic)火山岩。見た目は黒っぽい。
火山から噴出する場合も多いが、海洋地殻の上部は玄武岩からなっており、この章での「玄武岩」は、海洋地殻上部(海洋性プレート上部)由来の玄武岩である。
変成作用を受けた「変成・玄武岩」(meta-basalts)となっていることも多い。その場合、「角閃石」が主要鉱物であるもの、あるいは原岩が「玄武岩」か「ハンレイ岩」か不明な場合は、「角閃岩」と呼ぶことも多い。
(10) 「ハンレイ岩」(gabbro);
マグマが地下で固まった深成岩のうち、シリカ分(SiO2)が少ない(=マフィックな;mafic)深成岩。
海洋地殻の下部は「ハンレイ岩」で出来ている。
深成岩である「ハンレイ岩」は、火山岩の「玄武岩」と化学組成的には同じ。見た目は、白っぽい鉱物(主に長石類)と黒っぽい鉱物(角閃石や輝石類)が入り混じっている感じ。
実際には、変成作用を受けた「変成ハンレイ岩」(meta-gabbro)となっていることも多い。
「変成ハンレイ岩」は、「玄武岩」と同様に、「変成相」での「角閃岩相」の条件化で変成作用を受け、「角閃石」が主要鉱物であるもので、原岩が「玄武岩」か「ハンレイ岩」なのか不明な場合は、「角閃岩」と呼ぶことも多い。
この連載の回での「ハンレイ岩」あるいは「変成ハンレイ岩」は、マグマ由来の深成岩体としてのものと、海洋地殻下部由来のものとがある。
(1) 「片麻岩」類(gneisses(英)、Gneis(独)):
変成岩のうち、見た目が濃い色(黒っぽい)の部分と、淡い色(白っぽい)の部分が縞模様(片麻状組織)となっている岩石。どちらかというと、高温型の変成岩。日本では分布が限定的だが、ヨーロッパアルプスや世界各地の造山帯、古い地塊(クラトン)では良く見られる。
元となった岩石や、含まれる鉱物によって、細かく種類が分けられている。
原岩が花崗岩類(深成岩)と推定されるものは、「正片麻岩」(ortho-gneiss)、原岩が堆積岩(泥岩、砂岩など)と推定されるものは、「パラ片麻岩」(「準片麻岩」とも)(para-gneiss)という、2種類に区分するやり方も良く使われる。
(2) 「結晶片岩」類(schist(英)、scheifer(独))
変成岩のうち、「片理構造」と呼ばれる、ペラペラしたシートが重なったような構造をもつものの総称。見た目、含まれる主要鉱物、あるいは推定される原岩によって、多数の種類がある。
この回ででてくる「結晶片岩」類では、「雲母片岩」(mica-schist(英)、Glimmer- scheifer(独))は、鉱物として雲母(mica)が目立つもので、「泥質片岩」と同種と思われる。
また「石灰質片岩」(calc-schist(英)、Kalgig-scheifer(独))は、原岩が石灰岩やドロマイトと推定されるもの。
なお(“tonig-schefer”(独))という用語も、地質図(文献2A)に記載されているが、(文献19)、(文献20)などには記載されておらず、よく解らない。
(3) 「角閃岩」(amphibolite(英)、Amphibolit(独));
変成岩のうち、「角閃石」(類)と呼ばれる鉱物が多い変成岩。新鮮面はグレー〜ダークグレーで、風化した表面はやや緑色を帯びる。赤茶色をしたザクロ石という鉱物が含まれる場合もある。
「角閃岩」の原岩は、「玄武岩」、「ハンレイ岩」などの苦鉄質の火成岩と考えられている。
「角閃岩」は、海洋プレート沈み込み帯で、海洋プレートを構成している玄武岩、ハンレイ岩が地下深部で変成作用を受けたものと、マグマ由来の深成岩体としての「ハンレイ岩」が、後に変成作用を受けてできたものがある。
なお岩石としての「角閃岩」も、鉱物としての「角閃石」も、細かく言うと単一の名称ではなく、元素組成によって多数の種類に分類される。
また、原岩が「ハンレイ岩」(gabbro)であることが明確な場合は、「変成ハンレイ岩」(meta-gabbro)と呼ばれることも多い。
(4) 「クオーツアイト」(quartzite(英)、Quarzit(独));
岩石図鑑(文献19)には載っていないが、地学事典(文献20)によると、いくつかの意味あいで使われている岩石の名前。日本語では「珪岩」(けいがん)。
広義には「石英」(quartz)が多い岩石という意味あいで、この章では、おそらく、砂岩由来の、「石英」成分の多い変成岩という意味あいで使われている。
(5) 「結晶質石灰岩」(crystalline limestone);
「石灰岩」類(「ドロマイト」も含む)が変形作用を受けて、「方解石」(calcite)の結晶を多く含む、結晶質となった変成岩。
慣用的に日本語では「大理石」と呼ばれることが多い。英語でも(marble)と呼ぶことも多いが、装飾用石材としての「大理石」のような「マーブル模様」があることはむしろ少ない。
(6) 「ドロマイト」(dolomite、dolostone(英)、Dolomit(独));
「石灰岩」(limestone)の親戚で、化学組成として、Caの代わりにMgが一部あるいは大部分入れ替わったもの。見た目は石灰岩に似ている。
この連載では、「石灰岩類」と呼ぶときは、「ドロマイト」も含む意味で使用している。
(7) 「花崗岩」類(granites、granitoids(英)、Granit(独));
マグマが地下で固まった深成岩のうち、シリカ分(SiO2)が多い(=フェルシックな;felsic)深成岩。
狭義の「花崗岩」の鉱物組成としては、石英、長石類、黒雲母からなる。「花崗岩類」と呼ぶ場合は、(狭義の)「花崗岩」(granite)のほか、「花崗閃緑岩」(grano-diorite)、「トーナル岩」(tonalite)、「石英閃緑岩」(quartz diorite)なども含む。
なお、花崗岩類が高度な変成作用を受け、片麻状組織を持つものは、片麻岩類の一種、「正片麻岩」(ortho-gneiss)と呼ばれることが多い。「変成花崗岩類」(meta-granites、meta-granitoids)と呼ぶこともある。
英語の(granites)は「花崗岩類」、(granitoids)は「花崗岩的な岩石」、というニュアンスの違いがあると思われるが、この連載では区別せず「花崗岩類」と訳した。
(8) 「閃緑岩」(diorite(英)、(Diorit(独));
マグマが地下で固まった深成岩のうち、シリカ分(SiO2)が「花崗岩」と「玄武岩」の間くらい(=intermediate)の深成岩。
(9) 「玄武岩」(basalt);
マグマが地表や海底で固まった火山岩のうち、シリカ分(SiO2)が少ない(=マフィックな;mafic)火山岩。見た目は黒っぽい。
火山から噴出する場合も多いが、海洋地殻の上部は玄武岩からなっており、この章での「玄武岩」は、海洋地殻上部(海洋性プレート上部)由来の玄武岩である。
変成作用を受けた「変成・玄武岩」(meta-basalts)となっていることも多い。その場合、「角閃石」が主要鉱物であるもの、あるいは原岩が「玄武岩」か「ハンレイ岩」か不明な場合は、「角閃岩」と呼ぶことも多い。
(10) 「ハンレイ岩」(gabbro);
マグマが地下で固まった深成岩のうち、シリカ分(SiO2)が少ない(=マフィックな;mafic)深成岩。
海洋地殻の下部は「ハンレイ岩」で出来ている。
深成岩である「ハンレイ岩」は、火山岩の「玄武岩」と化学組成的には同じ。見た目は、白っぽい鉱物(主に長石類)と黒っぽい鉱物(角閃石や輝石類)が入り混じっている感じ。
実際には、変成作用を受けた「変成ハンレイ岩」(meta-gabbro)となっていることも多い。
「変成ハンレイ岩」は、「玄武岩」と同様に、「変成相」での「角閃岩相」の条件化で変成作用を受け、「角閃石」が主要鉱物であるもので、原岩が「玄武岩」か「ハンレイ岩」なのか不明な場合は、「角閃岩」と呼ぶことも多い。
この連載の回での「ハンレイ岩」あるいは「変成ハンレイ岩」は、マグマ由来の深成岩体としてのものと、海洋地殻下部由来のものとがある。
【注釈の項】
注1) 山々の標高について;
この章で記載した山々などの標高は、スイスのオンライン地図(文献2A)のうち、地形図レイヤーの値を採用し、記載しています。文献、ガイドブックなどによっては、数m程度違う値となっている場合があります。
注2) スイスのオンライン地質図について;
スイスのオンライン地質図は、パソコン等で見る「ウエブ版」(文献2A)と、スマホのアプリとなっている「アプリ版」(文献2B)(アプリ名;“Swiss topo”)とがあります。
どちらも、(Swiss topo)という機関がデータ元ですが、「ウエブ版」(文献2A)は、説明が詳しく、解像度も高い一方で、ポップアップの地質解説がドイツ語なのでちょっと解りにくい、という短所もあります。
一方「アプリ版」(文献2B)は、地質解説が英語で解りやすいのですが、解像度が低く、かつ、場所が違っていても似たような地質体をグループ化して説明している点は、短所だと思います。
また細かく見ると、地質説明に、けっこう違いがあります。
この章では、それぞれの山、地域を構成している地質(岩石)の説明は、両者に違いがある場合は、主に(文献2A)を参照し、(文献2B)は参考程度としました。
それぞれの地質図の使い方、見方などは、「参考文献」の項をご覧ください
注3) 「オフィオライト(岩体)」(ophiolite(英)、Ophiolit、Ophiolith(独))
一般的には、「海洋性プレート」の断片と考えられている複合岩体。上部海洋地殻を構成している、(変成)「玄武岩」、下部海洋地殻を構成している、(変成)「ハンレイ岩」、リソスフェアマントルを構成している「カンラン岩」(多くの場合、「蛇紋岩」へと変成している)の、3つの岩石の組み合わせが基本。
ただし、これらの一部が欠落している場合も「オフィオライト岩体」と推定される場合も多い。海洋性プレート上部に堆積した堆積物も含む、という定義もあり、ややあいまい。
(※ (5−2章(その1))の「補足説明2」でも解説しましたが、内容はほぼ同じです)
注4) 「地塊」という用語について
「ヨーロッパアルプスの地質学」において、テクトニック地質図や、(文献1)をはじめとした海外の各種文献では、類似した地質学的経歴をもつと考えられ、岩石の組み合わせも類似しているグループを、(nappe(英))、(Decke(独))、(Zone(英)、(独))などと呼んでいるが、日本語的に解りにくいので、この連載では、これらを全て「地塊」と表記した。
なお、「地塊」の下位区分としては、「ユニット」(unit)、「系」(series)をそのまま使用した。
注5) “Ma”は、百万年前を意味する単位
この章で記載した山々などの標高は、スイスのオンライン地図(文献2A)のうち、地形図レイヤーの値を採用し、記載しています。文献、ガイドブックなどによっては、数m程度違う値となっている場合があります。
注2) スイスのオンライン地質図について;
スイスのオンライン地質図は、パソコン等で見る「ウエブ版」(文献2A)と、スマホのアプリとなっている「アプリ版」(文献2B)(アプリ名;“Swiss topo”)とがあります。
どちらも、(Swiss topo)という機関がデータ元ですが、「ウエブ版」(文献2A)は、説明が詳しく、解像度も高い一方で、ポップアップの地質解説がドイツ語なのでちょっと解りにくい、という短所もあります。
一方「アプリ版」(文献2B)は、地質解説が英語で解りやすいのですが、解像度が低く、かつ、場所が違っていても似たような地質体をグループ化して説明している点は、短所だと思います。
また細かく見ると、地質説明に、けっこう違いがあります。
この章では、それぞれの山、地域を構成している地質(岩石)の説明は、両者に違いがある場合は、主に(文献2A)を参照し、(文献2B)は参考程度としました。
それぞれの地質図の使い方、見方などは、「参考文献」の項をご覧ください
注3) 「オフィオライト(岩体)」(ophiolite(英)、Ophiolit、Ophiolith(独))
一般的には、「海洋性プレート」の断片と考えられている複合岩体。上部海洋地殻を構成している、(変成)「玄武岩」、下部海洋地殻を構成している、(変成)「ハンレイ岩」、リソスフェアマントルを構成している「カンラン岩」(多くの場合、「蛇紋岩」へと変成している)の、3つの岩石の組み合わせが基本。
ただし、これらの一部が欠落している場合も「オフィオライト岩体」と推定される場合も多い。海洋性プレート上部に堆積した堆積物も含む、という定義もあり、ややあいまい。
(※ (5−2章(その1))の「補足説明2」でも解説しましたが、内容はほぼ同じです)
注4) 「地塊」という用語について
「ヨーロッパアルプスの地質学」において、テクトニック地質図や、(文献1)をはじめとした海外の各種文献では、類似した地質学的経歴をもつと考えられ、岩石の組み合わせも類似しているグループを、(nappe(英))、(Decke(独))、(Zone(英)、(独))などと呼んでいるが、日本語的に解りにくいので、この連載では、これらを全て「地塊」と表記した。
なお、「地塊」の下位区分としては、「ユニット」(unit)、「系」(series)をそのまま使用した。
注5) “Ma”は、百万年前を意味する単位
【参考文献】
(文献1) O. A. Pfiffner 著 “Geology of the Alps”, 2nd edition ,Wiley Blackball社刊,
(2014); (原著はドイツ語版で、2014年にドイツの出版社刊)
(文献1−1) (文献1)のうち、第5−2章 「中部アルプスのテクトニックな構造」
(Tectonic structure of the Alps ; the Central Alps)
(文献1−2) (文献1)のうち、第3−2章
「中生代のアルプス地域におけるテクトニックな進化」
(the Alpine domain in the Mesozoic; Plate Tectonic evolution)の項の、
図3-16,図3-28(「ジュラ紀」、「白亜紀」の古地理図)。
(文献2A) スイスのオンライン地質図(ウエブ版)
https://map.geo.admin.ch/
※ 地質図は、メニューより、 > Geocatalog > Nature and Environment > Geology
> GeoCover Vector Datasets 、より見ることができる。
※ 断層、テクトニック構造、「地塊」分布図などは、メニューより、> Geocatalog >
Nature and Environment > Geology > Tectonics 500 、より見ることができる。
※ 地形図も兼ねているので、地形図レイヤーより、山名、標高なども確認できる。
※ 地図自体は(EN)を選ぶと英語表記になるが、ポップアップの地質解説はドイツ語
なので、ちょっと解りにくい。
※ 利用したバージョンは、v 1.59.0
(文献2B) スイスのオンライン地質図(スマホアプリ版)
※ スマホに、“Swiss topo” というアプリをインストールして利用する。
※ メニューより、”geology” > “Gological Map” を選ぶと地質図を見ることができる。
※ 地図自体も、ポップアップの地質解説も全て英語なので、解りやすい。
※ 利用したバージョンは、v 1.19.1
(文献3) スイスのテクトニックマップ(紙媒体)
“Tectonische Karte der Schweiz”
50万分の1 図幅、”Swiss topo”発行、(発行年度不明)
ISBN 3-906723-56-9 (“Swiss topo” のインターネットサイトより購入)
(文献4) スイスの地質に関する解説サイト
“ Strati CH;Lithostratigraphic Lexicon of Switzerland ”
https://www.strati.ch/en/
のうち、(Sivies-Mischabel Decke)、(Tsate Decke)、
(Zermatt- Saas Fee Decke) 、(Dent-Blanche Decke)、
(Frilihorn Decke)、(Cimes-Blanches Decke)、
(Arolla Gruppe)、(Arolla Orthogneis)、
(Mont Collon Gabbro)、(Randa-Augengneis)、などの各項
(文献5)
A. Steck、H. Masson、M. Robyr 共著
“Tectonics of the Monte Rosa and surrounding nappes (Switzerland and Italy):
Tertiary phases of subduction, thrusting and folding in the Pennine Alps”
Swiss Journal of Geosciences誌、vol. 108、 p3?34 (2015)
https://sjg.springeropen.com/articles/10.1007/s00015-015-0188-x
(DOIアドレス; https://doi.org/10.1007/s00015-015-0188-x )
※ 「モンテローザ・ナップ」の他、「ヴァリス山群」に分布している、
いつくかの「地塊」(nappe),(zone)について、説明されている。
※ 上記のサイトから、PDF版が無料でダウンロードできる。
(文献6)
M. Marthaler、H. Rougier 共著
“ An Outstanding Mountain: The Matterhorn”
(表題を意訳すると;「マッターホルンの地質と地形」))
書籍;“Landscapes and Landforms of Switzerland ”、pp.187-199 (2021)の一部
https://www.researchgate.net/publication/342847689_An_Outstanding_Mountain_The_Matterhorn
(DOIアドレス; https//www.DOI:10.1007/978-3-030-43203-4_13)
※ 主にマッターホルンの地質と地形について詳しく解説されているが、
周辺の地質についても説明がある。
※ 上記のサイトから、PDFファイルが無料でダウンロードできる。
(文献7)
P. Manzotti、M. Ballèvre、M. Zucali、M. Robyr、Martin Engi 共著
“The tectonometamorphic evolution of the Sesia?Dent Blanche nappes
(internal Western Alps): review and synthesis”
Swiss Journal of Geosciences 誌、vol. 107, p 309?336 (2014)
https://sjg.springeropen.com/articles/10.1007/s00015-014-0172-x
(DOIアドレス ;https://doi.org/10.1007/s00015-014-0172-x )
※ 「ダンブランシュ・ナップ」の構成と地史に関する、新しい仮説を元にした詳しい説明がある
※ 上記のサイトから、PDF版が無料でダウンロードできる。
(文献8)
A. Escher、M. Marthaler 共著
“Cross section from the Briançonnais Siviez-Mischabel nappe, through the Piemont Tsate nappe, to the Austroalpine Dent Blanche unit (Moiry region)”
※ 掲載雑誌名などは不明、 (2001)
https://www.researchgate.net/publication/242137106_Cross_section_from_the_Brianconnais_SiviezMischabel_nappe_through_the_Piemont_Tsate_nappe_to_the_Austroalpine_Dent_Blanche_unit_Moiry_region
※ 上記のサイトから、PDF版が無料でダウンロードできる。
※ 「ローザンヌ大学」による、スイスアルプスの地質巡検の解説らしく、本格的な学術論文ではないが、「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」などの「地塊」に関する説明がある。
(文献9) 近藤 等 著 「アルプスの名峰」 山と渓谷社 刊 (1984)
(文献10) リヒャルト・ゲーデテ著、島田荘平、島田陽子 共訳
「アルプス4000m峰 登山ガイド」 山と渓谷社 刊 (1997)
(文献11) 「地球の歩き方;スイス(2024-2025年版)」 Gakken社 刊 (2023)
(文献12) 小川 著 「ツェルマット;周辺を歩く」
山と渓谷社 刊 (2000)
(文献13) ウイキペディア・ドイツ語版の、(Walliser Alpen)の項
https://de.wikipedia.org/wiki/Walliser_Alpen
(2025年10月 閲覧)
(文献14) ウイキペディア英語版の、(Weisshorn)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Weisshorn
(2025年10月 閲覧)
(文献15) ウイキペディア英語版の、(Zinalrothorn)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Zinalrothorn
(2025年10月 閲覧)
(文献16) ウイキペディア英語版の、(Ober Gabelhorn)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Ober_Gabelhorn
(2025年10月 閲覧)
(文献17) ウイキペディア英語版の、(Dent Blanche )の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Dent_Blanche
(2025年10月 閲覧)
(文献18) ウイキペディア英語版の、(Dent Blanche nappe)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Dent_Blanche_nappe
(2025年10月 閲覧)
(文献19) ウイキペディア英語版の、(Geology of the Alps)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Geology_of_the_Alps
(2025年10月 閲覧)
(文献20) 西本 著「観察を楽しむ、特徴がわかる 岩石図鑑」 ナツメ社刊 (2020)
のうち、 「片麻岩」、「結晶片岩」、「角閃岩」、「花崗岩」、
「閃緑岩」、「ハンレイ岩」などの各項
(文献21) 地質団体研究会 編 「新版 地質事典」 平凡社 刊(1996)のうち、
「オフィオライト」、「ドロマイト」、「クオーツァイト」などの各項
(2014); (原著はドイツ語版で、2014年にドイツの出版社刊)
(文献1−1) (文献1)のうち、第5−2章 「中部アルプスのテクトニックな構造」
(Tectonic structure of the Alps ; the Central Alps)
(文献1−2) (文献1)のうち、第3−2章
「中生代のアルプス地域におけるテクトニックな進化」
(the Alpine domain in the Mesozoic; Plate Tectonic evolution)の項の、
図3-16,図3-28(「ジュラ紀」、「白亜紀」の古地理図)。
(文献2A) スイスのオンライン地質図(ウエブ版)
https://map.geo.admin.ch/
※ 地質図は、メニューより、 > Geocatalog > Nature and Environment > Geology
> GeoCover Vector Datasets 、より見ることができる。
※ 断層、テクトニック構造、「地塊」分布図などは、メニューより、> Geocatalog >
Nature and Environment > Geology > Tectonics 500 、より見ることができる。
※ 地形図も兼ねているので、地形図レイヤーより、山名、標高なども確認できる。
※ 地図自体は(EN)を選ぶと英語表記になるが、ポップアップの地質解説はドイツ語
なので、ちょっと解りにくい。
※ 利用したバージョンは、v 1.59.0
(文献2B) スイスのオンライン地質図(スマホアプリ版)
※ スマホに、“Swiss topo” というアプリをインストールして利用する。
※ メニューより、”geology” > “Gological Map” を選ぶと地質図を見ることができる。
※ 地図自体も、ポップアップの地質解説も全て英語なので、解りやすい。
※ 利用したバージョンは、v 1.19.1
(文献3) スイスのテクトニックマップ(紙媒体)
“Tectonische Karte der Schweiz”
50万分の1 図幅、”Swiss topo”発行、(発行年度不明)
ISBN 3-906723-56-9 (“Swiss topo” のインターネットサイトより購入)
(文献4) スイスの地質に関する解説サイト
“ Strati CH;Lithostratigraphic Lexicon of Switzerland ”
https://www.strati.ch/en/
のうち、(Sivies-Mischabel Decke)、(Tsate Decke)、
(Zermatt- Saas Fee Decke) 、(Dent-Blanche Decke)、
(Frilihorn Decke)、(Cimes-Blanches Decke)、
(Arolla Gruppe)、(Arolla Orthogneis)、
(Mont Collon Gabbro)、(Randa-Augengneis)、などの各項
(文献5)
A. Steck、H. Masson、M. Robyr 共著
“Tectonics of the Monte Rosa and surrounding nappes (Switzerland and Italy):
Tertiary phases of subduction, thrusting and folding in the Pennine Alps”
Swiss Journal of Geosciences誌、vol. 108、 p3?34 (2015)
https://sjg.springeropen.com/articles/10.1007/s00015-015-0188-x
(DOIアドレス; https://doi.org/10.1007/s00015-015-0188-x )
※ 「モンテローザ・ナップ」の他、「ヴァリス山群」に分布している、
いつくかの「地塊」(nappe),(zone)について、説明されている。
※ 上記のサイトから、PDF版が無料でダウンロードできる。
(文献6)
M. Marthaler、H. Rougier 共著
“ An Outstanding Mountain: The Matterhorn”
(表題を意訳すると;「マッターホルンの地質と地形」))
書籍;“Landscapes and Landforms of Switzerland ”、pp.187-199 (2021)の一部
https://www.researchgate.net/publication/342847689_An_Outstanding_Mountain_The_Matterhorn
(DOIアドレス; https//www.DOI:10.1007/978-3-030-43203-4_13)
※ 主にマッターホルンの地質と地形について詳しく解説されているが、
周辺の地質についても説明がある。
※ 上記のサイトから、PDFファイルが無料でダウンロードできる。
(文献7)
P. Manzotti、M. Ballèvre、M. Zucali、M. Robyr、Martin Engi 共著
“The tectonometamorphic evolution of the Sesia?Dent Blanche nappes
(internal Western Alps): review and synthesis”
Swiss Journal of Geosciences 誌、vol. 107, p 309?336 (2014)
https://sjg.springeropen.com/articles/10.1007/s00015-014-0172-x
(DOIアドレス ;https://doi.org/10.1007/s00015-014-0172-x )
※ 「ダンブランシュ・ナップ」の構成と地史に関する、新しい仮説を元にした詳しい説明がある
※ 上記のサイトから、PDF版が無料でダウンロードできる。
(文献8)
A. Escher、M. Marthaler 共著
“Cross section from the Briançonnais Siviez-Mischabel nappe, through the Piemont Tsate nappe, to the Austroalpine Dent Blanche unit (Moiry region)”
※ 掲載雑誌名などは不明、 (2001)
https://www.researchgate.net/publication/242137106_Cross_section_from_the_Brianconnais_SiviezMischabel_nappe_through_the_Piemont_Tsate_nappe_to_the_Austroalpine_Dent_Blanche_unit_Moiry_region
※ 上記のサイトから、PDF版が無料でダウンロードできる。
※ 「ローザンヌ大学」による、スイスアルプスの地質巡検の解説らしく、本格的な学術論文ではないが、「シヴィエ・ミシャベル・ナップ」などの「地塊」に関する説明がある。
(文献9) 近藤 等 著 「アルプスの名峰」 山と渓谷社 刊 (1984)
(文献10) リヒャルト・ゲーデテ著、島田荘平、島田陽子 共訳
「アルプス4000m峰 登山ガイド」 山と渓谷社 刊 (1997)
(文献11) 「地球の歩き方;スイス(2024-2025年版)」 Gakken社 刊 (2023)
(文献12) 小川 著 「ツェルマット;周辺を歩く」
山と渓谷社 刊 (2000)
(文献13) ウイキペディア・ドイツ語版の、(Walliser Alpen)の項
https://de.wikipedia.org/wiki/Walliser_Alpen
(2025年10月 閲覧)
(文献14) ウイキペディア英語版の、(Weisshorn)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Weisshorn
(2025年10月 閲覧)
(文献15) ウイキペディア英語版の、(Zinalrothorn)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Zinalrothorn
(2025年10月 閲覧)
(文献16) ウイキペディア英語版の、(Ober Gabelhorn)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Ober_Gabelhorn
(2025年10月 閲覧)
(文献17) ウイキペディア英語版の、(Dent Blanche )の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Dent_Blanche
(2025年10月 閲覧)
(文献18) ウイキペディア英語版の、(Dent Blanche nappe)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Dent_Blanche_nappe
(2025年10月 閲覧)
(文献19) ウイキペディア英語版の、(Geology of the Alps)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Geology_of_the_Alps
(2025年10月 閲覧)
(文献20) 西本 著「観察を楽しむ、特徴がわかる 岩石図鑑」 ナツメ社刊 (2020)
のうち、 「片麻岩」、「結晶片岩」、「角閃岩」、「花崗岩」、
「閃緑岩」、「ハンレイ岩」などの各項
(文献21) 地質団体研究会 編 「新版 地質事典」 平凡社 刊(1996)のうち、
「オフィオライト」、「ドロマイト」、「クオーツァイト」などの各項
【書記事項】
・初版リリース;2025年10月18日
△改訂1;(2025年10月19日)
5−2章のうち、(その1)(旧稿)の投稿内容が長すぎるため、「(その1)(改)」と「(その2)(新)」に分割することとした。そのため、この連載は、当初の「5−2章(その2)」から「5−2章(その3)」へと表題を改めた。なお、内容に大きな変更はない。
△改訂2;(2025年10月22日)
・「補足説明」の項に入れていた「ツァテ・ナップ」に関する解説は、この連載の5−2章(その1)の部分に移行した。
・「注釈」の項に入れていた「岩石の説明」を、「補足説明」の項に移行した。
△改訂3;(2025年10月23日)
・誤記などを修正
〇最新改訂年月日;2025年10月23日
△改訂1;(2025年10月19日)
5−2章のうち、(その1)(旧稿)の投稿内容が長すぎるため、「(その1)(改)」と「(その2)(新)」に分割することとした。そのため、この連載は、当初の「5−2章(その2)」から「5−2章(その3)」へと表題を改めた。なお、内容に大きな変更はない。
△改訂2;(2025年10月22日)
・「補足説明」の項に入れていた「ツァテ・ナップ」に関する解説は、この連載の5−2章(その1)の部分に移行した。
・「注釈」の項に入れていた「岩石の説明」を、「補足説明」の項に移行した。
△改訂3;(2025年10月23日)
・誤記などを修正
〇最新改訂年月日;2025年10月23日
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
ベルクハイルさんの記事一覧
-
「ヨーロッパアルプスの地質学」;5−2章 「ヴァリス山群」の地質 (その2、新);「モンテローザ」、「ブライトホルン」、及び「ゴルナーグラート」付近の地質 3 更新日:2025年10月21日
-
「ヨーロッパアルプスの地質学」;5−2章 「ヴァリス山群」の地質(その3);ヴァイスホルンとその周辺 3 更新日:2025年10月23日
-
 「ヨーロッパアルプスの地質学」;5−2章 「ヴァリス山群」の地質(その1(改));ヴァリス山群の概要、及び「マッターホルン」の地質
4
更新日:2025年10月20日
「ヨーロッパアルプスの地質学」;5−2章 「ヴァリス山群」の地質(その1(改));ヴァリス山群の概要、及び「マッターホルン」の地質
4
更新日:2025年10月20日
※この記事はヤマレコの「ヤマノート」機能を利用して作られています。
どなたでも、山に関する知識や技術などのノウハウを簡単に残して共有できます。
ぜひご協力ください!

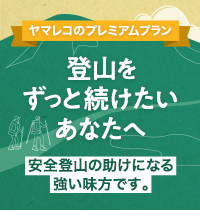






コメントを編集
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する