記録ID: 7371691
全員に公開
無雪期ピークハント/縦走
甲信越
粟ヶ岳/北五百川コース
2024年10月13日(日) [日帰り]

体力度
3
日帰りが可能
- GPS
- --:--
- 距離
- 11.9km
- 登り
- 1,199m
- 下り
- 1,197m
コースタイム
| 天候 | 晴れ時々曇り |
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2024年10月の天気図 |
| アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
| コース状況/ 危険箇所等 |
よく整備された登山道です。粘土質の土は乾いていても滑りやすいので注意。 |
| その他周辺情報 | いい湯らてい、にて汗を流しました。大人@900円。 |
写真
去年11月に続いて2回目の粟ヶ岳。3週間ぶりの登山ということで足慣らしも兼ねています。
3:30 北五百川コース登山口(150m)出発
3:54 元堂(180m)八汐尾根へ
5:07 粟薬師・5合目(600m)
5:38 短いクサリ場(730m)
去年11月と比べても気温が低いと感じました。今回は雨上がりではないので、湿度が低かったからかもしれません。
3:30 北五百川コース登山口(150m)出発
3:54 元堂(180m)八汐尾根へ
5:07 粟薬師・5合目(600m)
5:38 短いクサリ場(730m)
去年11月と比べても気温が低いと感じました。今回は雨上がりではないので、湿度が低かったからかもしれません。
7:19 粟ヶ岳山頂(1292.6m)到着!!
着きました!
雲一つない快晴、澄んだ秋の景色。最高です!
そして去年は登頂後すぐに広角レンズが破損するという事態となったので、
今回は心ゆくまでカメラ片手に景色を楽しみたいところ。
着きました!
雲一つない快晴、澄んだ秋の景色。最高です!
そして去年は登頂後すぐに広角レンズが破損するという事態となったので、
今回は心ゆくまでカメラ片手に景色を楽しみたいところ。
装備
| 個人装備 |
三脚
水
ハイドレーションシステム
長袖シャツ
Tシャツ
ソフトシェル
タイツ
ズボン
靴下
スパッツ
グローブ
雨具
日よけ帽子
靴
予備靴ひも
ザック
ザックカバー
行動食
非常食
飲料
地図(地形図・山と高原地図)
コンパス
ガーミンGPS
笛
鈴
ラジオ
計画書
ヘッドランプ
予備電池
アマチュア無線機
ファーストエイドキット
補修キット
常備薬
日焼け止め
ロールペーパー
登山保険証
健康保険証
スマホ
財布
サングラス
タオル
一眼レフカメラ
広角ズームレンズ
望遠ズームレンズ
ねんどろいど(あおい・ひなた)
|
|---|
感想
今回は3週間ぶり、そして風邪の病み上がりもあって、
程好い負荷をということで1回登ったことのある粟ヶ岳を選びました。
去年11月の初登頂直後にレンズが壊れ、思うように撮影できなかったリトライも兼ねています。
豪雪地帯ということで森林限界が低く、山頂はもちろん眺望絶佳。
澄んだ秋空の下、去年は見えなかった弥彦山、日本海は元より、磐梯山や飯豊山まで
くっきり見えて最高でした。気付けば1時間20分もの山頂滞在となりました。
やはり粟ヶ岳は本当に名山です。
まるで平日のように静かな山行、そして久々に良い汗をかきました。
夏が終わってからというもの、週末は殆ど天候が微妙で消化不良でしたが、
やはり好天の山に登ると元気が出ます。
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:179人

 loon_nz
loon_nz

 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大 拍手
拍手








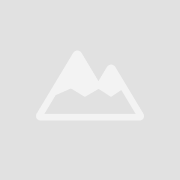





体調をくずされてたのでしたか。
無事 復帰されて、よかったです。
足慣らしとはいえ7時間走行、
さすがです。
3時半出発と はやいですね。ご自宅から
登山口まで 3時間必要で
12時に家を出られたのかな?
やはりお若いです。
ブルーの御写真がいいですね。
空気が澄んでいる感じがいたします
ススキ越しの山の景色は 好きです。
やせ尾根を歩いておられるのは
ルーンさん? ドローンで写したような
写真ですね。!!
素敵な御写真をありがとうございます。
2回目だったのですね。
最近は ルーンさんの山行を
忘れてしまって、土地勘がない関東と言うのもありますが、
お年です。笑 申し訳ないですが
2度目でも新鮮に拝見できるのは
良いのかもです。あはは。
前回は見えなかった 山々が見えて
山頂滞在1時間20分とはすごい、
私はきっとせっかちで あまりゆっくりできなくて、、
次はゆっくりしてみたいです。
ありがとうございました。
いつもご覧いただきましてありがとうございます。
前回いつひいたのかはっきり覚えていないくらい風邪をひかないのですが、
久しぶりに37℃越えで辛かったです。今はほぼ全快です。ありがとうございます。
先週末の3連休は9月にきていたらと思う好天でしたね。
まだちょっと風邪の症状は残ってましたが、行けると判断しました。
山の空気を吸ったら風邪も吹き飛ぶかなと思いました。
家を出発したのは0時半でした。出発する時は気合が要るんですが、
夜中は道路ガラ空きで運転が楽なんですよ。
病み上がりだったので、様子が分かっている山にしようということで粟ヶ岳にしました。
去年は春のような霞がかった景色で、近くの弥彦山も見えなかったのです。
2回目でも景色が本当にきれいで、撮影にも気合が入りました。
ドローンで写したように見えるのは思い切り広角にして自分が離れたからです。
さりげない工夫なんですが、楽しんで見ていただいて有難いです。
去年は登頂してすぐにレンズが壊れ、景色が霞んでいたこともあって、
楽しめたかというとやはり後味の悪い記憶となってしまいました。
去年のこともあったので、今回の山頂滞在は本当に景色を満喫できました。
「日本百名山」の著者の深田さんは、いつも時間を掛けて景色をしっかり見ておられたそうです。
写真を撮るのはもちろん楽しいですが、自分の目でもしっかり見ておこうといつも心掛けています。
それと自分も土地勘はあまりないので、山頂に居ても方向感覚がイマイチ掴み切れていないです。
土地勘がない地方の山ですので、なかなか覚えにくいのは自然なことと思います。
逆に自分にとって行ったことのある山にはモチヴェーションが上がりにくくなっており、
初めての山のようにいつも新鮮な気持ちで登れたらなと思います。
このたびもありがとうございました!
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する