記録ID: 8641783
全員に公開
ハイキング
富士・御坂
富士山 ご無沙汰のスバ吉ルートで色々と新発見(2025)
2025年09月04日(木) [日帰り]

- GPS
- 09:02
- 距離
- 15.9km
- 登り
- 1,620m
- 下り
- 1,616m
コースタイム
日帰り
- 山行
- 7:18
- 休憩
- 2:19
- 合計
- 9:37
距離 15.9km
登り 1,620m
下り 1,616m
5:16
5分
スタート地点
14:53
| 天候 | 台風前の影響か、終日ミストとガスと、ときどき小雨 |
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2025年09月の天気図 |
| アクセス |
利用交通機関:
バス
都内→ハイウェイバスで富士急ハイランド横のカプセルホテル前泊→徒歩20分で富士山パーキング→巡回バスでスバルライン吉田口5号目へ 復路 スバルライン吉田口5号目→路線バスで河口湖駅→ハイウェイバスで都内へ帰宅 |
| コース状況/ 危険箇所等 |
吉田ルートの崩壊は激しく、その改修工事がかなり入っているのが見受けられた |
| その他周辺情報 | なんちゃらカプセルホテルから徒歩5分ほどのスーパーは22時頃まで営業していて、夜は売れ残り中華惣菜が100円台、200円台とかなりお得でした |
| 予約できる山小屋 |
頂上富士館
江戸屋
胸突江戸屋
日の出館
本七合目鳥居荘
白雲荘
|
写真
ガスが登ってきた。ちなみに前を登る水色のポンチョを着てる女性はソロ登山のようでしたが突然「あぁもう!!」的な不満を表す奇声を発したり、デカい声で歌を歌ったりと独り言を中国語でずっと言ってて怖かった
まずは「伊豆岳」へ。「伊豆岳は浅間大社の見解では八神峰には含まない」とWikipediaの記載が有り、久須志神社脇の看板には確かに記載が無いものの、剣ヶ峰直下に設置されている「富士学会」執筆の地図には記載がありますね。富士学会は「富士山に関する研究を推進する『日本学術会議』協力学術研究団体です」だそうです、色々有りますね
「駒ヶ岳」に上がる。ここにある「銅馬舎」から御殿場口を見下ろす、の図。ここの祠には聖徳太子が馬に乗って富士山に飛来したことに由来する銅製の馬が有ると書かれていますが、数年前に来た時も銅馬像は見当たらないものの(保管中?盗難?)、「神鏡」はがっしりと設置されているお陰でまだ存在します。
富士宮口頂上脇の有料トイレに寄るも「トイレの神様」は居らず。もう上がる体力が無いとのことで少し寂しい気分で排尿。そんな会話をしていたら、この「三島岳」は登れるとお聞きし踏み跡を探して上がってみる。正式なルートは少し先に進んでUターンする感じで上がる踏み跡が有りますが、この当たりから正面突破で上がれる踏み跡も有ります。
大沢崩れ源頭部の頂点を撮ろうとしていたら、突然後ろから登山者の方に抜かれたので映り込んでしまったけど、なんか良い感じなのでアップします笑。右端に朽ちた鳥居の足元が写っていますね
たまに写真がアップされていたこの「全日本山岳リレー縦走の記念碑」となる方角指示盤オブジェは久須志岳にあったんですね。やっと見つけられました。頂上扇屋のお二人方、本当に有難う御座いました。
久須志神社に戻ってきました。浅間大社の図では「伊豆岳」は描かれていません。富士学会の根拠も知りたいですね (昔撮った写真だと駒ヶ岳の下に「←WC」と落書き?されていたんですが綺麗に消されてますねw)
今年から設置された鉄ゲート、やり過ぎ感。ちなみに上部の横の鉄筋(鳥居で言う貫(ぬき)部分?)の両端の切り方が垂直ではなく斜めに切ってるのは、いわゆる「神明系」と呼ばれる鳥居の「襷(たすき)落とし」の手法を取り入れているのでしょうか? 鳥居でも無いけど色味も含めて鳥居風にしようとしているのが山梨クオリティ
感想
仕事の調整の目処が立ったので、急遽「日帰りコース」を組む。
となると「スバルライン吉田口ルート」しか時間的に選択肢が無く、あまりテンションが上がらないながらも、そう言えば数年マトモに使ってないなと思い「たまには良いか」とコース決定。
例えるなら昔好きだったけど最近全く観なくなっていたYouTuberのチャンネルがオススメに出て来て、興味は無いけどなんと無く観ようかな、と同じ感覚
さて入山
スバルライン吉田口スタッフ特有の、あの「登山者を見下す無礼さ」も華麗にスルーして登山開始
久しぶりの吉田口ルートは自然崩壊が進んでいる様で、補修工事の多さが崩壊の進行を表していて、少し寂しいものがありました。
なお、朝2時起きで中華惣菜を山盛り食べるのはキツいものがありますが、登山の日は朝から超ハイカロリー(1,000Kcalを目安に)を摂取すると登山後半のバテ度がレベル違いで超絶ラクなのでオススメです。
特に「炭水化物多めの脂質それなりの量」という組み合わせで摂取すると、私の場合は消化スピードと消費のペースがちょうど良く(8年の筋トレを通じたPFCバランスの試行と体感をもとにした個人的見解)、カロリーは登山の最大勝因だと再認識させられた山行となりました。カロリー最高、炭水化物最高♪
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:361人

 pekinska
pekinska

 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大
 拍手
拍手



































































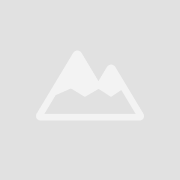












いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する