 河口湖から新富士行きの最終バスに乗る。道の駅なるさわでは車窓から焼けかけた富士が見えた。
河口湖から新富士行きの最終バスに乗る。道の駅なるさわでは車窓から焼けかけた富士が見えた。
 1
1
9/6 18:07
河口湖から新富士行きの最終バスに乗る。道の駅なるさわでは車窓から焼けかけた富士が見えた。
 そのまま絶景を堪能しながらて朝霧高原へ、と思ったら精進湖・本栖湖は暑い雲の中へ。雨を心配したが局所的だったらしく高原に着く頃には路面は完全に乾いていた。
そのまま絶景を堪能しながらて朝霧高原へ、と思ったら精進湖・本栖湖は暑い雲の中へ。雨を心配したが局所的だったらしく高原に着く頃には路面は完全に乾いていた。
 1
1
9/6 18:19
そのまま絶景を堪能しながらて朝霧高原へ、と思ったら精進湖・本栖湖は暑い雲の中へ。雨を心配したが局所的だったらしく高原に着く頃には路面は完全に乾いていた。
 <道の駅 朝霧高原>
<道の駅 朝霧高原>
軽くステビして出発するつもりが車の出入りが多く騒がしかったので眠れず、予定を1時間ほど繰り上げて出発。滞在中は肌寒いくらいで虫にも悩まされず快適だった。
 1
1
9/6 23:53
<道の駅 朝霧高原>
軽くステビして出発するつもりが車の出入りが多く騒がしかったので眠れず、予定を1時間ほど繰り上げて出発。滞在中は肌寒いくらいで虫にも悩まされず快適だった。
 荷物を纏めて国道を南下。翌日は皆既月食の日という事で月明りと街灯でヘッドライトは時々点ける位で良かった。
荷物を纏めて国道を南下。翌日は皆既月食の日という事で月明りと街灯でヘッドライトは時々点ける位で良かった。
 1
1
9/6 23:56
荷物を纏めて国道を南下。翌日は皆既月食の日という事で月明りと街灯でヘッドライトは時々点ける位で良かった。
 ふと気配を感じたので照らしてみるとホルスタインが草を食んでいた。夜中は寝ないでいいの。
ふと気配を感じたので照らしてみるとホルスタインが草を食んでいた。夜中は寝ないでいいの。
 1
1
9/7 0:15
ふと気配を感じたので照らしてみるとホルスタインが草を食んでいた。夜中は寝ないでいいの。
 <朝霧さわやかパーキング>
<朝霧さわやかパーキング>
30分ほどゆるゆると下った所にあった駐車場。自販機もトイレもあるのでここで時間調整をしても良かったかも。
 1
1
9/7 0:20
<朝霧さわやかパーキング>
30分ほどゆるゆると下った所にあった駐車場。自販機もトイレもあるのでここで時間調整をしても良かったかも。
 今回のルート付近にある2軒のコンビニのうちこちらは夜間は営業していなかった。
今回のルート付近にある2軒のコンビニのうちこちらは夜間は営業していなかった。
 1
1
9/7 0:30
今回のルート付近にある2軒のコンビニのうちこちらは夜間は営業していなかった。
 一時間ほど歩いて県道75号線に移り人穴浅間神社へ。境内には230基を超す富士講の碑塔が立ち並ぶ。
一時間ほど歩いて県道75号線に移り人穴浅間神社へ。境内には230基を超す富士講の碑塔が立ち並ぶ。
 1
1
9/7 1:03
一時間ほど歩いて県道75号線に移り人穴浅間神社へ。境内には230基を超す富士講の碑塔が立ち並ぶ。
 <人穴浅間神社>
<人穴浅間神社>
神仏分離令により光侎寺大日堂の代わりに置かれた浅間神社の一つ。祭神は勿論コノハナサクヤヒメに加え富士講の開祖長谷川角行。現在の社殿は平成になってから造営されたもの。
 1
1
9/7 1:05
<人穴浅間神社>
神仏分離令により光侎寺大日堂の代わりに置かれた浅間神社の一つ。祭神は勿論コノハナサクヤヒメに加え富士講の開祖長谷川角行。現在の社殿は平成になってから造営されたもの。
 地名の由来ともなった「人穴」。約1万年前の溶岩流にできた洞穴で古来より霊験のある場所として知られるほか、角行の修行した地とされる。
地名の由来ともなった「人穴」。約1万年前の溶岩流にできた洞穴で古来より霊験のある場所として知られるほか、角行の修行した地とされる。
 1
1
9/7 1:06
地名の由来ともなった「人穴」。約1万年前の溶岩流にできた洞穴で古来より霊験のある場所として知られるほか、角行の修行した地とされる。
 参道を下りて社務所を過ぎた先には人穴浄土門の碑が建つ。風化して碑文の判読は難しいが上部に左読みで「人穴浄土門」と読める。人穴が角行入滅の地という事で浄土に至る門として富士講信者にとっての聖地となっている。
参道を下りて社務所を過ぎた先には人穴浄土門の碑が建つ。風化して碑文の判読は難しいが上部に左読みで「人穴浄土門」と読める。人穴が角行入滅の地という事で浄土に至る門として富士講信者にとっての聖地となっている。
 1
1
9/7 1:12
参道を下りて社務所を過ぎた先には人穴浄土門の碑が建つ。風化して碑文の判読は難しいが上部に左読みで「人穴浄土門」と読める。人穴が角行入滅の地という事で浄土に至る門として富士講信者にとっての聖地となっている。
 参道一の鳥居には「浅間人穴」の扁額。
参道一の鳥居には「浅間人穴」の扁額。
 1
1
9/7 1:13
参道一の鳥居には「浅間人穴」の扁額。
 人穴小学校の先で東に折れ広見地区へ。ここから徐々に高度を上げていく。この辺りも酪農の施設がひしめく。
人穴小学校の先で東に折れ広見地区へ。ここから徐々に高度を上げていく。この辺りも酪農の施設がひしめく。
 1
1
9/7 1:36
人穴小学校の先で東に折れ広見地区へ。ここから徐々に高度を上げていく。この辺りも酪農の施設がひしめく。
 広見公民館の少し北にある事務所に設置された自販機が最後の補給地点かな。
広見公民館の少し北にある事務所に設置された自販機が最後の補給地点かな。
 1
1
9/7 1:36
広見公民館の少し北にある事務所に設置された自販機が最後の補給地点かな。
 公民館を東に折れて進んだ先の養鶏場にも自販機は見えたけど敷地内なので利用はできなさそう。
公民館を東に折れて進んだ先の養鶏場にも自販機は見えたけど敷地内なので利用はできなさそう。
 1
1
9/7 1:54
公民館を東に折れて進んだ先の養鶏場にも自販機は見えたけど敷地内なので利用はできなさそう。
 <上井出林道起点>
<上井出林道起点>
養鶏場先のゲートよりいよいよ林道に入場。
 1
1
9/7 1:59
<上井出林道起点>
養鶏場先のゲートよりいよいよ林道に入場。
 ゲートの看板類を読んでいるとカメラトラップがあるとか……。
ゲートの看板類を読んでいるとカメラトラップがあるとか……。
 1
1
9/7 1:59
ゲートの看板類を読んでいるとカメラトラップがあるとか……。
 裾野に四方八方に広がる林道は思いの外歩きやすく勾配も殆ど感じさせず進んでいけた。十万石林道起点の手前は広場になっていて重機や材木が整然と並び作業基地のようだった。
裾野に四方八方に広がる林道は思いの外歩きやすく勾配も殆ど感じさせず進んでいけた。十万石林道起点の手前は広場になっていて重機や材木が整然と並び作業基地のようだった。
 1
1
9/7 2:44
裾野に四方八方に広がる林道は思いの外歩きやすく勾配も殆ど感じさせず進んでいけた。十万石林道起点の手前は広場になっていて重機や材木が整然と並び作業基地のようだった。
 大沢取り付きを一旦過ぎて上井出登山道を見に行く。大沢の先のカーブが伐採地になっていて西側の空が広がる。
大沢取り付きを一旦過ぎて上井出登山道を見に行く。大沢の先のカーブが伐採地になっていて西側の空が広がる。
 1
1
9/7 3:29
大沢取り付きを一旦過ぎて上井出登山道を見に行く。大沢の先のカーブが伐採地になっていて西側の空が広がる。
 伐採地の少し先で上井出登山道を観察。下部は一般の登山道と呼んでもいいほどに道形がはっきりとしている。
伐採地の少し先で上井出登山道を観察。下部は一般の登山道と呼んでもいいほどに道形がはっきりとしている。
 1
1
9/7 3:38
伐採地の少し先で上井出登山道を観察。下部は一般の登山道と呼んでもいいほどに道形がはっきりとしている。
 上部はやや不明瞭。暗い林床を行くのでこちらから登るのは止しておく。
上部はやや不明瞭。暗い林床を行くのでこちらから登るのは止しておく。
 1
1
9/7 3:38
上部はやや不明瞭。暗い林床を行くのでこちらから登るのは止しておく。
 大沢取り付き点に引き返し川床から入山する。ひどいガレを想定していたけど歩行への支障はあまりない。
大沢取り付き点に引き返し川床から入山する。ひどいガレを想定していたけど歩行への支障はあまりない。
 1
1
9/7 3:55
大沢取り付き点に引き返し川床から入山する。ひどいガレを想定していたけど歩行への支障はあまりない。
 しばらくは堆積した岩を足場に堰堤を越えていける。
しばらくは堆積した岩を足場に堰堤を越えていける。
 1
1
9/7 4:04
しばらくは堆積した岩を足場に堰堤を越えていける。
 ようやく空が晴れてきた。
ようやく空が晴れてきた。
 1
1
9/7 4:10
ようやく空が晴れてきた。
 大沢第2号練積堰堤で行き詰まる。石の隙間に手は掛けられても足がどうしても滑ってしまう。
大沢第2号練積堰堤で行き詰まる。石の隙間に手は掛けられても足がどうしても滑ってしまう。
 1
1
9/7 4:17
大沢第2号練積堰堤で行き詰まる。石の隙間に手は掛けられても足がどうしても滑ってしまう。
 ひとつ手前の大沢第2号コンクリート床固まで戻り左岸を巻いて歩く。
ひとつ手前の大沢第2号コンクリート床固まで戻り左岸を巻いて歩く。
 1
1
9/7 4:22
ひとつ手前の大沢第2号コンクリート床固まで戻り左岸を巻いて歩く。
 越えられなかった堰堤の上まで来てみると細いロープが垂れていた。気付いていても利用はしなかったと思うけど……。
越えられなかった堰堤の上まで来てみると細いロープが垂れていた。気付いていても利用はしなかったと思うけど……。
 1
1
9/7 4:25
越えられなかった堰堤の上まで来てみると細いロープが垂れていた。気付いていても利用はしなかったと思うけど……。
 堰堤の先からはしばらく崖沿いに進む。あまり沢から離れると灌木がうるさいしかと言って沢床まではかなり高さがあるので崖に寄りすぎるのも危険。
堰堤の先からはしばらく崖沿いに進む。あまり沢から離れると灌木がうるさいしかと言って沢床まではかなり高さがあるので崖に寄りすぎるのも危険。
 1
1
9/7 4:25
堰堤の先からはしばらく崖沿いに進む。あまり沢から離れると灌木がうるさいしかと言って沢床まではかなり高さがあるので崖に寄りすぎるのも危険。
 なんてことも言っていられず、崩落で道がなくなるので南側の斜面へ退避する。
なんてことも言っていられず、崩落で道がなくなるので南側の斜面へ退避する。
 1
1
9/7 4:26
なんてことも言っていられず、崩落で道がなくなるので南側の斜面へ退避する。
 上部にはかなりはっきりとした道が付けられていた。上井出口の登山道だろうか。
上部にはかなりはっきりとした道が付けられていた。上井出口の登山道だろうか。
 1
1
9/7 4:30
上部にはかなりはっきりとした道が付けられていた。上井出口の登山道だろうか。
 北山林道近くでやっと山頂と対面。
北山林道近くでやっと山頂と対面。
 1
1
9/7 4:33
北山林道近くでやっと山頂と対面。
 一度沢に下りて右岸に乗り移る。
一度沢に下りて右岸に乗り移る。
 1
1
9/7 4:45
一度沢に下りて右岸に乗り移る。
 フジアザミ
フジアザミ
 1
1
9/7 4:46
フジアザミ
 大滝監視カメラ脇を通過。
大滝監視カメラ脇を通過。
 1
1
9/7 4:48
大滝監視カメラ脇を通過。
 調子よく右岸を歩いて行ったら三ッ沢の北側に入り込んでしまっていた。奥に見えているのが大沢。
調子よく右岸を歩いて行ったら三ッ沢の北側に入り込んでしまっていた。奥に見えているのが大沢。
 1
1
9/7 5:03
調子よく右岸を歩いて行ったら三ッ沢の北側に入り込んでしまっていた。奥に見えているのが大沢。
 だんだんと明るくなってきて大沢の下流や天子山塊まで見えてきた。この感じだと赤富士になっている事だろう。
だんだんと明るくなってきて大沢の下流や天子山塊まで見えてきた。この感じだと赤富士になっている事だろう。
 1
1
9/7 5:07
だんだんと明るくなってきて大沢の下流や天子山塊まで見えてきた。この感じだと赤富士になっている事だろう。
 <大滝>
<大滝>
南側に移るとすぐ先が大滝。先日の台風でもう少し水量があるかと思ったけど若干量が滴る程度だった。
 1
1
9/7 5:08
<大滝>
南側に移るとすぐ先が大滝。先日の台風でもう少し水量があるかと思ったけど若干量が滴る程度だった。
 ホソエノアザミ
ホソエノアザミ
 1
1
9/7 5:14
ホソエノアザミ
 シロヨメナとテンニンソウ
シロヨメナとテンニンソウ
 1
1
9/7 5:15
シロヨメナとテンニンソウ
 本当は間違えた北側に取り付きのピンクテープがあったのだけど横着して南側から鉄砲尾根に取り付いた。尾根上はブルーのテープが道案内をしてくれる。
本当は間違えた北側に取り付きのピンクテープがあったのだけど横着して南側から鉄砲尾根に取り付いた。尾根上はブルーのテープが道案内をしてくれる。
 1
1
9/7 5:16
本当は間違えた北側に取り付きのピンクテープがあったのだけど横着して南側から鉄砲尾根に取り付いた。尾根上はブルーのテープが道案内をしてくれる。
 少し登ると土石流感知のワイヤが大沢に張られている。ここから上部で検知するための光ファイバーがビニル管に通されていて、その多くが地上に出ているのでこれも尾根歩きの目印になる。
少し登ると土石流感知のワイヤが大沢に張られている。ここから上部で検知するための光ファイバーがビニル管に通されていて、その多くが地上に出ているのでこれも尾根歩きの目印になる。
 1
1
9/7 5:19
少し登ると土石流感知のワイヤが大沢に張られている。ここから上部で検知するための光ファイバーがビニル管に通されていて、その多くが地上に出ているのでこれも尾根歩きの目印になる。
 若木保護のような人工物も点々と設置されている。古い道標らしいのだが写真のように中に何もなかったり、落ち葉が詰まっていたり、管だけ転がっていたりするものが半数以上だった。
若木保護のような人工物も点々と設置されている。古い道標らしいのだが写真のように中に何もなかったり、落ち葉が詰まっていたり、管だけ転がっていたりするものが半数以上だった。
 1
1
9/7 5:20
若木保護のような人工物も点々と設置されている。古い道標らしいのだが写真のように中に何もなかったり、落ち葉が詰まっていたり、管だけ転がっていたりするものが半数以上だった。
 大滝下流を見下ろす。斜面にはテンニンソウがびっしり。
大滝下流を見下ろす。斜面にはテンニンソウがびっしり。
 1
1
9/7 5:22
大滝下流を見下ろす。斜面にはテンニンソウがびっしり。
 鉄砲尾根の踏み跡はあったりなかったり。基本的には崖沿い・尾根通しに登っていけば問題ない。
鉄砲尾根の踏み跡はあったりなかったり。基本的には崖沿い・尾根通しに登っていけば問題ない。
 1
1
9/7 5:26
鉄砲尾根の踏み跡はあったりなかったり。基本的には崖沿い・尾根通しに登っていけば問題ない。
 こちらは「当たり」の道標。いつ頃設置されたものだろう。
こちらは「当たり」の道標。いつ頃設置されたものだろう。
 1
1
9/7 5:27
こちらは「当たり」の道標。いつ頃設置されたものだろう。
 所々に倒木があるので歩きやすい所を適当に処理していく。
所々に倒木があるので歩きやすい所を適当に処理していく。
 1
1
9/7 5:28
所々に倒木があるので歩きやすい所を適当に処理していく。
 <大滝雨量観測所>
<大滝雨量観測所>
取り付きから150mほど高度を上げると国交省の施設前に出た。この日は大沢近辺に職員の姿はなかった。
 1
1
9/7 5:33
<大滝雨量観測所>
取り付きから150mほど高度を上げると国交省の施設前に出た。この日は大沢近辺に職員の姿はなかった。
 テンニンソウ
テンニンソウ
 1
1
9/7 5:34
テンニンソウ
 樹間から見えるのは白根三山。
樹間から見えるのは白根三山。
 1
1
9/7 5:34
樹間から見えるのは白根三山。
 たまに崖側に出ることがあるので大沢を観察できる。上流で激しく崩れてもこの辺りまで土砂が流れてくることは少ないように見える。
たまに崖側に出ることがあるので大沢を観察できる。上流で激しく崩れてもこの辺りまで土砂が流れてくることは少ないように見える。
 1
1
9/7 5:35
たまに崖側に出ることがあるので大沢を観察できる。上流で激しく崩れてもこの辺りまで土砂が流れてくることは少ないように見える。
 露出したビニル管。
露出したビニル管。
 1
1
9/7 5:41
露出したビニル管。
 大滝雨量観測所を過ぎると徐々に傾斜が強まる。
大滝雨量観測所を過ぎると徐々に傾斜が強まる。
 1
1
9/7 5:59
大滝雨量観測所を過ぎると徐々に傾斜が強まる。
 樹間にちらちらと大沢崩れの稜線を見ながら登っていくと2150m付近でモノレールの軌道が現れる。人工物があるとほっとする。
樹間にちらちらと大沢崩れの稜線を見ながら登っていくと2150m付近でモノレールの軌道が現れる。人工物があるとほっとする。
 1
1
9/7 6:33
樹間にちらちらと大沢崩れの稜線を見ながら登っていくと2150m付近でモノレールの軌道が現れる。人工物があるとほっとする。
 すぐ上部には大沢崩れへの下降点も。
すぐ上部には大沢崩れへの下降点も。
 1
1
9/7 6:35
すぐ上部には大沢崩れへの下降点も。
 後は軌道に沿って登っていくだけ。
後は軌道に沿って登っていくだけ。
 1
1
9/7 6:37
後は軌道に沿って登っていくだけ。
 この辺りまで登ってくると大沢崩れに高度感が出て迫力が増す。
この辺りまで登ってくると大沢崩れに高度感が出て迫力が増す。
 1
1
9/7 6:39
この辺りまで登ってくると大沢崩れに高度感が出て迫力が増す。
 開けた所からついに大沢崩れを見る。大きすぎて現実感がない。
開けた所からついに大沢崩れを見る。大きすぎて現実感がない。
 1
1
9/7 6:39
開けた所からついに大沢崩れを見る。大きすぎて現実感がない。
 富士宮市方面がすっきりと見える。
富士宮市方面がすっきりと見える。
 1
1
9/7 6:42
富士宮市方面がすっきりと見える。
 モノレール下端以降は明瞭な作業道をいくつか見かけた。終盤はこれを追ったり軌道を右に左にくぐったりして高度を上げていった。
モノレール下端以降は明瞭な作業道をいくつか見かけた。終盤はこれを追ったり軌道を右に左にくぐったりして高度を上げていった。
 1
1
9/7 6:45
モノレール下端以降は明瞭な作業道をいくつか見かけた。終盤はこれを追ったり軌道を右に左にくぐったりして高度を上げていった。
 <大沢休泊所>
<大沢休泊所>
鉄砲尾根取り付きから2時間ほどで御中道・大沢休泊所に到着。難しい所はなかったが足元が安定しない箇所があったりして思ったよりも時間を取られた。
 1
1
9/7 6:52
<大沢休泊所>
鉄砲尾根取り付きから2時間ほどで御中道・大沢休泊所に到着。難しい所はなかったが足元が安定しない箇所があったりして思ったよりも時間を取られた。
 滑沢・一番沢が崩れているので見に来る人もまれな掲示物を眺める。
滑沢・一番沢が崩れているので見に来る人もまれな掲示物を眺める。
 1
1
9/7 6:53
滑沢・一番沢が崩れているので見に来る人もまれな掲示物を眺める。
 ミヤマセンキュウ?
ミヤマセンキュウ?
 1
1
9/7 6:54
ミヤマセンキュウ?
 アキノキリンソウ
アキノキリンソウ
 1
1
9/7 6:54
アキノキリンソウ
 ヤマトリカブト
ヤマトリカブト
 1
1
9/7 6:54
ヤマトリカブト
 休泊所前にある道標。
休泊所前にある道標。
 1
1
9/7 6:55
休泊所前にある道標。
 大沢崩れの標石も。
大沢崩れの標石も。
 1
1
9/7 6:55
大沢崩れの標石も。
 三柱神社に山行の無事を祈願して石段で休憩させてもらう。
三柱神社に山行の無事を祈願して石段で休憩させてもらう。
 1
1
9/7 6:55
三柱神社に山行の無事を祈願して石段で休憩させてもらう。
 大沢崩れ右岸ルートは三柱神社の裏手より。以前は山道だったが頑丈なアルミ梯子が設置されていた。
大沢崩れ右岸ルートは三柱神社の裏手より。以前は山道だったが頑丈なアルミ梯子が設置されていた。
 1
1
9/7 7:10
大沢崩れ右岸ルートは三柱神社の裏手より。以前は山道だったが頑丈なアルミ梯子が設置されていた。
 <御中道雨量観測所>
<御中道雨量観測所>
階段の先はもう一つの雨量観測所。
 1
1
9/7 7:11
<御中道雨量観測所>
階段の先はもう一つの雨量観測所。
 ダイモンジソウ
ダイモンジソウ
 1
1
9/7 7:12
ダイモンジソウ
 観測所裏からはいきなりシャクナゲの藪が広がる。藪とは言っても背丈よりも低くまだ若木なのでそこまで頑強な抵抗はない。
観測所裏からはいきなりシャクナゲの藪が広がる。藪とは言っても背丈よりも低くまだ若木なのでそこまで頑強な抵抗はない。
 1
1
9/7 7:13
観測所裏からはいきなりシャクナゲの藪が広がる。藪とは言っても背丈よりも低くまだ若木なのでそこまで頑強な抵抗はない。
 藪を抜けると左岸の「壁」が目の前に。スケールの大きさに言葉を失う。鉄砲尾根の途中なら大沢崩れも普通に越えられると思っていたけどここからなんて無理。
藪を抜けると左岸の「壁」が目の前に。スケールの大きさに言葉を失う。鉄砲尾根の途中なら大沢崩れも普通に越えられると思っていたけどここからなんて無理。
 1
1
9/7 7:18
藪を抜けると左岸の「壁」が目の前に。スケールの大きさに言葉を失う。鉄砲尾根の途中なら大沢崩れも普通に越えられると思っていたけどここからなんて無理。
 <見晴台>
<見晴台>
かつての御中道の渡渉点に出た。道標はまだまだ健在の様子。
 2
2
9/7 7:19
<見晴台>
かつての御中道の渡渉点に出た。道標はまだまだ健在の様子。
 見晴台から先が第一の難関。危険な崖沿いか藪かの選択を迫られる。
見晴台から先が第一の難関。危険な崖沿いか藪かの選択を迫られる。
 1
1
9/7 7:19
見晴台から先が第一の難関。危険な崖沿いか藪かの選択を迫られる。
 歩きやすいと思われた崖沿いも砂礫の不安定な足場が断続してうまく進めない。おまけに大岩を巻いたりするシーンもあったりしてルートファインディングに忙殺される。
歩きやすいと思われた崖沿いも砂礫の不安定な足場が断続してうまく進めない。おまけに大岩を巻いたりするシーンもあったりしてルートファインディングに忙殺される。
 2
2
9/7 7:23
歩きやすいと思われた崖沿いも砂礫の不安定な足場が断続してうまく進めない。おまけに大岩を巻いたりするシーンもあったりしてルートファインディングに忙殺される。
 灌木が無くなるまでは多少の不便さはあっても草付きを選んだほうが楽な事が多かった。
灌木が無くなるまでは多少の不便さはあっても草付きを選んだほうが楽な事が多かった。
 2
2
9/7 7:28
灌木が無くなるまでは多少の不便さはあっても草付きを選んだほうが楽な事が多かった。
 崖沿いはまだこのような結束の弱いスコリア帯になっていて足を取られがち。
崖沿いはまだこのような結束の弱いスコリア帯になっていて足を取られがち。
 1
1
9/7 7:34
崖沿いはまだこのような結束の弱いスコリア帯になっていて足を取られがち。
 灌木帯ぎりぎりを進むのも枯木が行く手を阻むので今一つだった。
灌木帯ぎりぎりを進むのも枯木が行く手を阻むので今一つだった。
 1
1
9/7 7:42
灌木帯ぎりぎりを進むのも枯木が行く手を阻むので今一つだった。
 ヤハズヒゴタイ
ヤハズヒゴタイ
 1
1
9/7 7:45
ヤハズヒゴタイ
 地味に岩場を越えるシーンもあり左手の樹林帯を突破した方が苦労は少なかったかもしれない。
地味に岩場を越えるシーンもあり左手の樹林帯を突破した方が苦労は少なかったかもしれない。
 1
1
9/7 8:15
地味に岩場を越えるシーンもあり左手の樹林帯を突破した方が苦労は少なかったかもしれない。
 振り返ると南アルプス南端から、
振り返ると南アルプス南端から、
 1
1
9/7 8:23
振り返ると南アルプス南端から、
 北端に到る稜線を一望。本栖湖も見えた。
北端に到る稜線を一望。本栖湖も見えた。
 1
1
9/7 8:23
北端に到る稜線を一望。本栖湖も見えた。
 八ヶ岳が小さく見えるほどの絶景に思わず溜息をつく。
八ヶ岳が小さく見えるほどの絶景に思わず溜息をつく。
 1
1
9/7 8:23
八ヶ岳が小さく見えるほどの絶景に思わず溜息をつく。
 岩場に出た。ザレを避けこの上に登って進む。
岩場に出た。ザレを避けこの上に登って進む。
 1
1
9/7 8:31
岩場に出た。ザレを避けこの上に登って進む。
 標高2600mを超えた。左岸の方はそろそろ灌木帯が途切れる。
標高2600mを超えた。左岸の方はそろそろ灌木帯が途切れる。
 2
2
9/7 8:34
標高2600mを超えた。左岸の方はそろそろ灌木帯が途切れる。
 こちらはまだ灌木の中の岩登り。古いマーキングは概ね有効だがこのルートではあくまでも目安。
こちらはまだ灌木の中の岩登り。古いマーキングは概ね有効だがこのルートではあくまでも目安。
 2
2
9/7 8:37
こちらはまだ灌木の中の岩登り。古いマーキングは概ね有効だがこのルートではあくまでも目安。
 中くらいの小石が最もバランスを崩しやすい。よって景色がいいのに藪に入ることを余儀なくされしばらく歯がゆい思いをする。
中くらいの小石が最もバランスを崩しやすい。よって景色がいいのに藪に入ることを余儀なくされしばらく歯がゆい思いをする。
 1
1
9/7 8:43
中くらいの小石が最もバランスを崩しやすい。よって景色がいいのに藪に入ることを余儀なくされしばらく歯がゆい思いをする。
 カラマツ<シャクナゲ<<<古木の順に頑強。それでも先人の踏み跡などのお陰で薮漕ぎとまではいかないのが救い。
カラマツ<シャクナゲ<<<古木の順に頑強。それでも先人の踏み跡などのお陰で薮漕ぎとまではいかないのが救い。
 1
1
9/7 8:45
カラマツ<シャクナゲ<<<古木の順に頑強。それでも先人の踏み跡などのお陰で薮漕ぎとまではいかないのが救い。
 溶岩に空いた穴から大沢崩れを見る。さしずめ右岸の胎内くぐり。
溶岩に空いた穴から大沢崩れを見る。さしずめ右岸の胎内くぐり。
 2
2
9/7 8:51
溶岩に空いた穴から大沢崩れを見る。さしずめ右岸の胎内くぐり。
 崩落部辺縁では時折人工物を見掛ける。これは平成19年のものなので比較的新しい。右岸は崩壊の影響が割と少ないそうなのでしばらくは道標代わりになってくれるのだろう。
崩落部辺縁では時折人工物を見掛ける。これは平成19年のものなので比較的新しい。右岸は崩壊の影響が割と少ないそうなのでしばらくは道標代わりになってくれるのだろう。
 2
2
9/7 8:52
崩落部辺縁では時折人工物を見掛ける。これは平成19年のものなので比較的新しい。右岸は崩壊の影響が割と少ないそうなのでしばらくは道標代わりになってくれるのだろう。
 2800m位で灌木帯も概ね切れた。後は遠くに見える頂上を目指してひたすらの登りが続く。
2800m位で灌木帯も概ね切れた。後は遠くに見える頂上を目指してひたすらの登りが続く。
 1
1
9/7 9:01
2800m位で灌木帯も概ね切れた。後は遠くに見える頂上を目指してひたすらの登りが続く。
 登ってきた大沢右岸を眺める。
登ってきた大沢右岸を眺める。
 1
1
9/7 9:10
登ってきた大沢右岸を眺める。
 このルートにはヤマトリカブトが多い。最後の木陰で休憩して出発。
このルートにはヤマトリカブトが多い。最後の木陰で休憩して出発。
 1
1
9/7 9:11
このルートにはヤマトリカブトが多い。最後の木陰で休憩して出発。
 2900mを超えた所で完全に灌木帯を抜けた。積極的に岩を足場に選んで進んでいく。
2900mを超えた所で完全に灌木帯を抜けた。積極的に岩を足場に選んで進んでいく。
 1
1
9/7 9:15
2900mを超えた所で完全に灌木帯を抜けた。積極的に岩を足場に選んで進んでいく。
 北からは一番沢の岸が徐々に近づいてくる。
北からは一番沢の岸が徐々に近づいてくる。
 1
1
9/7 9:22
北からは一番沢の岸が徐々に近づいてくる。
 岩場の上を進んでいるところ。大沢からは絶えず土煙が上がっているがこの日は落石の音は聞こえなかった。右端は源頭部、その上が山頂となる。近いようだがこの後一向に近付いてこない。
岩場の上を進んでいるところ。大沢からは絶えず土煙が上がっているがこの日は落石の音は聞こえなかった。右端は源頭部、その上が山頂となる。近いようだがこの後一向に近付いてこない。
 1
1
9/7 9:24
岩場の上を進んでいるところ。大沢からは絶えず土煙が上がっているがこの日は落石の音は聞こえなかった。右端は源頭部、その上が山頂となる。近いようだがこの後一向に近付いてこない。
 まだちらほらとペイントがある。
まだちらほらとペイントがある。
 1
1
9/7 9:25
まだちらほらとペイントがある。
 大丈夫だろうと思って足を掛けた溶岩ブロックがごっそり動いて肝を冷やす。重さは100Kg近くあるのではないだろうか。
大丈夫だろうと思って足を掛けた溶岩ブロックがごっそり動いて肝を冷やす。重さは100Kg近くあるのではないだろうか。
 1
1
9/7 9:27
大丈夫だろうと思って足を掛けた溶岩ブロックがごっそり動いて肝を冷やす。重さは100Kg近くあるのではないだろうか。
 ずっと巨大な左岸のギャップを見せられて遠近感が狂ってくる。気付いたのは対して右岸の方は割と簡単に沢床に下りられそうだということ。砂礫地獄にハマるのでやらないけれど。
ずっと巨大な左岸のギャップを見せられて遠近感が狂ってくる。気付いたのは対して右岸の方は割と簡単に沢床に下りられそうだということ。砂礫地獄にハマるのでやらないけれど。
 1
1
9/7 9:32
ずっと巨大な左岸のギャップを見せられて遠近感が狂ってくる。気付いたのは対して右岸の方は割と簡単に沢床に下りられそうだということ。砂礫地獄にハマるのでやらないけれど。
 3000mを過ぎて最初の岩場。するする登れるのが楽しくて先をよく観察せずに登ってしまった。
3000mを過ぎて最初の岩場。するする登れるのが楽しくて先をよく観察せずに登ってしまった。
 1
1
9/7 9:35
3000mを過ぎて最初の岩場。するする登れるのが楽しくて先をよく観察せずに登ってしまった。
 岩場の端にはミヤマハナゴケのコロニー。僅かな水分が得られるのか高山植物も広がっていて美しい。
岩場の端にはミヤマハナゴケのコロニー。僅かな水分が得られるのか高山植物も広がっていて美しい。
 1
1
9/7 9:36
岩場の端にはミヤマハナゴケのコロニー。僅かな水分が得られるのか高山植物も広がっていて美しい。
 イワヒゲも咲いていた。
イワヒゲも咲いていた。
 1
1
9/7 9:36
イワヒゲも咲いていた。
 岩場の先は切れていて進めない。途中まで戻って北から下りようとしても危なっかしいギャップがあり飛び降りることもできない。
岩場の先は切れていて進めない。途中まで戻って北から下りようとしても危なっかしいギャップがあり飛び降りることもできない。
 1
1
9/7 9:37
岩場の先は切れていて進めない。途中まで戻って北から下りようとしても危なっかしいギャップがあり飛び降りることもできない。
 行きつ戻りつの思案の後写真正面のオーバーハングした岩場をクライムダウンした。
行きつ戻りつの思案の後写真正面のオーバーハングした岩場をクライムダウンした。
 1
1
9/7 9:44
行きつ戻りつの思案の後写真正面のオーバーハングした岩場をクライムダウンした。
 そんな事があったもんだから次の岩場は登らず大沢側に巻いたが浮きの多いガレで却って歩き辛い。
そんな事があったもんだから次の岩場は登らず大沢側に巻いたが浮きの多いガレで却って歩き辛い。
 1
1
9/7 9:50
そんな事があったもんだから次の岩場は登らず大沢側に巻いたが浮きの多いガレで却って歩き辛い。
 途中で岩に乗ることにしたけど高度感はあるしざらついた部分の岩は脆いわで危なかった。
途中で岩に乗ることにしたけど高度感はあるしざらついた部分の岩は脆いわで危なかった。
 1
1
9/7 9:53
途中で岩に乗ることにしたけど高度感はあるしざらついた部分の岩は脆いわで危なかった。
 とはいえ岩場を歩いたほうが圧倒的に楽なので退路を確保しつつ岩に足を掛けていく。
とはいえ岩場を歩いたほうが圧倒的に楽なので退路を確保しつつ岩に足を掛けていく。
 1
1
9/7 10:00
とはいえ岩場を歩いたほうが圧倒的に楽なので退路を確保しつつ岩に足を掛けていく。
 仏像のような岩を見ながら岩盤の脇を進む。
仏像のような岩を見ながら岩盤の脇を進む。
 2
2
9/7 10:04
仏像のような岩を見ながら岩盤の脇を進む。
 主杖流しでも見る溶岩流の跡がたまに右岸でも観察できる。
主杖流しでも見る溶岩流の跡がたまに右岸でも観察できる。
 1
1
9/7 10:12
主杖流しでも見る溶岩流の跡がたまに右岸でも観察できる。
 砂礫をえっちら登っていたらこんな所にシカかカモシカの足跡が。
砂礫をえっちら登っていたらこんな所にシカかカモシカの足跡が。
 1
1
9/7 10:18
砂礫をえっちら登っていたらこんな所にシカかカモシカの足跡が。
 オンタデの草紅葉がもう始まっている。
オンタデの草紅葉がもう始まっている。
 1
1
9/7 10:23
オンタデの草紅葉がもう始まっている。
 大沢崩れ源頭部を見上げる。左岸と大沢の地層が大きく異なるのが興味深い。
大沢崩れ源頭部を見上げる。左岸と大沢の地層が大きく異なるのが興味深い。
 2
2
9/7 10:25
大沢崩れ源頭部を見上げる。左岸と大沢の地層が大きく異なるのが興味深い。
 朝霧高原に広がった雲がゆっくりと昇ってきた。逃げ切りたいところだけど10歩進んだら息切れするような高度まで来てしまったので祈りながら登るしかない。
朝霧高原に広がった雲がゆっくりと昇ってきた。逃げ切りたいところだけど10歩進んだら息切れするような高度まで来てしまったので祈りながら登るしかない。
 1
1
9/7 10:47
朝霧高原に広がった雲がゆっくりと昇ってきた。逃げ切りたいところだけど10歩進んだら息切れするような高度まで来てしまったので祈りながら登るしかない。
 右岸の縁に突き出た大岩を左(北側)に迂回。右奥の城塞のような岩壁が剣ヶ峰、中央に小さく頭を出しているのが雷岩。
右岸の縁に突き出た大岩を左(北側)に迂回。右奥の城塞のような岩壁が剣ヶ峰、中央に小さく頭を出しているのが雷岩。
 1
1
9/7 11:00
右岸の縁に突き出た大岩を左(北側)に迂回。右奥の城塞のような岩壁が剣ヶ峰、中央に小さく頭を出しているのが雷岩。
 斜面の向こうに河口湖が見えた。こちらは晴れていて河口湖大橋までくっきり。
斜面の向こうに河口湖が見えた。こちらは晴れていて河口湖大橋までくっきり。
 1
1
9/7 11:05
斜面の向こうに河口湖が見えた。こちらは晴れていて河口湖大橋までくっきり。
 右岸の縁。これだけ近づくのに10分近くも掛かる。
右岸の縁。これだけ近づくのに10分近くも掛かる。
 1
1
9/7 11:09
右岸の縁。これだけ近づくのに10分近くも掛かる。
 大岩を巻いた3450m付近から砂礫歩きとなる。ここからしばらくは岩場が出ても浅かったりして我慢の登りが続く。
大岩を巻いた3450m付近から砂礫歩きとなる。ここからしばらくは岩場が出ても浅かったりして我慢の登りが続く。
 1
1
9/7 11:15
大岩を巻いた3450m付近から砂礫歩きとなる。ここからしばらくは岩場が出ても浅かったりして我慢の登りが続く。
 右岸の縁に立つ。
右岸の縁に立つ。
 1
1
9/7 11:29
右岸の縁に立つ。
 岩場を見付けたので良かれと昇っていくとまたここでも先で下降する羽目に。ここは岩が脆くて危険だった。
岩場を見付けたので良かれと昇っていくとまたここでも先で下降する羽目に。ここは岩が脆くて危険だった。
 1
1
9/7 11:43
岩場を見付けたので良かれと昇っていくとまたここでも先で下降する羽目に。ここは岩が脆くて危険だった。
 滑沢と合流しスラブの頂点へ向けて高度を上げていく。
滑沢と合流しスラブの頂点へ向けて高度を上げていく。
 1
1
9/7 11:46
滑沢と合流しスラブの頂点へ向けて高度を上げていく。
 スラブ対岸の尾根を詰めていくと岩壁が立ちふさがる。9年前と同様に正面のスリットを横断してここから見えるお鉢の鞍部を目指すのだけど右手から岩場を登っても良かったかもしれない。
スラブ対岸の尾根を詰めていくと岩壁が立ちふさがる。9年前と同様に正面のスリットを横断してここから見えるお鉢の鞍部を目指すのだけど右手から岩場を登っても良かったかもしれない。
 1
1
9/7 11:56
スラブ対岸の尾根を詰めていくと岩壁が立ちふさがる。9年前と同様に正面のスリットを横断してここから見えるお鉢の鞍部を目指すのだけど右手から岩場を登っても良かったかもしれない。
 スリットは傾斜したザレで状態は良くない。グローブに穴が開くようなざらついた岩場に手を掛けてへつるようにして渡った。
スリットは傾斜したザレで状態は良くない。グローブに穴が開くようなざらついた岩場に手を掛けてへつるようにして渡った。
 1
1
9/7 12:02
スリットは傾斜したザレで状態は良くない。グローブに穴が開くようなざらついた岩場に手を掛けてへつるようにして渡った。
 ちなみにこの岩場は結構な量の水が滴り落ちていて氷を見ることができた。
ちなみにこの岩場は結構な量の水が滴り落ちていて氷を見ることができた。
 1
1
9/7 12:05
ちなみにこの岩場は結構な量の水が滴り落ちていて氷を見ることができた。
 後は適当な足場を探して頂上まで這い上がる。見上げるとお鉢巡りをする人たち。
後は適当な足場を探して頂上まで這い上がる。見上げるとお鉢巡りをする人たち。
 1
1
9/7 12:11
後は適当な足場を探して頂上まで這い上がる。見上げるとお鉢巡りをする人たち。
 予定よりも少し遅くなったけどお鉢に合流。ずっと絶景を見ながら歩いてきたけどやっぱりお鉢の風景は何度見ても圧倒される。
予定よりも少し遅くなったけどお鉢に合流。ずっと絶景を見ながら歩いてきたけどやっぱりお鉢の風景は何度見ても圧倒される。
 2
2
9/7 12:19
予定よりも少し遅くなったけどお鉢に合流。ずっと絶景を見ながら歩いてきたけどやっぱりお鉢の風景は何度見ても圧倒される。
 大沢崩れ源頭部付近より登ってきた谷を見下ろす。やっぱりスケールが大きすぎて達成感というか現実感がついてこない。
大沢崩れ源頭部付近より登ってきた谷を見下ろす。やっぱりスケールが大きすぎて達成感というか現実感がついてこない。
 2
2
9/7 12:20
大沢崩れ源頭部付近より登ってきた谷を見下ろす。やっぱりスケールが大きすぎて達成感というか現実感がついてこない。
 写真待ちの行列には加わらず頂上へ。
写真待ちの行列には加わらず頂上へ。
 1
1
9/7 12:28
写真待ちの行列には加わらず頂上へ。
 <富士山頂剣ヶ峰>
<富士山頂剣ヶ峰>
今年も無事山頂に立てた。感無量とはこのこと。
 1
1
9/7 12:37
<富士山頂剣ヶ峰>
今年も無事山頂に立てた。感無量とはこのこと。
 大内院を覗き込む。
大内院を覗き込む。
 1
1
9/7 12:38
大内院を覗き込む。
 お鉢をパノラマで。八葉蓮華と呼ばれるのも頷ける。
お鉢をパノラマで。八葉蓮華と呼ばれるのも頷ける。
 1
1
9/7 12:38
お鉢をパノラマで。八葉蓮華と呼ばれるのも頷ける。
 二等三角点「富士山」
二等三角点「富士山」
最新の測量で5cm程高くなった。
 1
1
9/7 12:55
二等三角点「富士山」
最新の測量で5cm程高くなった。
 下りは時計回りで。大沢崩れ左岸は山頂まで崩壊壁が続いているんだ。
下りは時計回りで。大沢崩れ左岸は山頂まで崩壊壁が続いているんだ。
 1
1
9/7 13:01
下りは時計回りで。大沢崩れ左岸は山頂まで崩壊壁が続いているんだ。
 予定にはなかったけど釈迦の割石があまりにも格好良くて白山岳にも登ることにした。
予定にはなかったけど釈迦の割石があまりにも格好良くて白山岳にも登ることにした。
 1
1
9/7 13:05
予定にはなかったけど釈迦の割石があまりにも格好良くて白山岳にも登ることにした。
 白山岳への道はなんとなく右岸の登りに似ている。
白山岳への道はなんとなく右岸の登りに似ている。
 1
1
9/7 13:09
白山岳への道はなんとなく右岸の登りに似ている。
 河口湖を見ながらの贅沢な登り。
河口湖を見ながらの贅沢な登り。
 1
1
9/7 13:10
河口湖を見ながらの贅沢な登り。
 久須志岳・成就岳。時折振り返っては元気をもらった。
久須志岳・成就岳。時折振り返っては元気をもらった。
 1
1
9/7 13:13
久須志岳・成就岳。時折振り返っては元気をもらった。
 <白山岳山頂>
<白山岳山頂>
大盛況の剣ヶ峰に比べこちらは自分ひとり。
 2
2
9/7 13:16
<白山岳山頂>
大盛況の剣ヶ峰に比べこちらは自分ひとり。
 かと思ったらこんな所にヤマネがいた。
かと思ったらこんな所にヤマネがいた。
 1
1
9/7 13:17
かと思ったらこんな所にヤマネがいた。
 白山岳から望む剣ヶ峰。
白山岳から望む剣ヶ峰。
 1
1
9/7 13:18
白山岳から望む剣ヶ峰。
 二等三角点「富士白山」
二等三角点「富士白山」
 1
1
9/7 13:19
二等三角点「富士白山」
 精進湖方面は雲が多め。
精進湖方面は雲が多め。
 1
1
9/7 13:20
精進湖方面は雲が多め。
 河口湖と三坂山地
河口湖と三坂山地
 1
1
9/7 13:20
河口湖と三坂山地
 山中湖。この辺りだと富士山が一番天気が良かったみたい。
山中湖。この辺りだと富士山が一番天気が良かったみたい。
 1
1
9/7 13:20
山中湖。この辺りだと富士山が一番天気が良かったみたい。
 白山岳を下りて吉田/須走口の頂上へ。
白山岳を下りて吉田/須走口の頂上へ。
 1
1
9/7 13:27
白山岳を下りて吉田/須走口の頂上へ。
 <吉田口/須走口下山口>
<吉田口/須走口下山口>
今回は須走口へ向けて下山。
 1
1
9/7 13:29
<吉田口/須走口下山口>
今回は須走口へ向けて下山。
 最後にお鉢を見ておく。また来年。
最後にお鉢を見ておく。また来年。
 1
1
9/7 13:29
最後にお鉢を見ておく。また来年。
 雲の絨毯を目指して下降。
雲の絨毯を目指して下降。
 1
1
9/7 13:40
雲の絨毯を目指して下降。
 雄大な景色を楽しみながら軽快に下っていく。砂礫は登りでは苦難そのものだけど下りでうまく使えばいいクッション。
雄大な景色を楽しみながら軽快に下っていく。砂礫は登りでは苦難そのものだけど下りでうまく使えばいいクッション。
 1
1
9/7 13:48
雄大な景色を楽しみながら軽快に下っていく。砂礫は登りでは苦難そのものだけど下りでうまく使えばいいクッション。
 <八合目下江戸屋分岐>
<八合目下江戸屋分岐>
ここで須走口コースへ。
 1
1
9/7 13:58
<八合目下江戸屋分岐>
ここで須走口コースへ。
 吉田口側には「※通行料がかかります」の文字。
吉田口側には「※通行料がかかります」の文字。
 1
1
9/7 13:58
吉田口側には「※通行料がかかります」の文字。
 下り始めると斜面にちょっとした溶岩流の跡が。
下り始めると斜面にちょっとした溶岩流の跡が。
 1
1
9/7 14:04
下り始めると斜面にちょっとした溶岩流の跡が。
 <本七合 見晴館>
<本七合 見晴館>
次の小屋では登下山道が分岐。
 1
1
9/7 14:05
<本七合 見晴館>
次の小屋では登下山道が分岐。
 小屋の下にははっきりとした溶岩流跡が続いている。
小屋の下にははっきりとした溶岩流跡が続いている。
 1
1
9/7 14:06
小屋の下にははっきりとした溶岩流跡が続いている。
 分岐からしばらく段差のある岩混じりの下りにくい道が続く。
分岐からしばらく段差のある岩混じりの下りにくい道が続く。
 1
1
9/7 14:06
分岐からしばらく段差のある岩混じりの下りにくい道が続く。
 七合目太陽館の手前まで下りてきた。山頂がもうあんなに遠い。
七合目太陽館の手前まで下りてきた。山頂がもうあんなに遠い。
 1
1
9/7 14:17
七合目太陽館の手前まで下りてきた。山頂がもうあんなに遠い。
 以前登った時はこんな注連縄の岩なんてあったっけ。
以前登った時はこんな注連縄の岩なんてあったっけ。
 1
1
9/7 14:25
以前登った時はこんな注連縄の岩なんてあったっけ。
 大沢崩れ右岸にはほとんど見られなかったオノエイタドリが多い。
大沢崩れ右岸にはほとんど見られなかったオノエイタドリが多い。
 1
1
9/7 14:26
大沢崩れ右岸にはほとんど見られなかったオノエイタドリが多い。
 ゲイターを着けて砂走りまでトラバースしていく。午後に発生した雲がせり上がってきた。
ゲイターを着けて砂走りまでトラバースしていく。午後に発生した雲がせり上がってきた。
 1
1
9/7 14:27
ゲイターを着けて砂走りまでトラバースしていく。午後に発生した雲がせり上がってきた。
 <砂走り>
<砂走り>
案の定雲を突っ切るような下り坂に。日帰りで富士登山をすると大体このパターンになる。
 1
1
9/7 14:29
<砂走り>
案の定雲を突っ切るような下り坂に。日帰りで富士登山をすると大体このパターンになる。
 まだ先は長いので走らずざくざくと足裏を滑らせるようにして下りて行く。
まだ先は長いので走らずざくざくと足裏を滑らせるようにして下りて行く。
 1
1
9/7 14:31
まだ先は長いので走らずざくざくと足裏を滑らせるようにして下りて行く。
 メイゲツソウ
メイゲツソウ
 1
1
9/7 14:41
メイゲツソウ
 砂払五合までは一気に600m高度を落とす。やっぱり見えているのに遠くてなかなか近付いてこない。
砂払五合までは一気に600m高度を落とす。やっぱり見えているのに遠くてなかなか近付いてこない。
 1
1
9/7 14:42
砂払五合までは一気に600m高度を落とす。やっぱり見えているのに遠くてなかなか近付いてこない。
 <砂払五合目 吉野家>
<砂払五合目 吉野家>
最後の小屋を通過。
 1
1
9/7 14:48
<砂払五合目 吉野家>
最後の小屋を通過。
 下りてくるとまた青空が見え始めた。曇っていたら小富士は諦めて須走五合目ゴールにしようかと思っていた。
下りてくるとまた青空が見え始めた。曇っていたら小富士は諦めて須走五合目ゴールにしようかと思っていた。
 1
1
9/7 14:49
下りてくるとまた青空が見え始めた。曇っていたら小富士は諦めて須走五合目ゴールにしようかと思っていた。
 小休止し五合目に向けて下山を再開。背後で五合目まであと2kmもあるのねという声を聴く。そう、ここからもそれなりに下るんだった。
小休止し五合目に向けて下山を再開。背後で五合目まであと2kmもあるのねという声を聴く。そう、ここからもそれなりに下るんだった。
 1
1
9/7 14:49
小休止し五合目に向けて下山を再開。背後で五合目まであと2kmもあるのねという声を聴く。そう、ここからもそれなりに下るんだった。
 樹林帯に入り高度を落としていく。この辺りまで来ると砂礫が薄くブレーキが掛けづらくなっているのでついつい足裏に力が入り靴の中に熱が溜まってくる。
樹林帯に入り高度を落としていく。この辺りまで来ると砂礫が薄くブレーキが掛けづらくなっているのでついつい足裏に力が入り靴の中に熱が溜まってくる。
 1
1
9/7 14:53
樹林帯に入り高度を落としていく。この辺りまで来ると砂礫が薄くブレーキが掛けづらくなっているのでついつい足裏に力が入り靴の中に熱が溜まってくる。
 ダケカンバの美しい森。須走口が森の登山道と言われる所以だ。
ダケカンバの美しい森。須走口が森の登山道と言われる所以だ。
 1
1
9/7 14:53
ダケカンバの美しい森。須走口が森の登山道と言われる所以だ。
 <分岐>
<分岐>
砂払五合目から150mほど高度を落とすと登山道と合流。ここから下は普通に岩の多い登山道。
 1
1
9/7 14:54
<分岐>
砂払五合目から150mほど高度を落とすと登山道と合流。ここから下は普通に岩の多い登山道。
 <古御嶽神社>
<古御嶽神社>
この時間から登り始めるハイカーとすれ違いながら五合目の喉元まで下りてきた。大沢休泊所の三柱神社とは山頂を挟んで正反対に位置するが古御嶽の神様に無事の下山を報告した。
 2
2
9/7 15:04
<古御嶽神社>
この時間から登り始めるハイカーとすれ違いながら五合目の喉元まで下りてきた。大沢休泊所の三柱神社とは山頂を挟んで正反対に位置するが古御嶽の神様に無事の下山を報告した。
 古御嶽神社の正面から富士箱根トレイルに入り小富士へのルートへ合流する。道はしっとりとしていて滑りやすいが非常に明瞭。
古御嶽神社の正面から富士箱根トレイルに入り小富士へのルートへ合流する。道はしっとりとしていて滑りやすいが非常に明瞭。
 1
1
9/7 15:07
古御嶽神社の正面から富士箱根トレイルに入り小富士へのルートへ合流する。道はしっとりとしていて滑りやすいが非常に明瞭。
 <分岐>
<分岐>
五合目との分岐に出た。ここから小富士まで整備された道が続く。
 1
1
9/7 15:09
<分岐>
五合目との分岐に出た。ここから小富士まで整備された道が続く。
 ガイドロープまでついて判りやすい。アップダウンもほとんどなく遊歩道と呼んでも差し支えないのだけど鬱蒼とした森を延々歩かされるのでちょっと不安になり熊鈴を出した。
ガイドロープまでついて判りやすい。アップダウンもほとんどなく遊歩道と呼んでも差し支えないのだけど鬱蒼とした森を延々歩かされるのでちょっと不安になり熊鈴を出した。
 1
1
9/7 15:13
ガイドロープまでついて判りやすい。アップダウンもほとんどなく遊歩道と呼んでも差し支えないのだけど鬱蒼とした森を延々歩かされるのでちょっと不安になり熊鈴を出した。
 斜面上にある大岩が社殿跡に見えたりトレイル脇の岩が石仏に見えたりし始めた。寝不足かな。
斜面上にある大岩が社殿跡に見えたりトレイル脇の岩が石仏に見えたりし始めた。寝不足かな。
 2
2
9/7 15:15
斜面上にある大岩が社殿跡に見えたりトレイル脇の岩が石仏に見えたりし始めた。寝不足かな。
 森が明るくなり始めた。
森が明るくなり始めた。
 1
1
9/7 15:17
森が明るくなり始めた。
 突然樹林帯が切れて砂礫の広場に飛び出し呆気にとられる。
突然樹林帯が切れて砂礫の広場に飛び出し呆気にとられる。
 1
1
9/7 15:18
突然樹林帯が切れて砂礫の広場に飛び出し呆気にとられる。
 <小富士>
<小富士>
正面に見えていた塚ではなくさらに北東の小丘がどうやら小富士と呼ばれる場所らしい。こんなにも広々とした場所だったとは。
 1
1
9/7 15:19
<小富士>
正面に見えていた塚ではなくさらに北東の小丘がどうやら小富士と呼ばれる場所らしい。こんなにも広々とした場所だったとは。
 石積みの上には祠も祀られている。
石積みの上には祠も祀られている。
 1
1
9/7 15:19
石積みの上には祠も祀られている。
 振り返ると雲を纏い後光を背負った富士山の姿が小富士に重なっていた。
振り返ると雲を纏い後光を背負った富士山の姿が小富士に重なっていた。
 1
1
9/7 15:20
振り返ると雲を纏い後光を背負った富士山の姿が小富士に重なっていた。
 神々しい……。
神々しい……。
 1
1
9/7 15:20
神々しい……。
 フジアザミ
フジアザミ
 1
1
9/7 15:22
フジアザミ
 小富士から林道への下りはまた負担の強い樹林帯の下りかと思いきや砂礫の坂道が続いていた。
小富士から林道への下りはまた負担の強い樹林帯の下りかと思いきや砂礫の坂道が続いていた。
 1
1
9/7 15:23
小富士から林道への下りはまた負担の強い樹林帯の下りかと思いきや砂礫の坂道が続いていた。
 マーキングだけでなくケルンもあるので安心。というか砂礫の尾根先を目指すだけなので迷いようがない。
マーキングだけでなくケルンもあるので安心。というか砂礫の尾根先を目指すだけなので迷いようがない。
 1
1
9/7 15:23
マーキングだけでなくケルンもあるので安心。というか砂礫の尾根先を目指すだけなので迷いようがない。
 天気が良ければ山中湖を眺めながら下りて行ける。砂礫は深めでリッチな感触を楽しめるし、何より2000mもあるので涼しい。こんなにも良い所があったのかと感動しながらにこにこしながらカラマツの林道を目指した。
天気が良ければ山中湖を眺めながら下りて行ける。砂礫は深めでリッチな感触を楽しめるし、何より2000mもあるので涼しい。こんなにも良い所があったのかと感動しながらにこにこしながらカラマツの林道を目指した。
 1
1
9/7 15:24
天気が良ければ山中湖を眺めながら下りて行ける。砂礫は深めでリッチな感触を楽しめるし、何より2000mもあるので涼しい。こんなにも良い所があったのかと感動しながらにこにこしながらカラマツの林道を目指した。
 樹林帯に入ったところが林道終点。どうやら未舗装のようだ。それにここまで下った足跡も薄かった。
樹林帯に入ったところが林道終点。どうやら未舗装のようだ。それにここまで下った足跡も薄かった。
 1
1
9/7 15:29
樹林帯に入ったところが林道終点。どうやら未舗装のようだ。それにここまで下った足跡も薄かった。
 <林道小富士線終点>
<林道小富士線終点>
ロープが張ってあるのは車両の進入防止のためらしい。
 1
1
9/7 15:29
<林道小富士線終点>
ロープが張ってあるのは車両の進入防止のためらしい。
 ここからは長い林道歩き。轍はあるものの倒木がいくつもあり暫く使われていないことが判る。ただ状態は概ね良い。
ここからは長い林道歩き。轍はあるものの倒木がいくつもあり暫く使われていないことが判る。ただ状態は概ね良い。
 1
1
9/7 15:34
ここからは長い林道歩き。轍はあるものの倒木がいくつもあり暫く使われていないことが判る。ただ状態は概ね良い。
 一箇所、1772m点の手前だけ崩壊したような大倒木帯がある。ただ、ここは西側に迂回する踏み跡があった。
一箇所、1772m点の手前だけ崩壊したような大倒木帯がある。ただ、ここは西側に迂回する踏み跡があった。
 1
1
9/7 15:38
一箇所、1772m点の手前だけ崩壊したような大倒木帯がある。ただ、ここは西側に迂回する踏み跡があった。
 <林道富士山中線終点>
<林道富士山中線終点>
一旦舗装路に出てほっとするがこれは別の林道との交点ですぐまた未舗装路に突入する。
 1
1
9/7 15:50
<林道富士山中線終点>
一旦舗装路に出てほっとするがこれは別の林道との交点ですぐまた未舗装路に突入する。
 以降はたまに倒木がある程度で、それも迂回の踏み跡で避けられる。ただ景色は開けないので単調な下りが続いた。
以降はたまに倒木がある程度で、それも迂回の踏み跡で避けられる。ただ景色は開けないので単調な下りが続いた。
 1
1
9/7 15:52
以降はたまに倒木がある程度で、それも迂回の踏み跡で避けられる。ただ景色は開けないので単調な下りが続いた。
 緑に埋もれつつある砂防堰堤。
緑に埋もれつつある砂防堰堤。
 1
1
9/7 16:01
緑に埋もれつつある砂防堰堤。
 <林道小富士線起点>
<林道小富士線起点>
まぁ大方の予想はついていたけど小富士林道は閉鎖されていた。小富士前後のあの美しい風景は徒歩者だけのものという事だ。ゲートの先からは滝沢林道の舗装路となっている。
 1
1
9/7 16:10
<林道小富士線起点>
まぁ大方の予想はついていたけど小富士林道は閉鎖されていた。小富士前後のあの美しい風景は徒歩者だけのものという事だ。ゲートの先からは滝沢林道の舗装路となっている。
 <新屋山神社 奥宮>
<新屋山神社 奥宮>
小富士林道起点のすぐ先に鎮座する金運の神様。日も暮れ始めた時間だけど県外ナンバーの車が何台もここを目指して登ってきていた。
 1
1
9/7 16:14
<新屋山神社 奥宮>
小富士林道起点のすぐ先に鎮座する金運の神様。日も暮れ始めた時間だけど県外ナンバーの車が何台もここを目指して登ってきていた。
 後は予定していた中の茶屋まで舗装路をひたすら歩いた。
後は予定していた中の茶屋まで舗装路をひたすら歩いた。
 1
1
9/7 17:08
後は予定していた中の茶屋まで舗装路をひたすら歩いた。
 道中山野草もたくさん咲いていたのだけど撮る気にもなれず黙々と下って行った。写真はこの辺りは秋になるとカラマツの黄葉が綺麗だろうなと思ってシャッターを切っただろう一枚。
道中山野草もたくさん咲いていたのだけど撮る気にもなれず黙々と下って行った。写真はこの辺りは秋になるとカラマツの黄葉が綺麗だろうなと思ってシャッターを切っただろう一枚。
 1
1
9/7 17:26
道中山野草もたくさん咲いていたのだけど撮る気にもなれず黙々と下って行った。写真はこの辺りは秋になるとカラマツの黄葉が綺麗だろうなと思ってシャッターを切っただろう一枚。
 <中の茶屋>
<中の茶屋>
富士講碑の立ち並ぶ中の茶屋で行動終了。タクシーを呼んで河口湖まで運んでもらった。
 1
1
9/7 17:45
<中の茶屋>
富士講碑の立ち並ぶ中の茶屋で行動終了。タクシーを呼んで河口湖まで運んでもらった。
 河口湖駅より。2025年の富士登山シーズン最後の土日はいい天気だった。来年はどのルートで登ろうか。
河口湖駅より。2025年の富士登山シーズン最後の土日はいい天気だった。来年はどのルートで登ろうか。
 1
1
9/7 18:18
河口湖駅より。2025年の富士登山シーズン最後の土日はいい天気だった。来年はどのルートで登ろうか。
 今夜は皆既月食。疲れて眠ってしまったがいい月夜だった。
今夜は皆既月食。疲れて眠ってしまったがいい月夜だった。
 1
1
9/7 18:18
今夜は皆既月食。疲れて眠ってしまったがいい月夜だった。



























 へるにゃん
へるにゃん

 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大
 拍手
拍手


















































































































































































































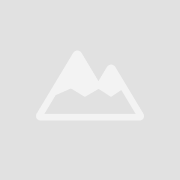















いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する