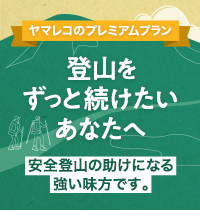小辺路(こへち)
最終更新:2025-05-04 00:52 - silverfrost
基本情報
紀伊山地の熊野参詣道のひとつで、高野山と熊野本宮を結ぶ全長72kmの参詣道。
紀伊半島中央部を南北に縦断し、途中には伯母子山をはじめとする標高1,000m以上の峠を三度も越える、熊野参詣道の中でも最も険しい道でもある。
現在では2泊3日または3泊4日の行程とするのが一般的。
その行程には、日本二百名山に数えられる伯母子岳が単独で含まれ、または護摩壇山を寄り道として歩かれる場合がある。
基本的には、交通至難であることも手伝って歩く人も少なく、静謐な雰囲気が保たれている。
▼和歌山観光 全ルートマップ他
https://www.wakayama-kanko.or.jp/asset/map/kohechi
▼田部市熊野ツーリズムビューロー
https://www.tb-kumano.jp/kumano-kodo/kohechi/
紀伊半島中央部を南北に縦断し、途中には伯母子山をはじめとする標高1,000m以上の峠を三度も越える、熊野参詣道の中でも最も険しい道でもある。
現在では2泊3日または3泊4日の行程とするのが一般的。
その行程には、日本二百名山に数えられる伯母子岳が単独で含まれ、または護摩壇山を寄り道として歩かれる場合がある。
基本的には、交通至難であることも手伝って歩く人も少なく、静謐な雰囲気が保たれている。
▼和歌山観光 全ルートマップ他
https://www.wakayama-kanko.or.jp/asset/map/kohechi
▼田部市熊野ツーリズムビューロー
https://www.tb-kumano.jp/kumano-kodo/kohechi/
山の解説 - [出典:Wikipedia]
小辺路(こへち)は、熊野三山への参詣道・熊野古道のひとつ。高野山(和歌山県伊都郡高野町)と熊野本宮大社(和歌山県田辺市本宮町本宮)を結び、紀伊山地を南北に縦走する。小辺路は弘法大師によって開かれた密教の聖地である高野山と、熊野三山の一角である熊野本宮大社とを結ぶ道である。熊野古道の中では、起点から熊野本宮大社までを最短距離(約70キロメートル)で結び、奥高野から果無山脈にかけての紀伊山地西部の東西方向に走向する地質構造を縦断してゆく。そのため、大峯奥駈道を除けば最も厳しいルートである。(→#自然誌参照)
近世以前の小辺路は紀伊山地山中の住人の生活道路であり、20世紀になって山中に自動車の通行できる道路が開通してからも、おおよそ昭和30年代までは使用され続けていた。そうした生活道路が、熊野と高野山を結ぶ参詣道として利用されるようになったのは近世以後のことであり、小辺路の名も近世初期に初出する。小辺路を通行しての熊野ないし高野山への参詣記録は近世以降のものが大半を占め、近世以前の記録もいくつか確認されているが少数である。(→#歴史参照)
高野山(和歌山県伊都郡高野町)を出発した小辺路はすぐに奈良県に入り、吉野郡野迫川村・十津川村を通って柳本(十津川村)付近で十津川(熊野川)に出会う。柳本を発って果無山脈東端にある果無峠を越えると和歌山県側に入り、田辺市本宮町八木尾の下山口にたどり着く。ここからしばらくは熊野川沿いに国道168号線をたどり中辺路に合流し、熊野本宮大社に至る。(→#小辺路の峠参照)
古人のなかには全ルートをわずか2日で踏破したという記録もあるが、現在では2泊3日または3泊4日の行程とするのが一般的である。日本二百名山に数えられる伯母子岳が単独で、または護摩壇山の関連ルートとして歩かれている 他は交通至難であることも手伝って歩く人も少なく、静謐な雰囲気が保たれている。また、高野山から大股にかけてなど著しい破壊の見られる区間(後述)も若干あるものの、良好な状態の古道がまとまって残されている点も評価されている。
ただ、全ルートの踏破には1000メートル級の峠3つを越えなければならず、一度山道に入ると長時間にわたって集落と行き合うことがないため、本格的な登山の準備が必要で、さらに冬季には積雪が見られるため、不用意なアプローチは危険と言われている。
高野山では町石道、黒河道、京大坂道、女人道、大峰道、有田・龍神道、相ノ浦道の高野参詣道と繋がる。